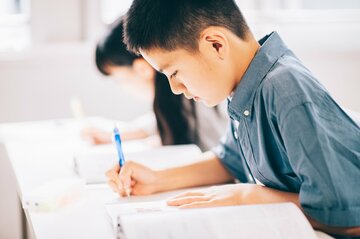Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo
Key Visual by Ayumi Ogawa / Photo
中学受験本番まで残り半年を切った。そんな中で、成績好調組と下降組の差はどこで生まれるのだろう? 実は「宿題のやり方」の差が大きく関係している。なぜ宿題をしなくてはいけないのか、机に向かっているのに宿題が終わらない理由、難関校に合格する子どもが宿題をやる時の共通点など、宿題を通して成績を伸ばすための具体的な方策をお届けする。(国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー 渋田隆之)
「通塾は楽しい」のに
成績が落ちる怖い理由
「塾の授業は楽しんで通えているようだ」「この前の面談でも、担任の先生から『よく頑張っている』と言われた」。それなのに「目の前の模試の成績がどんどん下がってきた」「元のクラスには戻れそうもない」といったお悩みの相談を受けることがあります。
こうした悩みがある一方で、偏差値の意味からも、成績を順調に伸ばしているお子さんが同じ数いるのも事実です。
成績好調組と下降組は、なぜ差がついてしまったのか? それは「持って生まれた能力の差」というより「宿題のやり方」の差です。今回は、この宿題をテーマに具体的なアドバイスをお伝えします。
(1)学年が上がるにしたがって宿題ができなくなる理由
原因は2つあります。1つは「時間が足りなくなること」。学校行事や習い事で忙しくなることに加え、通塾時間や週の通塾回数が増えることで宿題に充てる時間が必然的に短くなります。
そうなると、これまで宿題を「ダラダラ」こなしていた子どもは、とりあえず終わらせることを目的とした「イヤイヤ」やることになりがちです。これでは学習効果は期待できません。
もう一つは、「反抗期の到来」。成長するにつれて親が横について一緒に宿題をやるのを嫌がる子どもも出てきます。
いろいろと注意や指図をされるのが嫌になってきたのに加え、学習レベルが上がってくると「塾の先生より教え方が下手だから、親に教えてもらいたくない」という本音も出てきます。そして、その本音は親に届くことはほとんどありません。