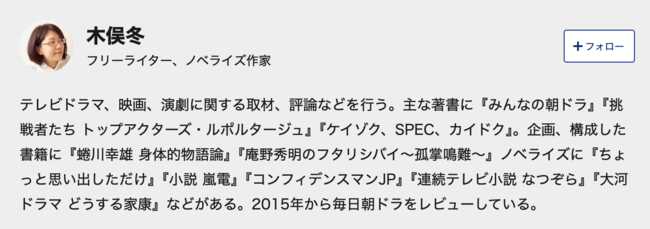戦災孤児たちの対談に感じる違和感、なぜ会議室?
 『あんぱん』第72回より 写真提供:NHK
『あんぱん』第72回より 写真提供:NHK
のぶは戦災孤児たちの座談会を行う。新聞社に5人の子どもたちを招き、写真撮影しながら、みんなの夢を聞く。 働かんでも食えるようになりたい。悪い大人にだまされがちなので、養子になるといいというような話をやけに大人びたことを話す。それを見た論説委員は「甘い」と指摘。復興の鍵を握るのはアメリカなのに、子どもの談話など……というのだ。
つまり、戦争の原因究明や復興のビジョンを取材するのがジャーナリズムだと思っているだろう。だが、東海林やのぶは末端の市民の声を掲載することを目標にしていて真反対のことをやっている。
子どもたちの座談会で興味深かったのは、子どもが案外冷めていることだ。悪い大人に搾取されるのだったら、養子になってぬくぬく生きたいと思っているという現状がよくわかる。実際、戦後そういうふうに思っていたのかはわからないが。
いつの世にも「悪い大人」が存在し、子どもや貧しい庶民をだましているという構造には共感する。
ただ、子どもの座談会を行うときに、なにかお菓子とか軽食とか出さないのだろうか。贔屓(ひいき)になるからやらないのだろうか。謝礼の代わりに食事をさせてあげるのも悪くはないのではないかと思ったのと、写真を撮るなら、焼け跡の彼らの暮らしを撮影したほうがいいのでは、ということ。
のぶは写真を勉強中なので、淡い光で撮ってほしいと撮影位置を指定してカメラマンに「詳しいですね」と感心される。新聞社の会議室で貧しい子どもたちを撮影するのもなんだか違和感を覚えた。もしかしたら、当時、月刊高知で、こういう企画をやっていたのかもしれないが。
東海林は自身の信念をもっているが、「月刊くじら」にピンチがやってきた。遅筆の作家の原稿が落ちた。
おもしろいものを掲載する信念に基づいて、この際、漫画を載せようと考える東海林。そこで活躍するのは――当然、嵩だ。
今朝『あさイチ』では博多華丸は、昨日のような先読みをしていなかったが、明日もきっと嵩の漫画が好評ということになるに違いない。やっぱり落胆よりも楽観がいい。