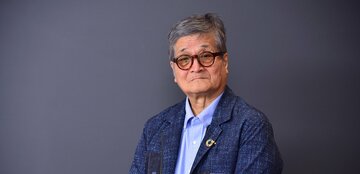人手不足や低生産性に悩む中小企業にとってDX(デジタルトランスフォーメーション)は喫緊の課題だ。しかし一方で、資金力やデジタルスキルの不足といった大きな壁がDX推進に立ちはだかる。そんな中小企業が直面する課題を乗り越えたモデルケースを紹介する。成功の鍵は、“身の丈”に合った持続可能なDXであるかどうかということだ。(取材・文・撮影/嶺 竜一)
自社の身の丈に合わない
高額のシステム投資で2度失敗
広島メタルワーク(本社:広島市)の社長、前田啓太郎氏が創業者の父から事業を継承したのは、経営危機に見舞われた1993年だった。64年の創業以来、ホテルや高級マンションのエントランス回りの装飾や百貨店の階段の手すりなど、意匠性の高い製品を製造してきたが、バブルがはじけて仕事が激減。7億円ほどあった売上高は半分以下になった。
「ステンレス加工ならなんでもやります」と懸命に営業し、食品機械や半導体装置、医療機器の部品製造などへと領域を拡大した。従来に比べて格段に高いレベルの精度が求められたが、専用の機械を導入し、職人は新たな技術を習得して適応していった。
一方、精密機器の大手取引先がメールで受発注するようになり、多種多様な部品発注が1年先の納品分まで来るようになると、手書きの帳票による管理は限界を迎える。
そこで、広島メタルワークは95年、デジタル化に踏み出した。発売されたばかりのWindows 95を搭載したPCを2台導入。事務所での受発注管理をデジタル化したのだ。
その後、大手製造業では、ロボットと生産管理システムを導入して自動化する動きが加速する。「さらにデジタル化しないと取り残される」と考えた前田社長は、仕事のやり方が変わることを嫌がる現場の反対を押し切って、2000年に大手産業機械メーカーが販売していた生産管理システムを導入した。しかし、期待した効果は得られなかった。
「量産を行う大手企業の生産管理には向いているのでしょうが、うちのように少量多品種の加工を行う中小企業には合わないものだった」と前田社長は当時を振り返る。
 広島メタルワーク
広島メタルワーク前田啓太郎 社長
そこで新たに、グレードの高いシステムを3000万円かけて購入した。それが予算の上限だった。しかし、その金額で設置できたPC端末は事務所に3台、現場に3台の計6台だけだった。
「40人の職人が作業をしている工場に端末が3台しかないから、作業効率が上がるわけがない。作業を終えた職人が『完了』の入力をするために列ができるんです。現場からも事務からも不満が噴出したけれど、だからといって端末を40台設置するとなると億単位の費用がかかる。とても無理でした」
広島メタルワークは月に1万6000ほどの部品加工を行い、その約半数が一点物。端末は3台しかないため、各従業員はこれまで通り、事務所でプリントアウトした図面を基に加工作業を行っていたが、図面に書かれた数字が小さ過ぎてよく見えず、上長に確認したり、端末のある事務所に確認しに行ったりという時間のロスが大きかった。受注が増えるとともに、不良ややり直しも頻発。生産効率はほとんど上がらず、長時間残業が常態化した。2度目のシステム投資も失敗したのだ。