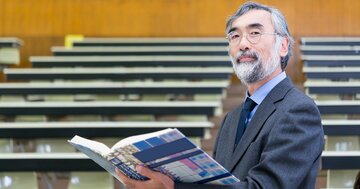国費留学生の割合がこのようになるのは理由がある。
まず、国費留学生には大きく分けて現地の日本大使館から推薦される「大使館推薦」と、大学が文部科学省に申請して枠を取る「大学推薦」の2つが存在する。
前者は国ごとに人数が割り当てられており、その選抜をクリアして来日するのは限られた数の学生たちだけである。
後者については、大学側が申請書を出して応募する性格のものであるが、こちらも出せば通るわけではないし、支給される学生の数も決まっている。
そして何よりも注意しなければならないのは、これらの国費留学生の選考が、彼らの入学前に行われることである。
つまり、いったん私費で来日してきた留学生が、後日、セレクションをクリアして「国費留学生」になる、ということはできない仕組みになっている。
外国人留学生がもらう奨学金は
文科省の「国費留学生」以外にもある
もちろん、留学生が受給できる奨学金は文部科学省が支出する「国費留学生」にかかわるものだけではない。通常、これらを支出する財団等への申請は、留学生自身が行うものであり、大学教員ができるのは推薦書を書く程度である。
しかしながら、一部の奨学金には大学ごとに「枠」が与えられているものがあり、こちらはその「枠」を獲得するために、大学教員がさまざまな機関に申請書を書いて、獲得のための交渉を行う。
筆者の経験した例からその例をいくつか挙げれば、まず、JICAが募集する「人材育成奨学計画」に関わるものがある。
日本政府が各国に拠出するODA資金の一部を利用して、将来の各国の開発に資する人材を日本国内で育成する目的をもって1999年に開始された事業であるが、たとえば「カンボジア・経済2名」といった枠が大学ごとに設けられており、この枠を確保すべく毎年交渉を行っている。