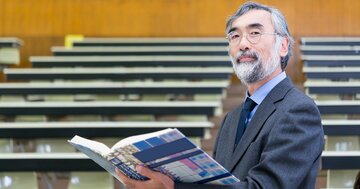負担は2倍になったとしても
教員にとって誇れる仕事に
筆者の勤務先もその1つであるが、結果、教員の教育負担は単純に2倍になった。日本語のコースと英語のコースに別個に授業を提供しなければならなくなったからである。
ちなみに少なくとも筆者の勤務先では、英語で教育を行うコースにいる留学生は、たとえば、アメリカ人やオーストラリア人といった英語の「ネイティブスピーカー」が多くを占めているわけではない。
「英語で教育を行う」のであるから、大学院教育に適応できるだけの英語が理解できればいいのであり、結果、その多くを占めるのはアジア地域からの留学生、ということになる。
加えて、筆者の勤務先ではこの英語コースの学生として、先ほど紹介したような、発展途上国の官僚を日本に派遣する奨学金を受けている学生を多数引き受けているので、これまで筆者が指導してきた英語コースの留学生も、中国や韓国といった近隣諸国や、アメリカやイギリス、スウェーデンといった先進国に加えて、カンボジアやバングラデシュ、キルギス、ラオス、さらにはアフリカのベナン等、その出身国は実にさまざまになっている。
世界中に教え子がいるというのは、ひょっとすると「大学教授のお仕事」の醍醐味の1つかもしれない。
優秀な留学生はその後
日本で大事な働き手になる
こうして留学生の受け入れについて説明していると出てくるのが、日本の大学はあまりにも留学生に依存しすぎているのではないか、という指摘である。
しかしながら、他国と比べた時、日本の大学における留学生比率は決して高くない。たとえば2023年の時点で学部レベルにおける、日本の大学の留学生比率は3.2%。この数字はOECD諸国の平均の5.5%を大幅に下回っている。