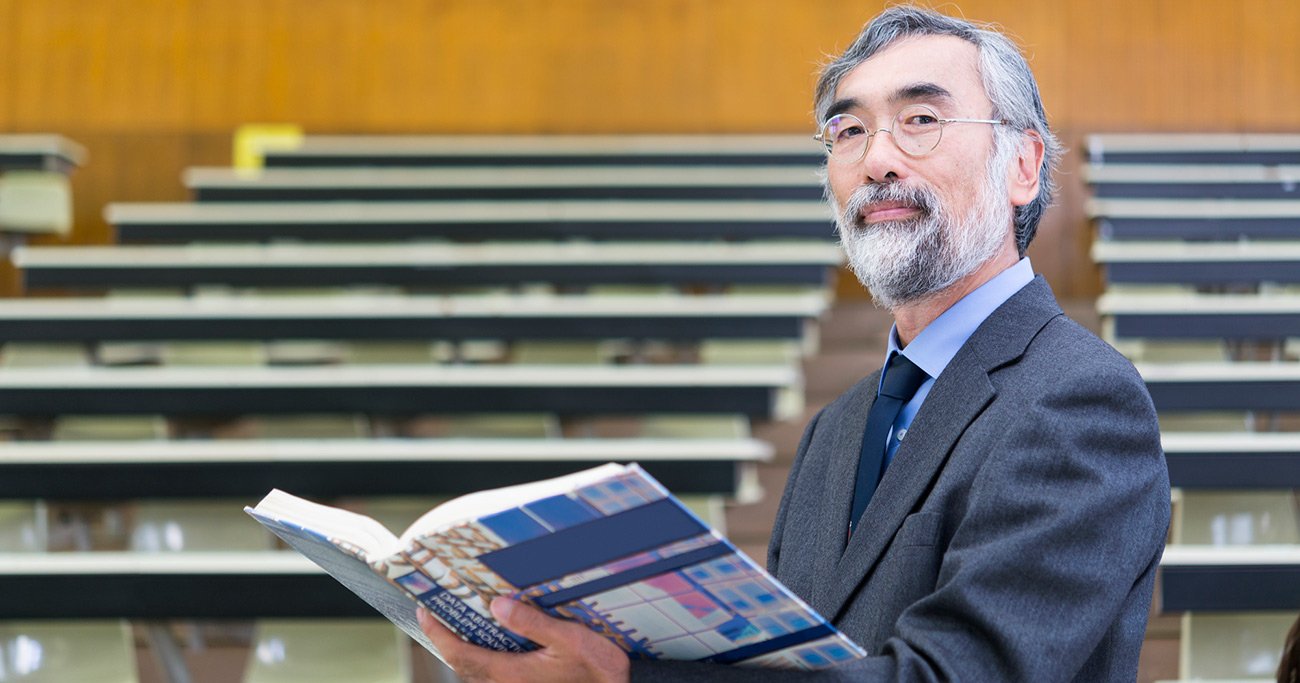 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
大学教授と聞けば、高い知性と人間性を備えた人物のはず。そう思い込んでいる人は少なくないが、現実には、出世するには処世術や政治力が物を言う世界。アカデミアの不条理を、現役のセンセイが赤裸々に明かす。※本稿は、木村 幹『国立大学教授のお仕事――とある部局長のホンネ』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。
教授までの道は長く険しく
昇進基準も大学ごとに異なる
一番下の職階になる助教から大学教員としてのキャリアを始めた場合、次は専任講師か准教授、そしてさらには教授へと進んでいく。
ちなみに、大学や学部・大学院の中には専任講師という職階を置いていないところも多いので、助教から講師を経ずに准教授になることもあるが、同じ大学の同じ部局(編集部注/学部や研究科など)へ助教から教授にいきなり昇進する例は、少なくとも筆者は聞いたことがない(他の大学に移る場合に助教であった人が、教授として採用されることはある)。
昇進に際しては、やはり研究や教育実績等の評価が必要であり、そのつど採用時と同じような審査が行われる。
つまり、履歴書や研究業績の提出が求められ、それらを基に教授会が選んだ人事担当者が審査を行い、報告書をまとめ、最終的にその報告に基づいて教授会で可否が決定される。
採用人事の際と同様、どのような人物をどのような手順で昇進させるのかについては、大学本部の了承も必要であり、事前に会議にかけて許可を得る必要がある。
逆にいえば、これらの審査を通る基準を満たさないと、大学教員はいつまでも同じ職階に留まりつづけることになる。以前は年功序列が重視され、誰かが昇進できないとそれより若い人が困る、などという事態も存在したが、最近ではあまりそういうことは気にしないところも増えている。







