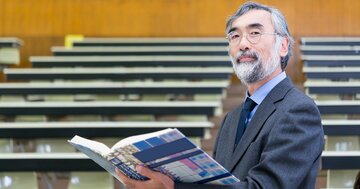写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
大学教員は「先生」と呼ばれ、尊敬をもって扱われることが多い。だがその環境が、ハラスメントの蔓延という思わぬ事態を招いている。なぜ大学で人間関係のトラブルが絶えないのか。現役の部局長がその背景に迫る。※本稿は、木村 幹『国立大学教授のお仕事――とある部局長のホンネ』の一部を抜粋・編集したものです。
「2番じゃダメ」な競争社会で
教員同士が蹴落とし合う事態に
大学教員にとっての人間関係というと、どんなことを想像されるだろうか。「教授会で口角飛ばして議論する教授たち」「舌鋒鋭く学会で論敵を追い詰める学者の群れ」といった感じかもしれない。
筆者の感じるところでは、大学教員の人間関係には、まったく異なる2つの面が存在する。
1つは「個人の名前」で作る人間関係である。とりわけ研究者としての大学教員は、自らの名前を出して論文や著書を書く仕事なので、大学や部局といった所属先ではなく、学会や学外の会議で培った個人的な人脈が重要になる。
研究を続けるためには「営業」も必要なので、人間関係の作り方もアグレッシブで前向きになりがちだ。そこでは彼らは、自らの優秀さを競い合い、他人を押しのけるかのように生きている。
少し古い表現を使えば、「2番じゃダメなんですか」と問われて、ダメなのがこの業界だからである。だから、大学教員はときに、自らが「2番から1番」になるために、相手を押しのけ、自らの優秀さを誇ろうとする。
だが、大学教員の人間関係には異なる側面もある。文部科学省の統計によれば、4年制大学だけで19万人、短大と専門学校をあわせれば20万人強も日本国内にいる大学教員であるが、その出身大学を見れば一定程度、特定の大学に集中していることがわかる。