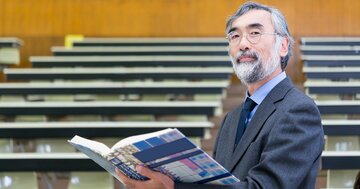外務省やJICAでは、留学生の選抜を行うことが困難なので、そのセレクションについても大学側が担当することになっており、筆者もこの仕事で中国、フィリピン、カンボジア、バングラデシュ、キルギス等に出張したことがある。
類似したものにやはりJICAの長期研修員制度や、インドネシアの公務員を現地大学と共同で教育する「リンケージ・プログラム」などが存在する。
奨学金には国際機関が拠出するものもあり、筆者の勤務先ではアジア開発銀行が管轄するものを利用している、こちらも大学の側が交渉して一定の枠を確保している。
日本語の壁を越えるため
英語だけの教育体制を整備
大学教員が留学生の受け入れのために行う仕事のもう1つは、制度の整備である。
たとえば、その代表的な事例として、一時期、文部科学省によって強く奨励された「英語コース」の設置がある。
背景には日本における留学生の受け入れ拡大を行うには、日本語の存在が大きな壁となっている、という理解があった。
つまり、日本語が話せる学生を受け入れるだけでは、留学生数の一定数以上の拡大は望めないから、思い切って日本語の負担を免除し、英語だけで教育を受けさせれば、より多くの優秀な学生が日本に来ることができるだろう、と考えたことになる。
とりわけ大学院は専門的な知識を学ぶところであり、多くの研究分野では英語にて議論がなされている。だから、その専門的な教育にわざわざ日本語を介する必要はない、というわけだ。
このような日本語を話さない留学生の受け入れは、21世紀に入り急速に拡大したが、当初は大きな問題が存在した。多くの大学院は、これらの留学生の受け入れを従来の教育課程で行ったからである。
結果、これらの大学院では、教育において日本語と英語を「ちゃんぽん」で行う事態が生じ、「英語だけで学習できる」環境を求めて来た留学生に大きな不満を持たせることとなった。
このような状況を受けて、各大学ではやがて従来からの日本語で行うコースとは別に、英語のみで教育を行う専用のコースを設けるようになった。