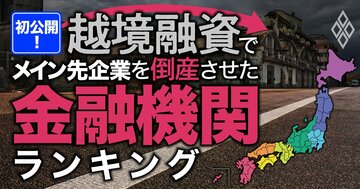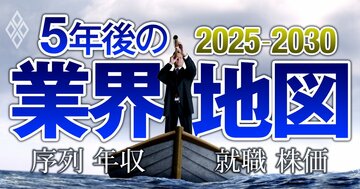中核プロセスは千差万別
試行錯誤するしかない
製造業DXの進展については、どのように見ていますか。
製造現場向けのデジタルツールは充実してきました。多くの工場に共通するプロセスであれば、ツールの導入が効果を発揮する場合もあるでしょう。ただ、製品によって工場の中核プロセスは千差万別です。その中核プロセスを変革しようとすれば、自分たちで工夫し試行錯誤するしかありません。そんな時に重要なのが「聞き役」の存在です。「このプロセスにセンサーを入れて可視化したい」「このプロセスにAIを導入すれば生産性が高まるのではないか」といった話を誰かにぶつけることで、思考が深まったり、より実践的なアイデアが生まれたりします。大企業なら外部のコンサルタントやITベンダーを聞き役にしてもいいし、中小企業なら都道府県の産業技術センターなどを訪ねてもいいでしょう。
日本の製造業は現場が強いといわれますが、現場が強すぎるがゆえにDXが進まないとも聞きます。
製造業ですから、現場が強いのは基本的に好ましいことだと思います。したがって、現場における変革マインドの醸成が決定的に重要です。現場のキーパーソンがデジタルに関心と親近感を持てば、DXは進みやすいでしょう。とはいえ、それが難しいのも確かです。人の意識はなかなか変わりません。「変わらないために、変わり続ける」という言い方がありますが、マインドを変えるにはこうした働きかけが効果的ではないでしょうか。
工場の人に「変えろ」と言っても反発されるだけです。そうではなく、自社の強みや本質的な部分を維持するため、つまり「変わらないために、変えよう」と呼びかける。現場の抵抗感をいかに取り除くか、DXに前向きな機運をいかにつくるか。現場がよくなるというロジック、あるいはストーリーづくりが大事ですし、経営者や変革リーダーの人間力が問われる場面でもあります。
工場におけるデジタルツイン、スマートグラスなどの可能性については、どうお考えでしょうか。
それらのテクノロジーもパーツの一つであり、どこで、どのように使うか次第です。有用な活用法は多くあるでしょう。たとえば、工場のラインで働く外国人が多ければ、流れてくる製品のラベルをスマートグラスで翻訳すれば生産性が高まるかもしれません。また、デジタルツインは、先ほど述べた「地上100メートル」の視点を得るのに役立つ可能性があります。工場の長く複雑なプロセスをバーチャル空間で再現できれば、プロセスの棚卸しと効率化につながるかもしれません。
製造現場にもAIの活用が広がりつつあります。テクノロジーはものづくりをどう変えるのでしょうか。
私の答えは単純で、「わかりません」としか言いようがありません。インターネットの普及期、セキュリティ市場がこれほど大きくなることを私は予想できませんでした。洗濯機が登場した後では、人々が毎日のように着替えをするようになり、結果として衣類の市場が大きく拡大したそうです。そんなことは誰も予想できません。デジタルやAIによる影響も同じです。濃い霧の中を進むようなものですから、試行錯誤型のアプローチしかないと思います。小さな失敗を繰り返し、失敗から学んで次につなげる。粘り強く、地道な活動が求められます。ソニーやホンダの草創期の物語を持ち出すまでもなく、日本の製造業は本来それが得意なはずです。
◉企画・制作|ダイヤモンドクォータリー編集部 ◉構成・まとめ|津田浩司 撮影|佐藤元一