AIやIoTなど最新テクノロジーが製造現場に導入され、DXの取り組みが活発になっている。しかし、そうした取り組みが成果につながっていないケースが少なくない。DXをビジネス価値につなげるためには、どのようなポイントに注意すべきだろうか。東京大学大学院工学系研究科教授の森川博之氏に話を聞いた。
DXを駆動する「大義」と
リーダーの「人間力」
編集部(以下青文字):多くの企業がDXの取り組みを強化しています。
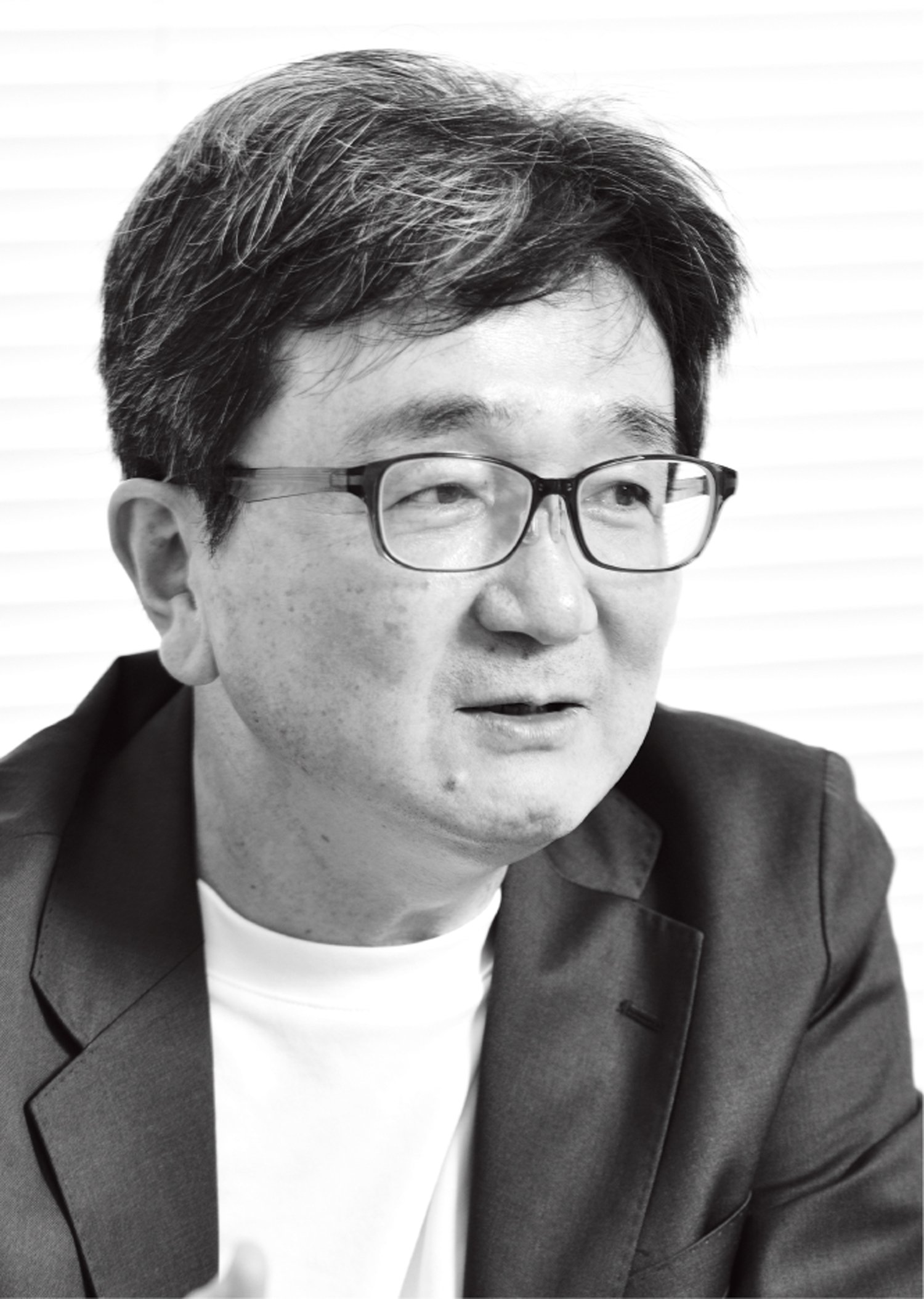 東京大学大学院 工学系研究科 教授
東京大学大学院 工学系研究科 教授森川博之
HIROYUKI MORIKAWA 1987年東京大学工学部卒業。2006年東京大学教授。モノのインターネット、DX、無線通信システム、情報社会デザインなどの研究に従事。情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)会長、Beyond 5G新経営戦略センター長、情報社会デザイン協会代表理事なども務める。電子情報通信学会会長、OECDデジタル経済政策委員会(CDEP)副議長、総務省情報通信審議会部会長などを歴任。著書に『データ・ドリブン・エコノミー』(ダイヤモンド社、2019年)など。
森川(以下略):「AIがすごいらしいから使ってみよう」とか「我が社もIoTをやろう」といった〝技術ありき〟の発想では、DXを成果につなげることは難しい。よくいわれることですが、明確な目標が必要です。たとえば、業務プロセスを一つ省ければコストを削減できます。それを可能にするデジタルツールがあるなら活用すればいい。それがDXです。その意味で、日本企業が数十年前から取り組んできたBPRとDXは、本質的には同じものだと思います。
しかし、既存業務に慣れていると、変革も困難かと思います。
誰しも、固定観念を取り払うのは難しいものです。そのためには、外部の目が有効です。物事を別の角度から見れば、新鮮な疑問や気づきが生まれます。また、俯瞰する視点を持つことも重要です。現場の人たちは地上で活動しているので、担当業務の細かいところまで目が届きます。一方で「地上100メートル」の視点から見れば業務プロセスの全体像をとらえることができます。それは、重複業務や冗長すぎるプロセスの発見につながるでしょう。新たな価値創造や全体最適化へのヒントが見つかるかもしれません。
価値創造のアプローチで、注意すべきポイントはありますか。
私はよく「テトリス」に例えて説明しています。さまざまな形のパーツを回転させながら、組み合わせることで何らかの価値を実現するのです。パーツは人であり、技術、企業の設備などです。これらをうまく組み合わせれば、新たな価値が生まれます。その際、各パーツを集めるための「引力」のようなものが必要で、それが「大義」です。「社会課題を解決したい」「誰かの困り事を何とかしたい」など、多くの人たちの共感を得られる大義を示すことで、テトリスのパーツが集まります。同時に、大義を掲げるリーダーの「人間力」も重要です。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





