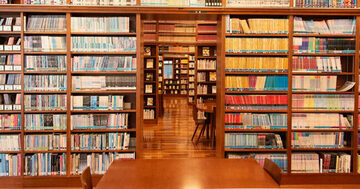旧幕臣である創立者の思い
 講堂前に立つ創立者江原素六の銅像
講堂前に立つ創立者江原素六の銅像
吉原 イギリスの財閥の手先となって動いた薩長藩閥が、この世を利権の支配する世の中にして、天皇陛下の宣旨で、言論を封殺したのが明治時代です。そのことを見抜いていた旧幕臣は、カネではなく人が大事だと自由民権運動を行い、人倫の道や独立自尊を大切にする正しい形での近代化を進めました。渋沢栄一や福沢諭吉がそうです。
――(缶入りドリンクを手に取って)これは沼津(静岡県)のお茶ですね。
吉原 創立者の江原素六は旧幕臣で、1868(明治元)年の徳川宗家の駿河移封に伴い沼津に移住しました。沼津兵学校や沼津中学校(現・県立沼津東高校)、駿東高等女学校(同沼津西高校)の設立者や発起人となり、沼津師範学校の校長を務めました。
牧場やお茶の輸出会社もつくり、そのご縁で今も沼津市と麻布学園はつながりがあり、2023年には包括連携協定も結びました。江原は、静岡県議会議員から1890年の第1回衆議院議員選挙でここの選挙区から立候補し当選。板垣退助の自由党に所属しました。
――キリスト教主義の学校の方は「文部省訓令第12号」(1899年)のことをよくお話になられますね。
吉原 「一般ノ教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルノ件」で、「課程外タリトモ宗教上ノ教育ヲ施シ又ハ宗教上ノ儀式ヲ行フコトヲ許ササルヘシ」という宗教教育を禁じるものでした。
日清戦争後、国粋主義化、つまり天皇陛下の政治利用をさらに進めようとする薩長政府に対して、当時の衆議院では、幕臣であった渋沢栄一や大倉喜八郎、三井の増田孝らが、代議士である江原先生を応援して、「宗教教育を否定すると人間は動物になってしまいますよ。日本人がみんな動物になったら困ります」とユーモアを交えながら、この訓令に反対する論戦を交わしています。
――キリスト教主義の学校にとっては存立の危機だったわけですね。
吉原 それでも強行されてしまい、江原先生は悩んだ。この10年前に東洋英和学校(現・東洋英和女学院)幹事となり校長も務めた。95年に麻布尋常中学校を東洋英和内に設立し、初代校長になっていた。この麻布尋常中学校が正規の学校と認められないと、ここで学ぶ生徒たちの大学進学への道が閉ざされてしまう。
マルティン・ルター『キリスト者の自由』には、「キリスト者は、あらゆるもの、最も自由な主であって、何ものにも隷属していない」「キリスト者は、あらゆるもの、最も義務を負うている僕(しもべ)であって、すべてのものに隷属している」とある。
このクリスチャンとしての「愛と誠」の心と四書五経に代表される武士道の精神。こうした理想と情熱を持った麻布の生徒が大学に進学し、社会で活躍していかないとこの日本は終わりだ。ここは隠れクリスチャン学校をつくるしかないということで、この訓令の翌1900年に、現校地である秋月藩(現・福岡県)上屋敷の土地を求めて移り、麻布中学校と改称しました。『江原素六伝』には一言、「訓令第12号があって麻布学園をつくった」としか記載されていないので、こうした江原先生の苦渋の決断が分からないのです。
――そこに麻布生の使命があるわけですね。
吉原 自由というのは精神の自由です。新自由主義的なおカネにとらわれる生き方ではありません。江原がカナダ・メソジスト教会で洗礼を受けた1877年は、権力者が有能な官僚が欲しいと東京大学を設立した年で、その5年後に帝国大学になります。
この間、憲法制定を巡る政争で起きた「明治14年の政変」(1881年)では、物事を考え、しゃべりすぎる連中は邪魔だと、大隈重信や福沢諭吉の門下が排除され、大隈は翌年に東京専門学校(現・早稲田大学)を設立しました。慶應義塾もこのころ没落の一途をたどるわけですが、福沢諭吉は、東大のように試験をやって管理するのは学問ではない、独立自尊、自分で考え、汝の志を立てるのが正しい教育だと批判しています。
こうした麻布設立の真実を在校生もOBもあまりご存じではない。そこで5000字の論文を書いて、先生方と1万6000人の卒業生に配りました。今年はこれを伝えるために各同期会を回り、併せて1人年間1万円の寄付を呼び掛けていこうと思います。
 左が創立100周年記念館(図書館)、右が創立120周年記念体育館 その間には中国大使館も見える
左が創立100周年記念館(図書館)、右が創立120周年記念体育館 その間には中国大使館も見える