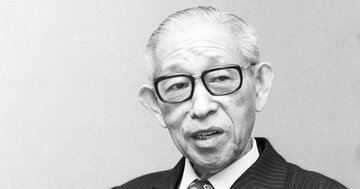写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
後継者がいない。その不安を救うはずだったのが、M&Aという“出口戦略”だった。老舗企業が信金と仲介会社の支援を受けて進めた事業承継――。だが、契約からわずか数カ月後、想定外の事態が起きる。経営者保証、買い手の素性、そして見落とされたリスク。「譲る」つもりだった決断が、なぜ「背負う」苦悩に変わったのか。中小企業を破産へと追い込んだ“M&A仲介の罠”の実態を追う。※本稿は、藤田知也『ルポ M&A仲介の罠』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
勝負服の蝶ネクタイで
M&A成立の記念写真
大阪市の大手信金本店の11階にある来賓会議室で2023年10月24日午前10時、新宿屋(編集部注/婦人靴の製造販売。1974年創業)を売り買いする「ご成約式」が開かれた。
その場を取り仕切ったのは、売り手のFA(編集部注/M&Aで、企業の買い手または売り手のどちらか一方に寄り添い、交渉から契約成立までをサポートをする専門家)を務める信金の承継支援課の担当者2人と、買い手のFAであるM&A DX社の担当者2人だ。
株式譲渡契約書に調印し、代表者の変更手続きを済ませたのち、株式の代金として百円玉を入れた封筒がA氏に手渡された。契約上の代金は60円だが、「お釣りは結構です」と言われた。
1カ月前に「800万円で譲り受けたい」と提案されたM&Aは結局、自分の会社の口座から600万円の退職金と200万円相当の社有車を受け取る取引となった。諸経費を引いた約560万円を新宿屋からA氏の個人口座に振り込み、そのうち550万円を「成功報酬」などの名目で信金に振り込んだ。
会社の実印や銀行印を受け取った買い手のM氏は、役員を代える手続きのために法務局へ向かった。
信金の担当者らはA氏を別室に案内し、数年前に最初の融資を担当した職員とサプライズで引き合わせ、A氏が勝負服とする蝶ネクタイを締めて記念写真に納まる演出もした。
これが会社を倒産に追い込む「門出」になるとは思いもしなかった。