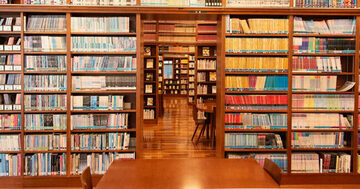麻布の正門。道沿いの季節の花は園芸好きの平秀明校長の手による。右はカタール大使館
麻布の正門。道沿いの季節の花は園芸好きの平秀明校長の手による。右はカタール大使館
20年前の危機を乗り越えた麻布の学園としての原点は何か。創立から130周年の今年、改めて創立者である江原素六(えばらそろく)の思いを振り返る。麻布生として、吉原毅理事長が心掛けてきたことにも耳を傾けよう。(ダイヤモンド社教育情報、撮影/平野晋子)
吉原 毅(よしはら・つよし)
学校法人麻布学園理事長

1955年東京・蒲田生まれ。麻布中学校・高等学校、慶應義塾大学経済学部卒。77年城南信用金庫に入職、企画部時代に小原鉄五郎・第3代理事長から薫陶を受け、92年理事兼企画部長、2006年副理事長を経て、10年理事長就任、17年顧問(20年より名誉顧問)。麻布学園理事を経て、17年より現職。24年千葉商科大学副学長、25年横浜商科大学理事長に就任。他に、公益財団法人小原白梅育英基金理事長、原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長、労働者協同組合ワーカーズコープセンター事業団監事、一般社団法人かながわ農福連携推進協会会長、立正大学評議員など。著書に『信用金庫の力』(岩波書店)、『原発ゼロで日本経済は再生する』(KADOKAWA)、共著に『この国の「公共」はどこへゆく』(花伝社)、『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』(小学館)など多数。
創立130周年から先を考える
――創立100周年で図書館、120周年で体育館を新築しました。130周年の今年は何を。
吉原 今年は余裕がないので、特別演奏会(8月3日、サントリーホール)のみです。
――指揮の鈴木優人さんとピアノの山下洋輔さんがOBなのですね。これから先の学園の課題とは何でしょう。
吉原 まず、校舎をどうするのかという問題があります。鉄筋3階建ての本校舎(1932年築)は躯体が丈夫で、私たちが学んだ時そのままの建物です。後から建てた理科棟や芸術棟には耐震補強をしました。最近は建設費も高騰していますし、すぐに建て替えると財務がまた厳しくなります。
とりあえず、アメニティーの改善からということで、空調を変えたりトイレの改装をしたりしたところ、見違えるようにきれいになりました。
――卒業生に伺うと、昔は校舎の中がボロボロで、教室の後ろにはネズミが住んでいたりしたと(笑)。全員が出席するわけでもなかったので、そもそも生徒の数だけ机がなかったという話も聞きました。
吉原 一生懸命さぼりましたからねえ。床板が古くて、歩くとボコッと音がして穴が開いたりしました(笑)。今は300人で7クラスですが、当時は5クラスで、1クラスに55~60人もいましたから。驚いたのですが、最近では6年間皆勤という子がたくさんいる。昔はほとんどいませんでしたから、最近の生徒さんはみんな真面目ですね。
――資金的なこともあって校舎の建て替えなどは検討中ということですが、何か手は打たれたのでしょうか。
吉原 校門からの校道は幅6mしかありません。既存不適格の状態で、校舎の建て替え工事をするにも、生徒の避難路としても、公道に接する校道の幅10mは必要です。創立時は公道に接している土地も保有していたのですが、当時は財務的に苦しかったため、切り売りされてしまった。そこで、校道を将来的に拡幅できるよう、隣の建物を投資物件として購入しました。発想の転換でした。
――反対側の建物は大使館で、こちらは難しそうですからね。
吉原 30年ローンを組みました。賃貸収入とローン返済額がほぼ同じです。東京都からは「都内の私立学校で賃貸マンション経営をするのはお前の所だけだ」と難色を示されたりもしました。目的は将来的な校道の拡幅にあるので、何とか説得しました。使っていないグラウンド端の一部敷地を売却することも理事会で提案され、これも返済に回しました。
――このあたりは手堅く進めている。創立140周年の頃には見えてきますか。
吉原 早ければローン返済を始めて15年目くらいから次の手を打てそうです。本校舎を建て替えるのがいいのか、それよりも教育のソフト面、例えば国際交流や理科・芸術の強化に使うのがいいのか、これからの理事会で考えることになります。
 校門からの狭い校道の拡張も課題。右が取得した建物
校門からの狭い校道の拡張も課題。右が取得した建物