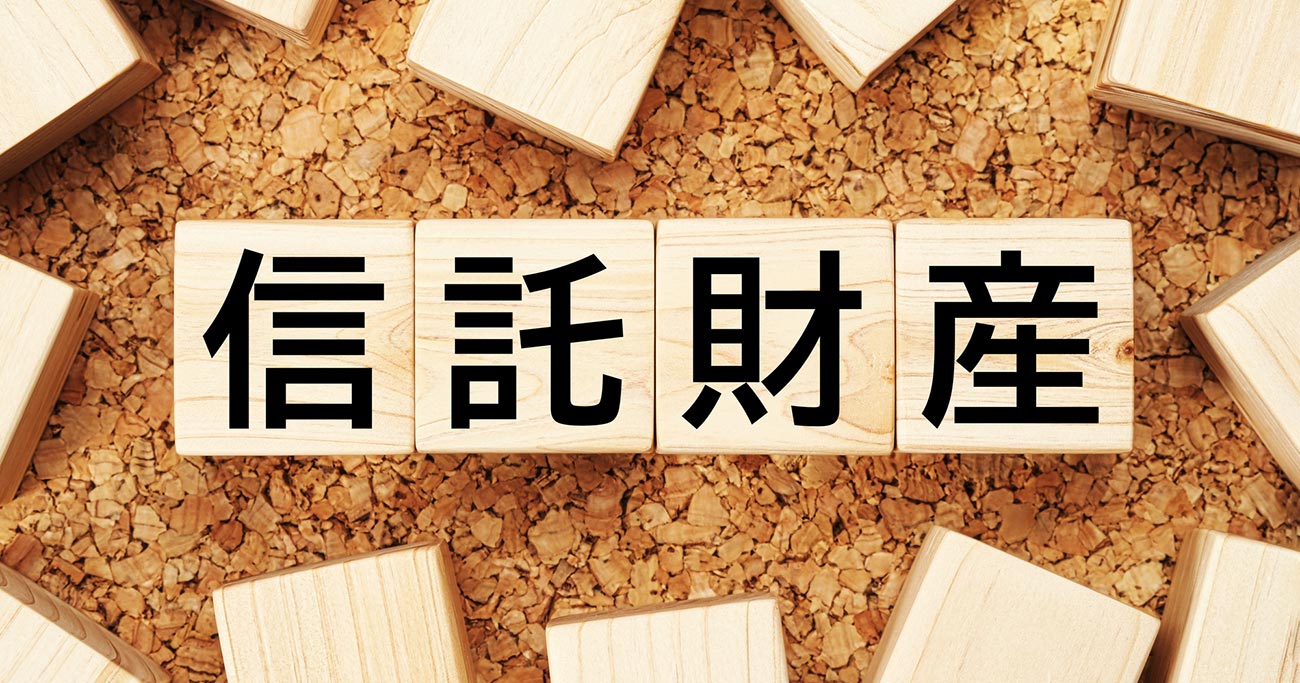 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
*本記事はきんざいOnlineからの転載です。
承継先の指定と指図権者の指定
信託の大きな特徴は、設計の自由度が高いことであり、ファミリーガバナンスの実効性を高める法的枠組みとして有効なツールになる。具体的には、「承継先の指定」と「指図権者の指定」という、信託を活用した二つの機能が主に活用されている。
承継先の指定とは、信託した財産(株式等)の相続発生後の行き先を指定する機能である。類似した機能に遺言があるが、遺言は遺言者の相続時に承継する行き先を指定することはできても、さらにその先を指定することはできない。これに対して信託では、当初(第1)受益者の相続発生時の行き先を指定するだけでなく、第1受益者の死亡により他の者(第2受益者)が受益権を取得し、第2受益者が死亡した場合に、別の者(第3受益者)が受益権を取得することをあらかじめ指定できる。これは「受益者連続機能」と呼ばれ、例えば親、子、孫への承継をあらかじめ指定することも可能である。
指図権者の指定とは、信託契約において、信託財産の運用や処分に関する指図者を定める機能である。例えば、株式を信託した場合、株式は信託名義となり、あくまで議決権行使は信託の受託者が実施することとなる。信託契約で受託者に対して議決権行使を指図する者を指定し、その指図に従って受託者が議決権を行使することを規定できる。ファミリーガバナンスにおいては、親が株式を信託し、財産権は受益権として子に承継し、議決権行使の指図権は共同経営者を指定する――といったかたちで活用される。株主間契約で定めることも可能だが、契約の定めに従わない議決権行使も法的には可能であり、第三者である受託者が介在することから、信託の方が確実性を高められると考えられる。







