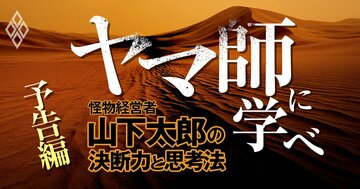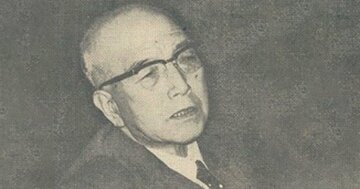Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。太郎は、人脈を「つくる」のではなく「育てる」ことを信条とし、誠実さと地道な努力で信頼を積み重ねてきた。札幌農学校で学んだ「良い果実は良い種子から生まれる」という教訓を「人間植林」と名付け、日々の気配りと誠実な行動で築いた人脈を、後の事業成功の礎としていった。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。
独自の人脈構築の技法
「人間植林」という戦略
人脈は「つくるもの」ではなく「育てるもの」。これは現代のビジネスの世界でも語られる鉄則ですが、それを徹底して体現していたのが、「ヤマ師」こと山下太郎でした。
自分の力を過信せず、有力者の知恵や支援に素直に頼るということを、臆面なくやり続けられることは、太郎の最大の才能だったかもしれません。
太郎が学んだ札幌農学校は当時、「山師、百姓、馬喰(ばくろう)の学校」といわれていました。山師は林業、百姓は農業、馬喰は畜産・獣医のことを指します。もっとも太郎は生涯を通じて農業をすることはなく、乗馬を趣味としながらも馬と関わる仕事もしませんでした。そして山師の学校にいながら林業にも携わらなかったわけですが、後々、別の意味で「ヤマ師」と呼ばれるようになるわけです。
札幌農学校時代、太郎は必ずしも優秀な成績を修めたわけではありませんが、そこでの最大の学びは「良い果実は、良い種子によって生まれる」というものでした。太郎はこの教訓を「人間植林」と呼び、自らの哲学としました。つまり、人間関係も良い種を選び、丁寧に手をかけ、長い時間をかけて育てることで、思いもよらない果実を実らせるものだというのです。
小説『ヤマ師』より引用(P133〜134)
多くの成功者は優れた学才や頭脳でその地位を得る。しかし太郎の場合、自分の力を過信することなく常に有力者の指導を仰ぎ、その支援協力にすがることを処世術のひとつと心得ていた。その道で最も優れた人、力を持った人への近づきを得ることについては努力を惜しまない。人のしない努力を臆面なくできることは太郎の一つの才能だった。
これは札幌農学校で学んだことでもある。学生時代の成績はパッとしなかったが、農芸科で学んだ中で最も印象的なことは「良い果実は、良い種子によって生まれる」という大原則だった。
太郎は、これを「人間植林」と名付けて処世哲学とした。良い人間関係を築くことで、いずれ思いがけない成果を得ることができる。まずは好種子たる人物を見極めること。そして種子が大木に育ち、実をつけるまでには長い年月がかかるかもしれないが、根気強く、緻密に人間関係を深めていくことを心がけた。
多くの成功者は優れた学才や頭脳でその地位を得る。しかし太郎の場合、自分の力を過信することなく常に有力者の指導を仰ぎ、その支援協力にすがることを処世術のひとつと心得ていた。その道で最も優れた人、力を持った人への近づきを得ることについては努力を惜しまない。人のしない努力を臆面なくできることは太郎の一つの才能だった。
これは札幌農学校で学んだことでもある。学生時代の成績はパッとしなかったが、農芸科で学んだ中で最も印象的なことは「良い果実は、良い種子によって生まれる」という大原則だった。
太郎は、これを「人間植林」と名付けて処世哲学とした。良い人間関係を築くことで、いずれ思いがけない成果を得ることができる。まずは好種子たる人物を見極めること。そして種子が大木に育ち、実をつけるまでには長い年月がかかるかもしれないが、根気強く、緻密に人間関係を深めていくことを心がけた。