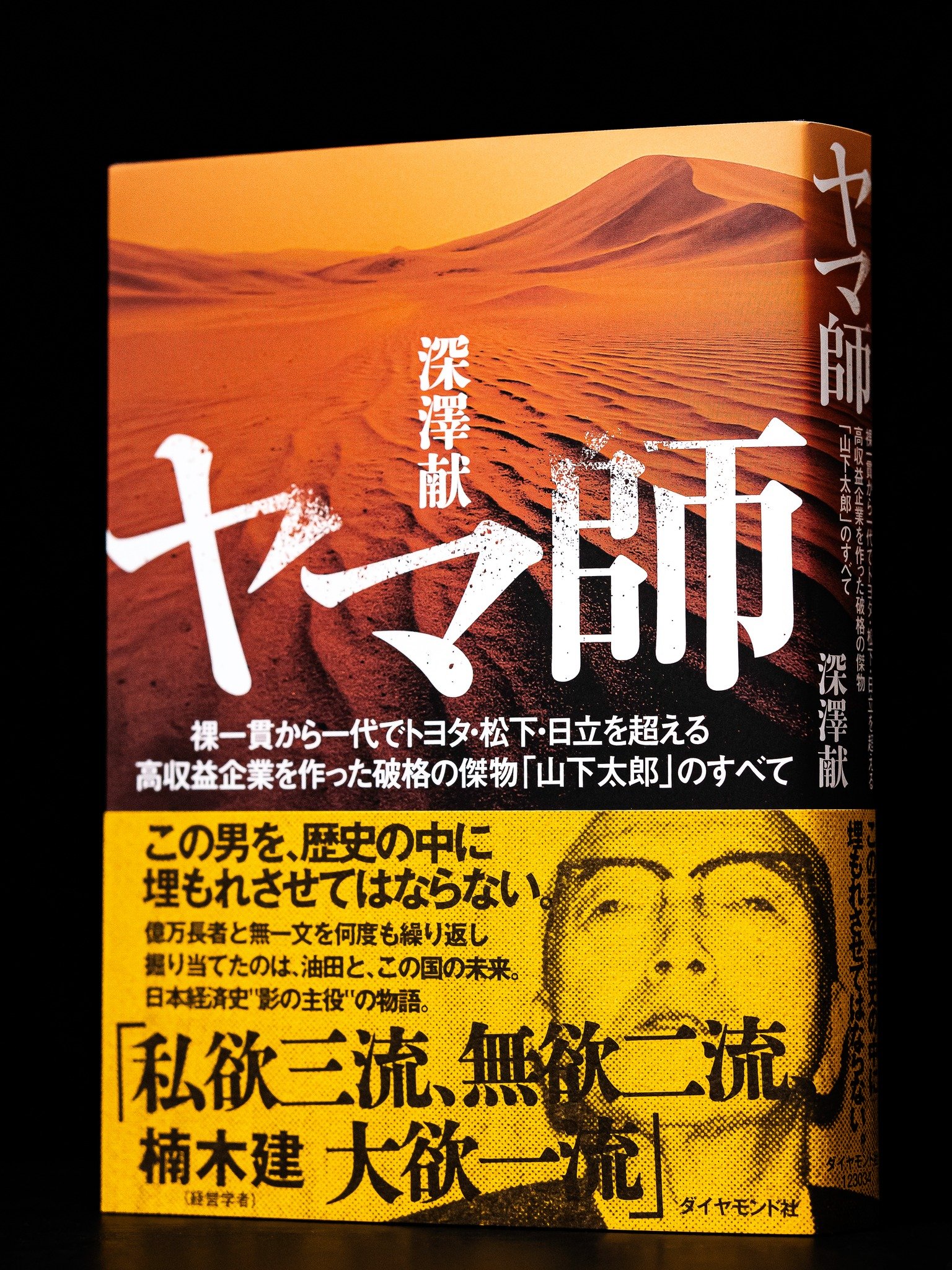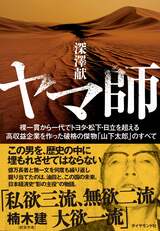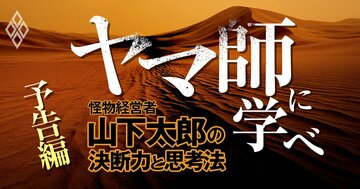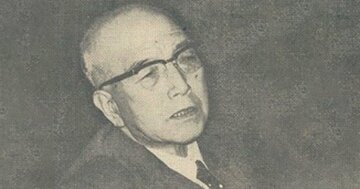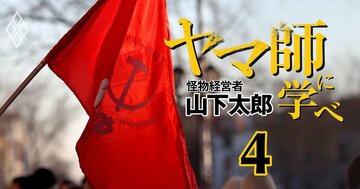暖房形式は、特甲は最先端の近代設備である熱源集中型の温水暖房が導入されていた。子供が立って歩けるほどの大きな地下トンネルにパイプが巡らされ、ボイラーから各戸に温水が供給されている。コックをひねれば1年中、熱いお湯が出る。それ以外の社宅はロシア式のペチカだった。レンガの壁の中に暖炉の煙道をめぐらせて部屋ごと暖める壁暖房である。いずれにしても、こたつや火鉢で暖を取っていた内地より、屋内にいる限りは暖かな生活ができた。
住宅の外壁はすべてレンガ組みで、部屋の窓はすべて二重窓になっている。外側の窓と内側の窓との間が15〜20センチほどあり、ここが冬には冷蔵庫の役割を果たしていた。上、下水道が整備され、トイレは水洗式だった。炊事はガスで行い、役員の家には電話もあった。
こうした住宅の基準は満鉄が定めたものだが、造る側の技術がずさんでは話にならない。特に気密性を保つのが重要で、隙間風などあってはならないし、水漏れもご法度だ。レンガの間に水が浸み込んだ後に凍ると、隙間を押し広げて壁や床をボロボロに崩すからだ。ここが設計監理者の腕の見せどころで、いいかげんな設計や工事では後から何度も修繕が必要になってしまう。
松本の期待に応えるためにも、太郎と市田は資材の調達から施工・監督まで一切手を抜かず、厳格な態度で臨んだ。そのため、最初の450戸の評判は上々だった。他の業者による社宅は、利ざやを取ろうとして粗放に造ったためか、トラブルが続出していた。
その結果、次なる発注が太郎のところに集中した。以後、新規案件は太郎が独占的に受注することになる。一度建ててしまえばあとは自動的に家賃が入ってくる。まさに「カネの成る木」を手に入れたのである。
住宅の外壁はすべてレンガ組みで、部屋の窓はすべて二重窓になっている。外側の窓と内側の窓との間が15〜20センチほどあり、ここが冬には冷蔵庫の役割を果たしていた。上、下水道が整備され、トイレは水洗式だった。炊事はガスで行い、役員の家には電話もあった。
こうした住宅の基準は満鉄が定めたものだが、造る側の技術がずさんでは話にならない。特に気密性を保つのが重要で、隙間風などあってはならないし、水漏れもご法度だ。レンガの間に水が浸み込んだ後に凍ると、隙間を押し広げて壁や床をボロボロに崩すからだ。ここが設計監理者の腕の見せどころで、いいかげんな設計や工事では後から何度も修繕が必要になってしまう。
松本の期待に応えるためにも、太郎と市田は資材の調達から施工・監督まで一切手を抜かず、厳格な態度で臨んだ。そのため、最初の450戸の評判は上々だった。他の業者による社宅は、利ざやを取ろうとして粗放に造ったためか、トラブルが続出していた。
その結果、次なる発注が太郎のところに集中した。以後、新規案件は太郎が独占的に受注することになる。一度建ててしまえばあとは自動的に家賃が入ってくる。まさに「カネの成る木」を手に入れたのである。
チャンスは、手を抜かない者の味方をする
質に徹することで生まれる信頼の連鎖
ここで得た教訓は、「チャンスが来たときに、手を抜かず、全力を尽くす人間だけが信頼を得られる」ということです。
満鉄のような巨大組織にとって、本当に必要なのは、口のうまさではなく「確かな実績」でした。太郎は、それを理解していたからこそ、勝負の場面で「質」に徹し、その後の信頼と継続発注という果実を手にすることができたのです。
一度建てれば、安定して家賃が入る――それは太郎にとって、まさに「カネの成る木」でした。しかし、それは棚ぼたではなく、「努力と信頼の積み重ね」によって自ら育てた木だったのです。
成功とは、努力を惜しまぬ者にだけ許される果実であることを、このエピソードが教えてくれます。
Key Visual by Noriyo Shinoda