これまでの事実関係から
見えてくる重大な問題
割り出しでポイントが損傷したのと同時に指令所の施設指令に故障表示が通知されたが、運行上支障がない軽度の故障との表示だったため、運行を継続した。これは小さな故障で列車を止めていては運行への影響が大きいため、運行に支障のない軽微なものであれば終電後に点検、修理するという判断があるからだ。
当該列車は4番線からポイントを無理やりこじ開けて(割り出して)出発したが、当該ポイントはもともと開通していた3番線側に固定されたままだったので、その後に3番線から発車した8列車の走行に異常はなかった。さらにポイントを4番線側に切り替えたところ、新たに重度の故障警報が発報。現地の点検を行った結果、午後2時46分にポイント故障が判明し、運転を見合わせた。これがトラブル発生までの経緯だ。
これを受けて東京メトロは緊急対策として、
(1) 情報の確実な伝達及び相互確認
(2) 列車情報のずれが発生した際の確実な把握
(3) ポイント通過時の制限速度の遵守
を徹底するとともに、「本件を重く受け止め、外部有識者を交えて背後要因も含めた検証を引き続き行い、その対策を後日公表」するとしているが、ここまでの事実関係から、いくつかの重大な問題が見えてくる。
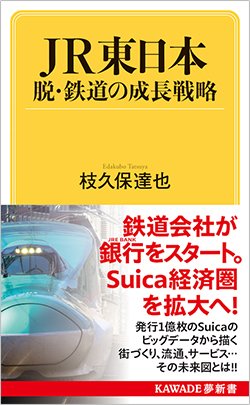 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
運転士については、急行列車と誤認していたのは仕方ないとしても、なぜ本来は到着しない東新宿駅4番線に入線した時点でなぜ違和感を持たなかったのか。また、急行列車と認識していたとしても、割り出したポイントの制限速度時速40キロを守らなかったのはなぜか。
列車番号変更を各列車に通知しなかった(または確実に行わなかった)のは指令所の重大な落ち度である。しかしある意味ではその結果として生じた、指令所と運転士の列車番号に関する認識の齟齬のもと、列車の取り違いが起きた事実はさらに重大である。
特に常時走行状況を監視する保安度の高いATCにおいて、例外的に行われるATC開放は慎重に行わなければならない。しかし今回は列車番号の取り違いにより指令所の意図とは異なる形でATCが開放され、ポイント割り出しや速度超過が発生してしまった。安全対策はハードと人間によって成り立つが、人間側に確認不足や判断の誤りが重なれば、容易に突破し得ることを示した教訓となった。今後の検証と再発防止策に注目していきたい。
4ページ2段落目
「割り出し後、当該ポイントを8本の列車が通過したが、全て4番線から発車する各駅停車であり、割り出した方向のまま走行したため安全や運行に影響はなかった。その後の新たな故障警報が発せられたことにより現地の点検を行った結果、午後2時46分にポイント故障が判明し、運転を見合わせた」
↓
「当該列車は4番線からポイントを無理やりこじ開けて(割り出して)出発したが、当該ポイントはもともと開通していた3番線側に固定されたままだったので、その後に3番線から発車した8列車の走行に異常はなかった。さらにポイントを4番線側に切り替えたところ、新たに重度の故障警報が発報。現地の点検を行った結果、午後2時46分にポイント故障が判明し、運転を見合わせた」
(2025年8月25日 22:58 ダイヤモンド・ライフ編集部)







