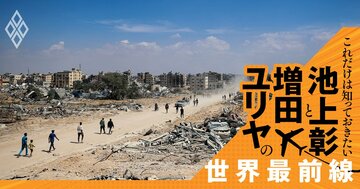パレスチナ問題についても、「ユダヤ人が絶対的な被害者」というストーリーに当てはめて考えている。「せっかく手に入れたこの土地でも、アラブのテロリストが私たちユダヤ人の土地と命をねらっている」というふうに。
その心理を表しているのが、10月7日のハマスによる奇襲がイスラエル社会で「第二のホロコースト」とよばれていることだ。理由は、ユダヤ人の市民にこれだけの犠牲者が出たのは、ホロコースト以来だったからだ。
でも、ハマスは「ユダヤ人を殺すこと」を目的としているわけではない。何度も書いたとおり、ハマスは、イスラエルの占領から生まれた抵抗運動だ。でも被害者意識の強いイスラエル社会には、それが理解できない。
こうしたイスラエルの教育には、根本的な問題がある。本来、人種差別やホロコーストの歴史を学ぶ理由は、「世界中でだれに対しても、このようなことをくりかえされてはならない」という普遍的な人権を学ぶためだ。でもイスラエルで教わるのは、「ユダヤ人の身に、このようなことがくりかえされてはならない」という教訓だ。
それにより、「ユダヤ人の安全のためには、アラブ人を殺してもかまわない」という意識に染まっていく。ガザの子どもを1万6000人も殺しても、「被害者は自分たち」と考えてしまう原点が、ここにある。
国民が軍に寄せる
絶対的な信頼
もう1つのポイントが、「軍への絶対的な信頼」だ。建国直後から紛争をくりかえしてきたイスラエル社会には強い国防意識があり、軍(イスラエル国防軍)は特別な存在になっている。
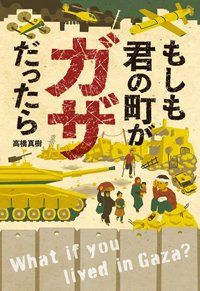 『もしも君の町がガザだったら』(高橋真樹 ポプラ社)
『もしも君の町がガザだったら』(高橋真樹 ポプラ社)
ユダヤ系のイスラエル人は、高校を卒業すると男性は3年、女性は2年の兵役につく。兵役を務めたあとは、一定の年齢まで予備役兵となり、年に1か月の軍事訓練を受ける。家族も友だちもみんなが軍隊の経験者だから、「国民と軍は一体」と考えるようになる。
今も国民の間では「世界でもっともモラルのある軍隊」というスローガンが信じられ、虐殺が指摘されても「軍が悪いことをするはずがない」と考える人が大半だ。
イスラエルは現在、中東で最強の軍事力をもっていて、中東で唯一、核兵器をもっている国でもある。何十年も前から、国の存在がおびやかされるような軍事的な脅威はない。それでも、国民の危機意識は強くなっている。
移民で成り立っているイスラエル社会は、まとまりがない。そこに一体感をもたらしているのが、「恐ろしい敵」への恐怖と、それに立ち向かう「正義の国防軍」という意識だ。この2つは、イスラエル社会に欠かせない存在となっている。