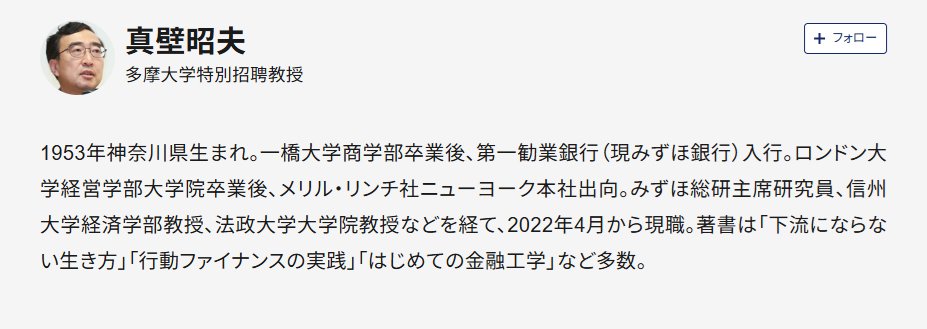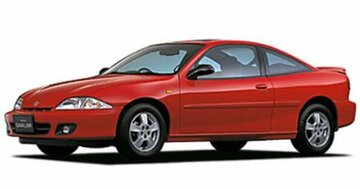「脱レアアース」と「高効率火力発電所」がカギになる
トランプ氏は、大学や研究機関に非常に厳しい姿勢を取っている。7月下旬、米航空宇宙局(NASA)では4000人の職員が退職を届け出た。国立衛生研究所(NIH)、疾病対策センター(CDC)、海洋大気局(NOAA)といった高等研究機関でも、職員が去っている。また、海外の大学などにポストを求める専門家が増えている。
こうした状況が続くと、これまで優位性を維持してきたAI関連や、政治・経済・安全保障などの分野で、米国は世界の覇権国から滑り落ちることになりかねない。
わが国は、そうした展開への対応を急がなければならない。安全保障面では、米国との同盟関係を基礎にすることに変わりはないが、米国一辺倒のスタンスは危険すぎる。極力広い範囲の諸国と連携を強化すべきだ。経済面では、関税引き上げや市場開放など米国からの要求に対応しつつ、自力で多国間の連携を推進する必要がある。
その一つに、レアアースを使用しない、あるいは使用量を抑えた高性能磁石などの製造技術を欧州や、安全保障面で対米関係を重視する新興国に供給することが挙げられる。世界のレアアース生産の70%は中国が押さえている。そのためトランプ氏も中国に弱腰だ。当面、中国がレアアースの輸出管理により、わが国や欧州などに揺さぶりをかけるリスクがある。
わが国の企業は、レアアースの必要性を抑えた高性能素材の製造技術を磨き、高性能モーターなどを実用化した。そうした製造技術を欧州などに提供し、多国間の経済連携の促進に賛同を増やすべきだ。
あるいはAIデータセンターの電力消費量が増える中、新興国に高効率火力発電所の建設、運営技術を供与することも、多国間の連携につながる可能性がある。
国際社会の意思決定は、基本的に多数決に基づく。多国間の連携はとても重要だ。トランプ政策に対しては、わが国は是々非々の立場を明確にする一方で、他国が必要とする製造技術などを積極的に供給していく――これこそ、自力で外需を取り込み、経済社会の安定を目指すのに必要な手法だ。
そうしたスタンスを明確にしないと、わが国はトランプ政策にのみ込まれていくだけだろう。国際社会において相応の地位を維持することは難しくなる。