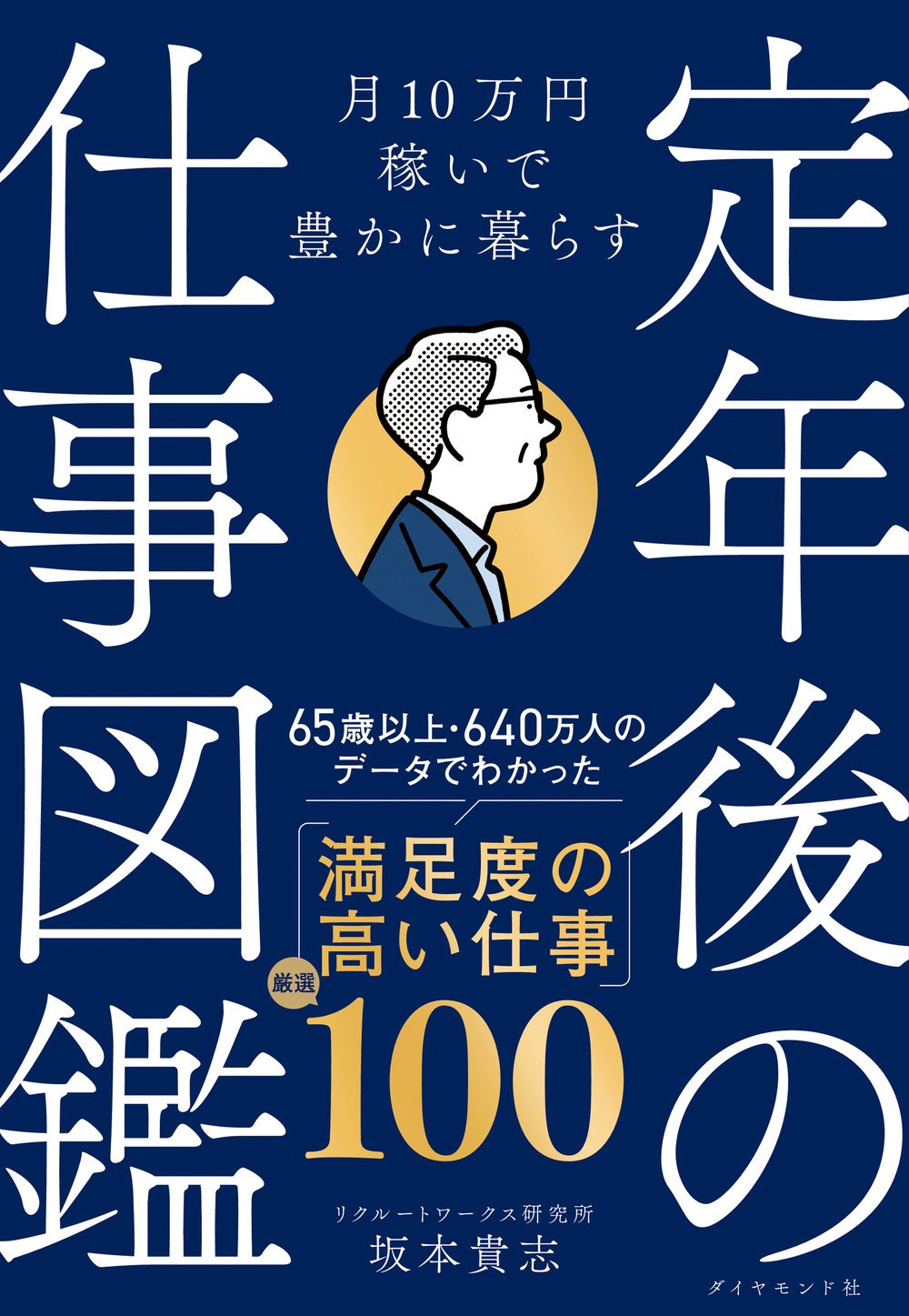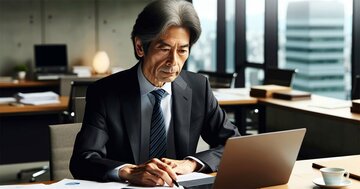働き方が多様化するなか、「定年=引退」というモデルは過去のものとなりつつある。「現役時代のようなフルタイム勤務ではなく、ストレスなく、少ない時間で続けられる仕事があれば……」と考える人も少なくないだろう。では、65歳以降に無理なく働ける仕事にはどんな選択肢があるのか。本記事では『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏にインタビューを実施。仕事の実態を、就業データと当事者の声をもとに紐解いてもらった。(構成・聞き手/ダイヤモンド社書籍編集局、杉本透子)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
60代前半の働き方の選択が「その後の人生」を左右する
――60歳の定年を迎えると、多くの人が「再雇用で今の会社に残るか」「転職や独立で新しい道に挑むか」という選択に直面します。この分岐点は、その後の生活の安定や仕事の満足度に大きな影響を与えるのでしょうか?
坂本貴志氏(以下、坂本):そうですね。特に中高年期――50代から60代半ばにかけての時期は、現役時代の終盤であり、かつ高齢期への入り口でもあります。このタイミングでどのようなキャリアを選ぶかが、その後10年、20年の生活と働き方の方向性を決める大きな節目になります。
――「中高年期」というのは、坂本さんのご著書『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』でも触れられていた3つのステージの真ん中ですね。
坂本:はい。キャリアの長期化を踏まえ、私は仕事人生を大きく3つに分けて考えることを提案しています。
1つ目が「若年~中堅期」で、新卒~50歳くらいまで。ここでは昇進・昇格やスキルアップを重ね、収入を高めることが主なモチベーションになります。
2つ目が「中高年期」で、50歳~60代半ばまで。組織での立場に限界が見え始める一方、年金受給まではまだ稼ぐ必要がある“もうひと踏ん張り”の時期です。
そして3つ目が「高齢期」。60代半ば以降の世代です。年金の支給が始まり、子育ても終わって家計負担が軽くなる時期で、働き方や働く目的が大きく変わります。
60代前半は「再雇用」の満足度が高い。年金にもプラス
――では、定年後すぐの60代前半では、どの選択肢が満足度につながるのでしょうか。
坂本:リクルートワークス研究所の大規模調査によると、60代前半において満足度が高いのは「転職した人」よりも「同じ会社で再雇用で働く人」でした。
――再雇用で働き続けるほうが満足度が高いのですね。同じような仕事をしていても、報酬が減ってしまう、というようなイメージもありますが……。
坂本:確かに、定年前と比べると収入は平均で2割程度下がります。大企業では27%以上も減るケースもあり、中小企業の減少幅は11%台にとどまるなど差はありますが、いずれにせよ下がるのは避けられません。
――それでも満足度が高い理由は何でしょうか。
坂本:やはり、慣れ親しんだ職場環境で、これまでの経験を活かせる安心感が大きいのではないでしょうか。新しい環境への適応という大きなストレスを避けられますし、一定の条件を満たせば65歳までは厚生年金の会社負担も続き、将来の年金額にもプラスに働きます。
定年後の継続雇用は批判的に語られることもありますが、データを見ると、必ずしも不適切な選択とはいえないことがわかります。
多くの方にとっては、60代半ばまではこれまでの経験を活かして成果を出し、その後に別の仕事へ移行するという流れが、中高年期から高齢期にかけてのキャリアのひとつの有力な選択肢になり得ると思います。
転職は「早め」「前向きな理由」がカギ
――では、転職や独立を選んだ場合はどうでしょうか。
坂本:転職を否定するわけではありませんが、60歳直前や定年後すぐに行う場合は注意が必要です。データでは、65歳までの中高年期に転職した人の満足度は、同じ会社で働き続けた人より低く、「不満足」と答える人も多くなっています。収入面でも、転職後のほうが低くなる傾向があります。
ただ、会社都合によってやむを得ず退職する人もいるので、「60代前半の転職はよくない」と一概に言えるわけではありません。
――収入も減ってしまうということで、厳しい現実があるのですね。
坂本:ただし、50代前半に「前向きな理由」で転職した人は満足度が高い傾向があります。体力や気力が十分なうちに、新しい環境で力を発揮できる準備をしておくことが重要です。
「やりたいことがある」「新しい分野に挑戦したい」といった積極的な動機があるかどうかが、結果を大きく左右します。
――転職のパターンにも特徴がありますか。
坂本:中高年期の転職で、典型的なのは大企業から中小企業に移るケースだと思います。中小企業は定年制が緩やかで、65歳まで正社員として働けるところも多いです。結果として、生涯年収が増える場合もあります。
ただし、大企業での専門分野だけに集中してきた方が、中小企業にうつり幅広い業務や人間関係に戸惑うことも少なくありません。そうした変化を受け入れる覚悟と柔軟性が必要です。
60代半ば以降は「小さな仕事」へシフト
――では、60代半ば以降はどうでしょうか。
坂本:この時期になると、働く目的や価値観が大きく変化します。高収入や出世よりも、社会貢献や健康維持、人とのつながりを重視する人が増えるのです。そこでおすすめしたいのが、私が「小さな仕事」と呼んでいる働き方です。
――「小さな仕事」とはどんなものですか?
坂本:報酬は高くありませんが、短時間で無理なく、しかも社会に必要とされる仕事です。
たとえば警備や施設管理、飲食店の接客、販売など、体を動かしながら地域に貢献できる仕事ですね。現役時代とは規模も内容も違いますが、働く手応えを見つけている人が多いです。
――現役世代からは「やりがいがなくなるのでは?」という声も聞こえてきそうです。
坂本:そう感じる方も多くいらっしゃると思いますが、実際には高齢期の就業者の満足度は中高年期より高いという調査結果が出ています。年齢とともに、仕事の価値を“達成”から“貢献”へとシフトしていくプロセスを経るからです。幸福度も50代を境に上昇傾向にあります。
自分の体力・価値観に合った戦略を
――最後に、これから定年後のキャリアを考える方へのアドバイスをお願いします。
坂本:60代前半は「これまでの経験を活かす」時期、60代半ば以降は「無理なく続けられる」時期と位置づけると、自然と選択肢が整理されます。
『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』にはデータや事例を多数掲載していますので、参考にしていただき、ご自身の体力、生活リズム、価値観に合った働き方を選んでいただければと思います。
定年後の仕事は現役時代の延長線上だけでなく、第二・第三のキャリアの可能性を視野に入れて考えてほしいと思います。
(※この記事は『定年後の仕事図鑑』を元にした書き下ろしです)
リクルートワークス研究所研究員・アナリスト
1985年生まれ。一橋大学国際・公共政策大学院公共経済専攻修了。厚生労働省にて社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府で官庁エコノミストとして「経済財政白書」の執筆などを担当。その後三菱総合研究所エコノミストを経て、現職。研究領域はマクロ経済分析、労働経済、財政・社会保障。近年は高齢期の就労、賃金の動向などの研究テーマに取り組んでいる。著書に『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』のほか、『ほんとうの定年後「小さな仕事」が日本社会を救う』『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』(共に、講談社現代新書)などがある。