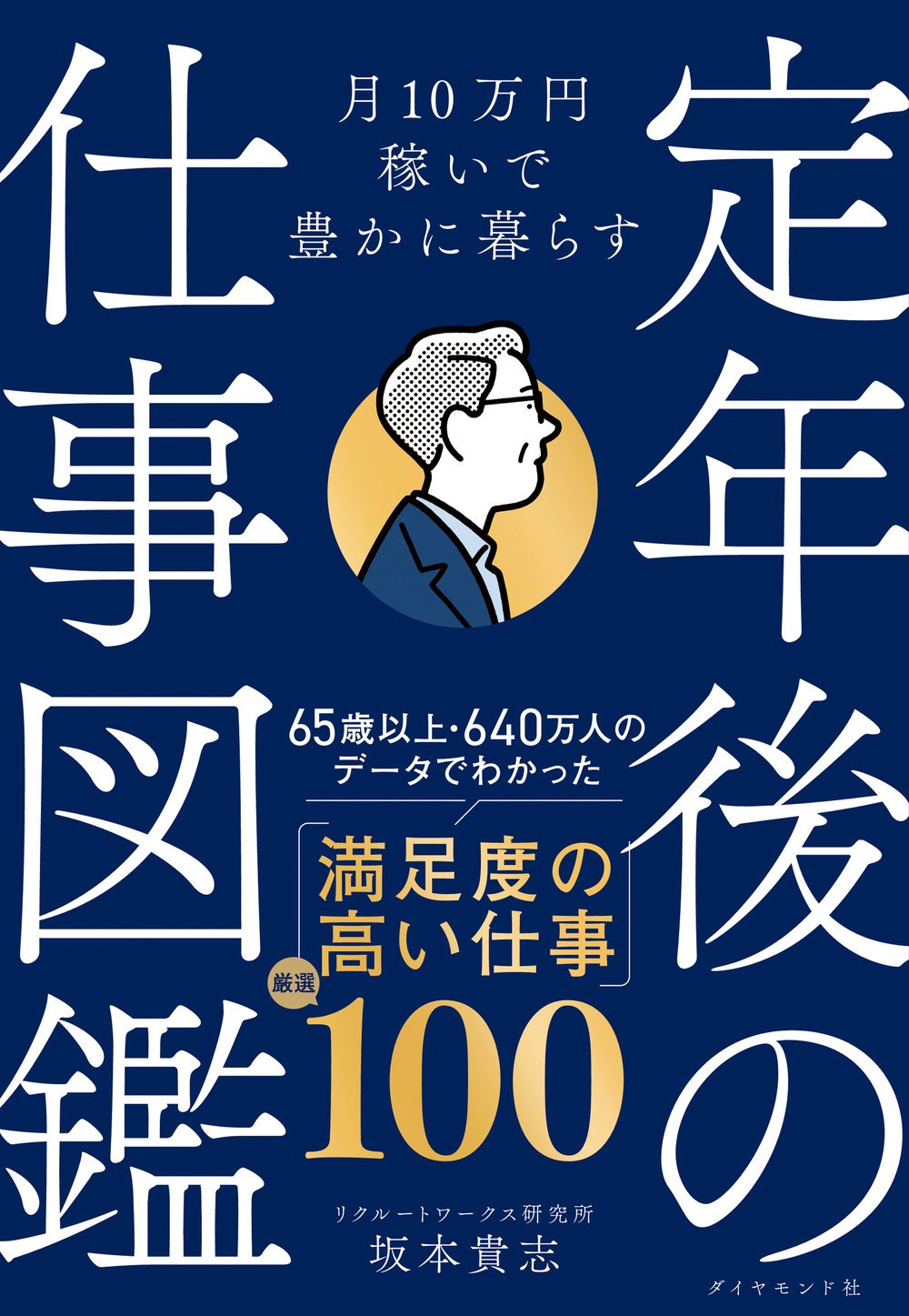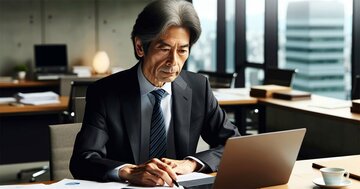働き方が多様化するなか、「定年=引退」というモデルは過去のものとなりつつある。「現役時代のようなフルタイム勤務ではなく、ストレスなく、少ない時間で続けられる仕事があれば……」と考える人も少なくないだろう。では、65歳以降に無理なく働ける仕事にはどんな選択肢があるのか。本記事では『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏にインタビューを実施。仕事の実態を、就業データと当事者の声をもとに紐解いてもらった。(構成・聞き手/ダイヤモンド社書籍編集局、杉本透子)
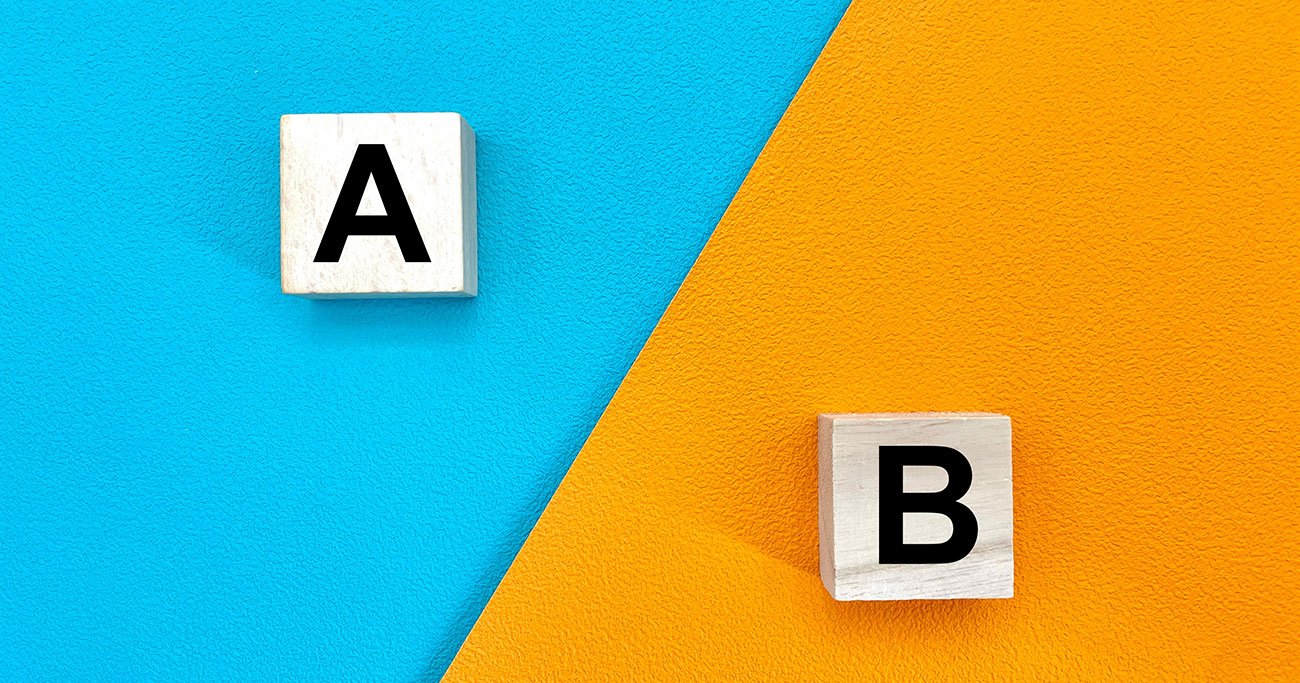 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
データで見ると「持ち家」に軍配が上がる
――定年を意識し始める世代にとって「住まい」は大きな関心事です。持ち家のほうが安心というイメージがある一方で、住宅価格の高騰もあり、迷われている方も少なくありません。「持ち家と賃貸、どちらが望ましいのか」この点について、坂本さんはどのようにお考えでしょうか。
坂本貴志氏(以下、坂本):ご質問のとおり、「持ち家か賃貸か」というテーマは多くの方が悩まれる点です。そのうえで、住宅に関して「どちらが絶対的な正解か」という問いに対して、一概に甲乙をつけるのは難しいですね。なぜなら、どちらにもメリット・デメリットがあり、個々人のライフスタイルや経済状況などによって最適な選択は大きく異なるからです。
――たしかに、住まいの地域や資産額、健康面などによっても、ベストな選択は人それぞれ違ってきそうです。その上で、多くの人にとって満足度が高くなるのはどちらの選択だと言えるでしょうか……?
坂本:定年後の家計を考える上で欠かせないのが経済的な側面、特に「フロー(定期的に入ってくる収入)」をいかに確保するかという点です。
多くの人が老後資金と聞くと「貯金=ストック」を思い浮かべます。しかし実際には、多くの高齢世帯は貯金を大きく取り崩さず、年金などのフローで日常生活を回しています。
住居費は毎月の支出の中でも大きな割合を占めますので、このフローを安定させる上で非常に重要なポイントになります。そうした視点で見ると、多くのデータからは、持ち家に軍配が上がると考えられます。
――どのような理由からでしょうか?
坂本:多くの人が、しっかり働けるうちに住宅ローンを完済する選択をしていることがデータからも見て取れます。総務省の家計調査によると、住宅・土地のための負債の平均額は40代で約1,300万円だったものが、60代には約163万円まで減少しているんです。
つまり、高齢期の家計のフローを安定させるためには、60代半ばまでに住宅ローンを完済し、住居費の支出を限りなく少ない状態にしておくことが望ましいと考えられます。
持ち家であれば、人生における住居に関する支出が先に概ね確定できるため、将来の不確実性を減らすことができるというメリットがあります。
――現役のうちに住宅ローンを払い終えるのが理想的なのですね。ただ、賃貸派にとってはライフスタイルが定まる前に住む場所を固定してしまうことへの不安もありそうです。
坂本:そうですね。賃貸には、仕事や家庭の都合に合わせて気軽に転居できるという大きなメリットがあります。
例えばお子さんが小さいうちは生活に即した立地の借家で暮らし、子育てを終えた後に老夫婦で暮らす小さな住居を取得するというのも、現実的な選択肢の一つです。
また、すでに持ち家をお持ちの方でも、世帯人数が減る定年後は、広い家から小さな家に住み替えることを積極的に考えるのも良いでしょう。
――賃貸は身軽ですが、高齢期の家計にとってデメリットが大きいのですね。
坂本:賃貸の場合は、寿命が続く限り毎月賃料が発生し続けます。これは、「いつまで生きるかわからない」という不確実性の高い状況において、「いざという時のために貯蓄を常に多く残しておく必要性」を生じさせます。
一方、持ち家であれば、住宅に関する支出が先に概ね確定できるため、将来の不確実性を減らすことができるのです。
――なるほど、不確実性の軽減という観点ですね。それは定年後の生活設計において非常に重要になりそうです。私たちが定年後の住まいを考える際に、最も重視すべきポイントは何でしょうか?
坂本:最も重視すべきは、やはり「定年後のフロー収入とのバランス」です。
公的年金は65歳以降の定期収入の中心となりますが、現役時代の働き方や収入、配偶者の働き方によって支給額は大きく異なります。
平均的な二人世帯の年金支給額が月20万円台半ばだとしても、平均支出は月30万円台前半となり、毎月3~7万円の赤字になるというデータもあります。この赤字をどう補うか、あるいは赤字を発生させないようにするか、という点で住居費が大きく影響します。
もし住宅ローンの支払いが残っていたり、毎月高額な家賃を支払い続けたりするならば、その分、貯金を切り崩したり別途の労働収入を確保する必要性が高まります。
私の著書『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』では、定年後に「月10万円を無理なく稼ぐ」ことを一つのベンチマークとしていますが、もし住居費の負担が軽ければ、この目標も達成しやすくなります。
――何歳まで生きるか、いつまで健康で自宅で暮らし続けるかなど、わからない要素が多いからこそ、よりリスクの低い選択をするのが安心だということですね。
坂本:おっしゃる通りです。70歳以上の実に92.4%が持ち家を取得しているというデータもあります。これは、多くの人が高齢期を迎えるにあたり、住居費という大きな支出を確定させ、老後の経済的基盤を安定させることを選んでいる現実を示しているとも言えるでしょう。
――非常に腑に落ちました。「持ち家か賃貸か」という二元論ではなく、自分の年金収入や、定年後も働き続けるかどうか、といった「フロー」の計画とセットで考えるべきだということですね。
坂本:その通りです。住居の問題は、高齢期の家計に非常に大きな影響を与えます。ご自身の年金受給見込み額を必ず確認し、健康状態や労働意欲も考慮しながら、住居や高齢期の働き方も考えるという視点が重要になります。
どちらの選択肢にもメリットとデメリットがあり、ご自身の人生設計に合った最適な解を見つけることが、定年後を豊かに生きるための鍵となるでしょう。
(※この記事は『定年後の仕事図鑑』を元にした書き下ろしです)
リクルートワークス研究所研究員・アナリスト
1985年生まれ。一橋大学国際・公共政策大学院公共経済専攻修了。厚生労働省にて社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府で官庁エコノミストとして「経済財政白書」の執筆などを担当。その後三菱総合研究所エコノミストを経て、現職。研究領域はマクロ経済分析、労働経済、財政・社会保障。近年は高齢期の就労、賃金の動向などの研究テーマに取り組んでいる。著書に『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』のほか、『ほんとうの定年後「小さな仕事」が日本社会を救う』『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』(共に、講談社現代新書)などがある。