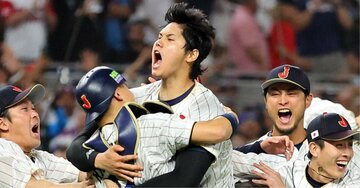はま寿司の看板 Photo:PIXTA
はま寿司の看板 Photo:PIXTA
吸水シート、使用済みゴミ、そして今回の洗剤…。大手回転寿司チェーン「はま寿司」で、なぜこれほど異物混入が相次ぐのか。実は、同社が発表する謝罪文の中に、危機管理の専門家が警鐘を鳴らす《絶対NGワード》があったのだ。良かれと思って使われるその言葉こそが、現場の危機意識を奪い、再発防止を遠ざけている。異物混入が止まらない構造的な問題を、謝罪文から徹底的に解き明かす。(ノンフィクションライター 窪田順生)
異物混入事故の中でも
はま寿司が特に問題視される
「すき家」の味噌汁にネズミが混入した騒動で大きなダメージを負ったゼンショーホールディングスに、再び不穏な空気が漂っている。
「すき家」とともにグループの成長を牽引(けんいん)している「はま寿司」で異物混入が立て続けに発覚しているのだ。注目すべきは「異物」の内容がどんどんシビアなものにエスカレーションして、ついには3歳女児が一時入院する事態まで起きてしまった点だ。
小さなミスが積み重なっている組織では、重大事故が発生するということがよくある。これは「ハインリッヒの法則」という危機管理に携わっている人々の間の「常識」である。
筆者も報道対策アドバイザーとして、さまざまな不祥事企業に関わる中で、この法則に当てはまる組織を目の当たりにしてきた。
もちろん、だからといってすぐに「はま寿司」に何が起きるなどと言いたいわけではない。ただ、危機管理の専門家として、これらの異物混入の対応に違和感があるのも事実だ。それを指摘させていただくので、関係者は再発防止策の参考にしていただきたい。
まず、「はま寿司」で最近話題になった異物混入を振り返ってみよう。