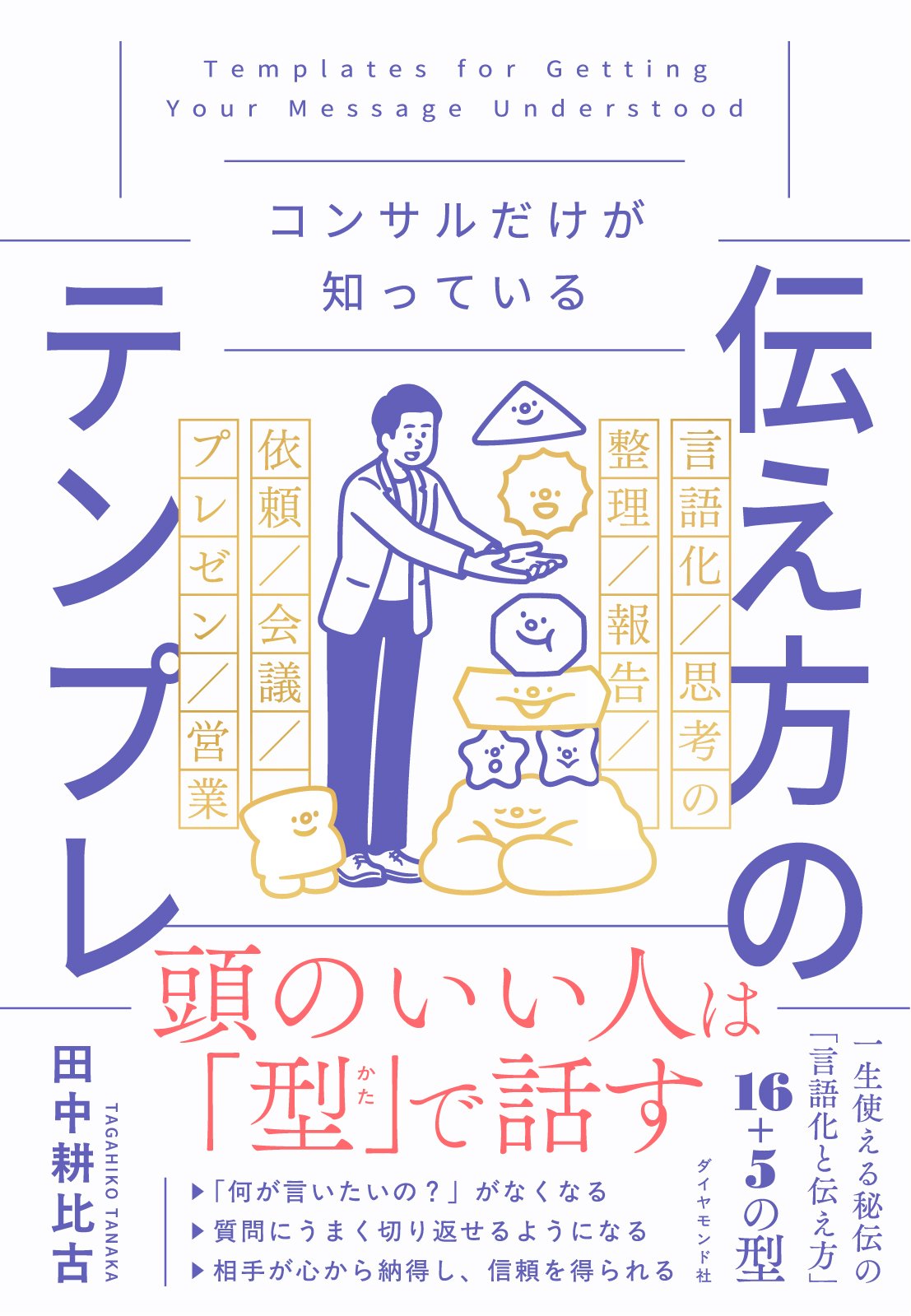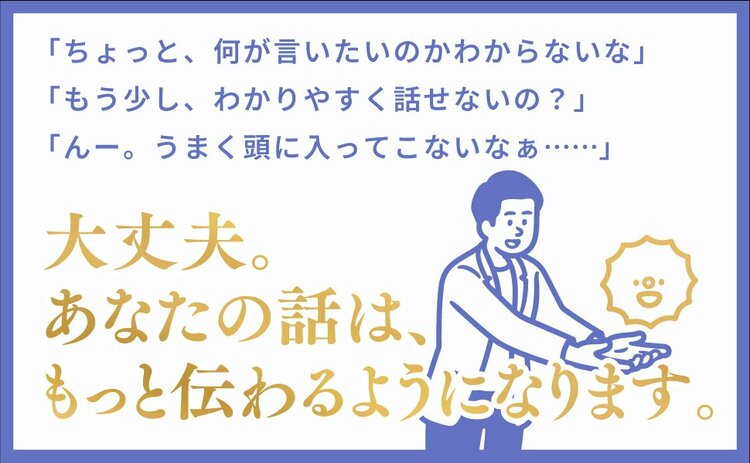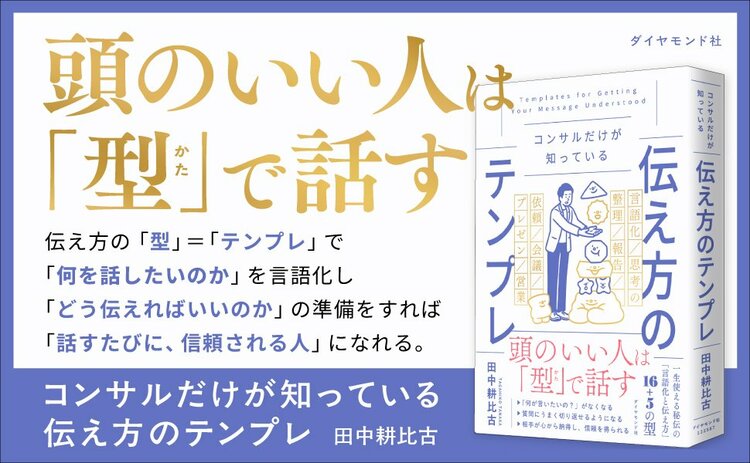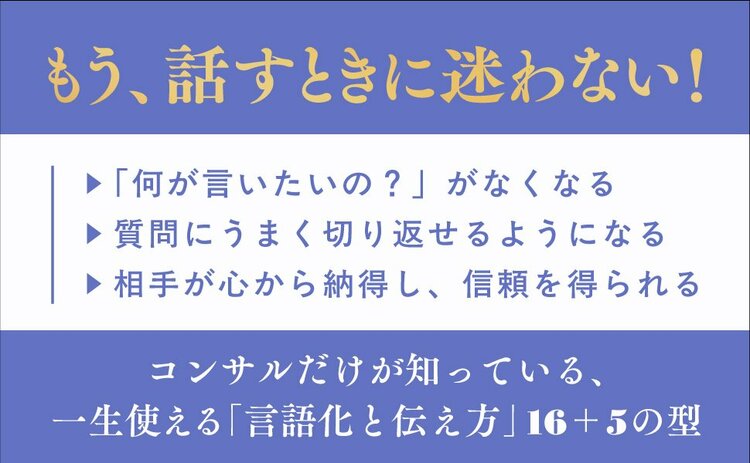「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「二の矢テンプレ」で言葉を選び直す
がんばって説明したのに「それって、どういうことだろう」「ちょっとピンとこないな」などと言われることもあります。
これは、相手の理解が追いついていない状態です。
自分の説明で用いた言葉の抽象度や、そもそもの言葉選びが適切でなかったことが原因だと考えられます。そんなとき有効なのが「二の矢テンプレ」です。
最初の矢、つまり予定していた伝え方ではうまく相手に刺さらなかったときに、別のルートで伝え直すために準備します。
「二の矢テンプレ」は、次の三つの視点で検討します。
視点①:感覚をつかませる─喩え話・ストーリー・比喩を用意する
視点②:抽象度を下げる─日常語・具体例・感情を添える
視点③:論点を揃える─評価軸・前提条件の違いを明確化する
視点①:言語を感覚に置き換える
説明が過剰に具体的だったり、内容が細か過ぎたりした場合には、この「言語を感覚に置き換える」アプローチが有効です。特に、聞き手がそのテーマについて詳しくないときには、効果が大きいでしょう。
例:
◎レゴブロックみたいに、あとから組み替えられます。
◎家庭用ゲーム機みたいに、まずは本体を用意しておいて、あとから遊びたいゲームを買って、適宜入れ替えていくイメージですね。
◎アメフトみたいに、ポジションごとの役割を明確に変えて、それぞれに特化したサービスを導入し、組み合わせていくわけです。
ここでのポイントは「相手が知っていそうなもの」で喩えることです。
例に挙げたアメフト(アメリカンフットボール)は、アメリカでは大人気スポーツでほぼ全員が知っています。
しかし、日本だと、詳しく知らない人もいるでしょうから、「一般的な喩え」としては不適切かもしれません。
そのため、野球やサッカーなどのスポーツで喩えるほうが好ましいと言えます。
視点②:抽象度を下げた具体的な表現を探す
「感覚に置き換えて喩える」とは反対に、説明が抽象的過ぎた場合に備えるのが、このアプローチです。
例:
◎将来的に他部署でも使えるように、あらかじめ仕組みをつくってしまう、ということです。
◎直感的にわかるように表示方法を変更できます。大きな文字で表示する、色を変える、動かすなどの設定が可能です。
◎サービスレベルによって価格を変えています。例えば、指定時間にお届けする場合は、追加料金が5千円かかりますが、午前・午後指定であれば3千円、日付指定のみなら千円、指定なしなら通常料金のみです。
視点③:前提を調整して、論点を揃える
相手の興味関心が、こちらの想定したものとズレているときには、抽象度をコントロールしても効果がありません。そのときは、話の前提を揃えにいきましょう。
例:
◎「目の前の課題に対応するだけで良い」というお話であれば、確かに、別案のほうがお安く実現できるかもしれません。ただ、将来の拡張性を考えるなら、提示させていただいた案のほうが良いのではないかと思います。
◎幅広いユーザーが参加してくれるという観点であれば、従来のやり方も決して間違っていないと思います。しかし、継続的に利用したいと考えてくれるコアユーザーの満足度を考えると、今回の提案について検討する余地が出てくるのではないでしょうか。
二の矢を持っておくと、最初の矢がうまく刺さらなかったときに、即座に次の一手を打つことができます。
一発では通らなかった場合に備えて、いろいろな矢を何本も用意しておくことで、対話力が格段に高まります。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)