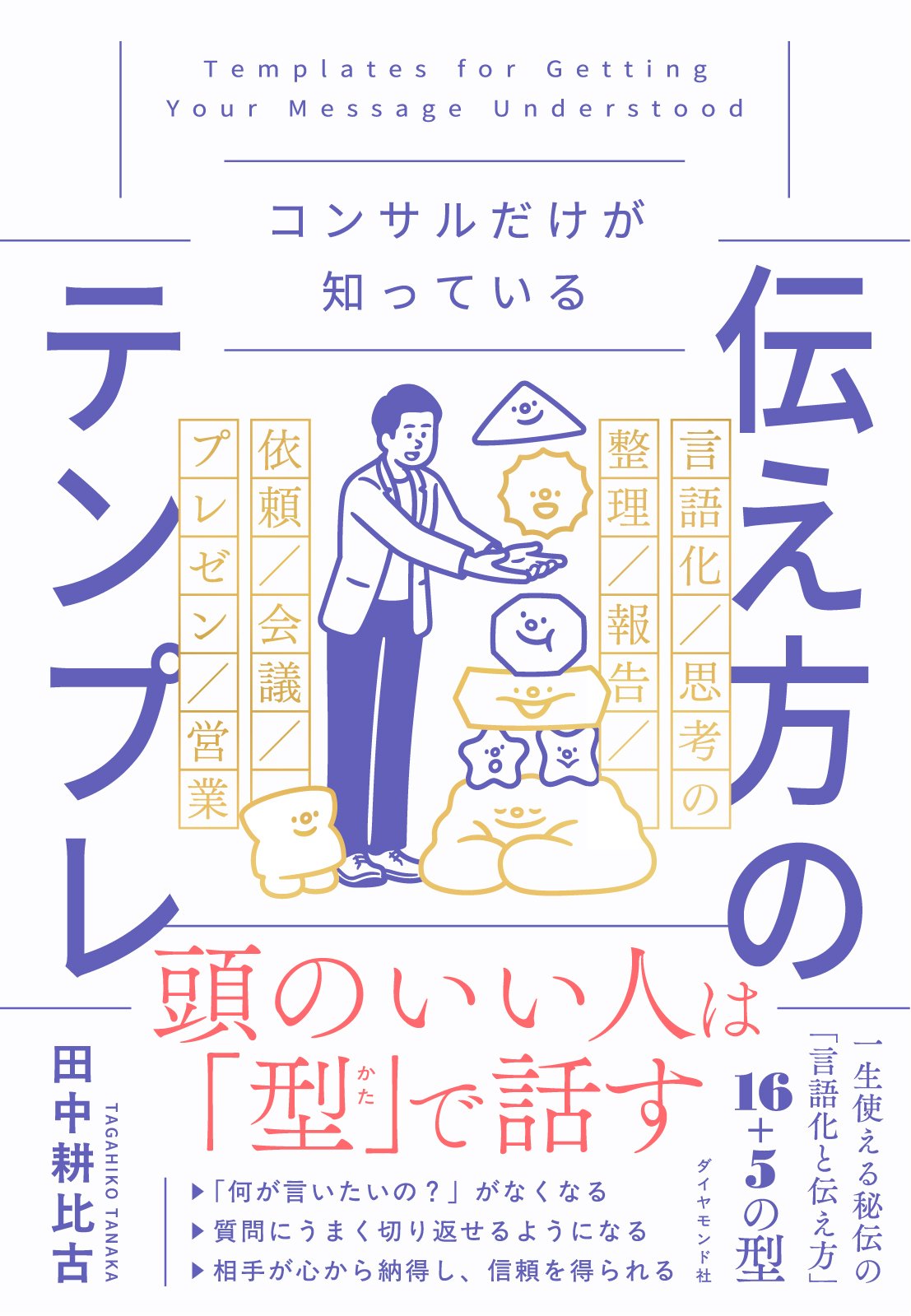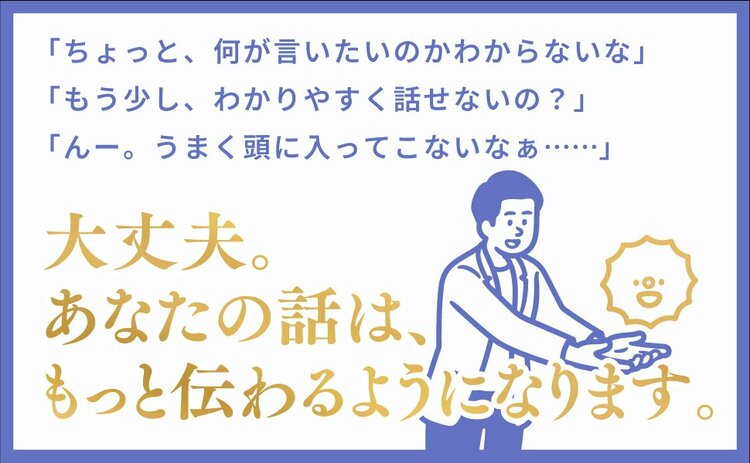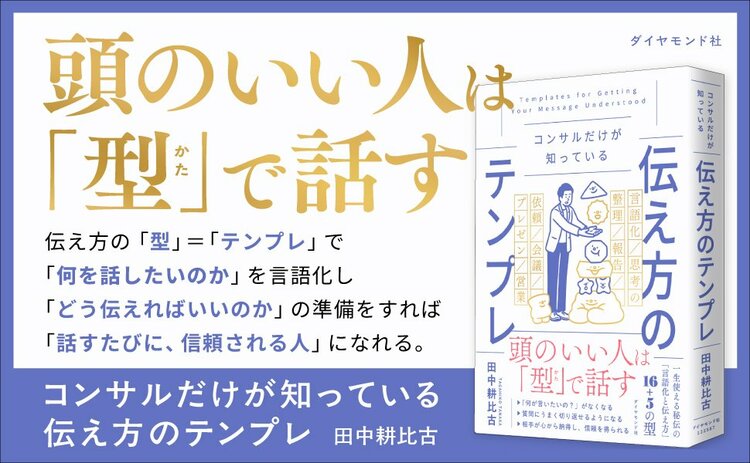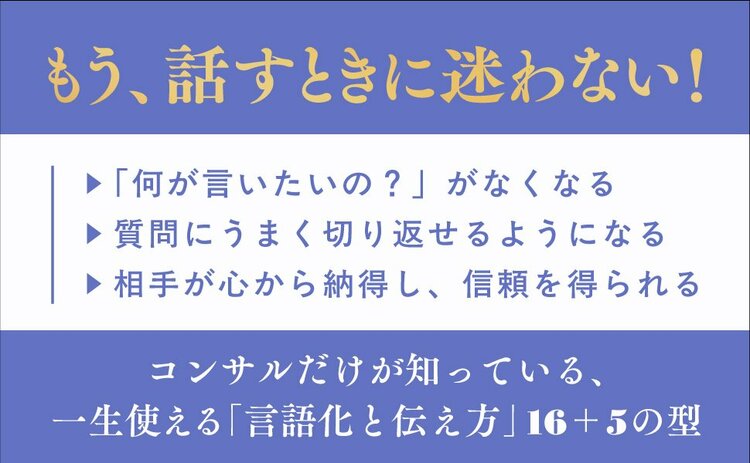「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
型を持っている人は、動揺しない
雑談中や会議で想定外の質問をされた、話の方向が急にそれた、あるいは、聞き手の表情が読めなくなった……。
話す場面では、こうした“揺らぎ”に必ず出会います。
そうした場合に、その揺らぎに影響されて、動揺してしまう人はたくさんいると思います。
しかし、中には落ち着いて受け止めて冷静に対応し、必要に応じて軌道修正ができる人もいます。
何が、このような違いを生むのでしょうか。
私は、そこに「型」が大きく影響していると思っています。
「型」を持っていると、想定外の揺らぎがあっても、動揺せずにすむ。
そして、安心して話を進められるようになります。
型を持つといっても、決して、話し方、しゃべり方を固定するわけではありません。
また、話す内容を丸暗記することでもありません。
型を持つとは、自分の中に「話の構造」を持つことなのです。
例えば、「話すときには、常に“結論→根拠→具体例”の順で組み立てる」「聞き手の目的を冒頭で確認する」というような話す順番を持つ。
あるいは、「必ず三つの論点で整理する」「ヒアリングした内容は、物事の時系列で整理し直す」などの設計図を持っておく。
すると、相手が想定と違うことを話し始めたり、話が脱線してしまったりした場合にも、元の話の本筋に戻るきっかけをつかめます。
話が脱線した際に、自分が最初に決めていた話の本筋の中の、どの部分まで話が進んでいたかを考えれば、そこに戻るための作戦を立てやすくなるからです。
相手の想定外の話も、自分の話の構造にどのように当てはめられるかを考えると、議論を整理する糸口がつかめます。
「型」があることで、発散した議論を自分が管理する世界の中に収めることができるわけです。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)