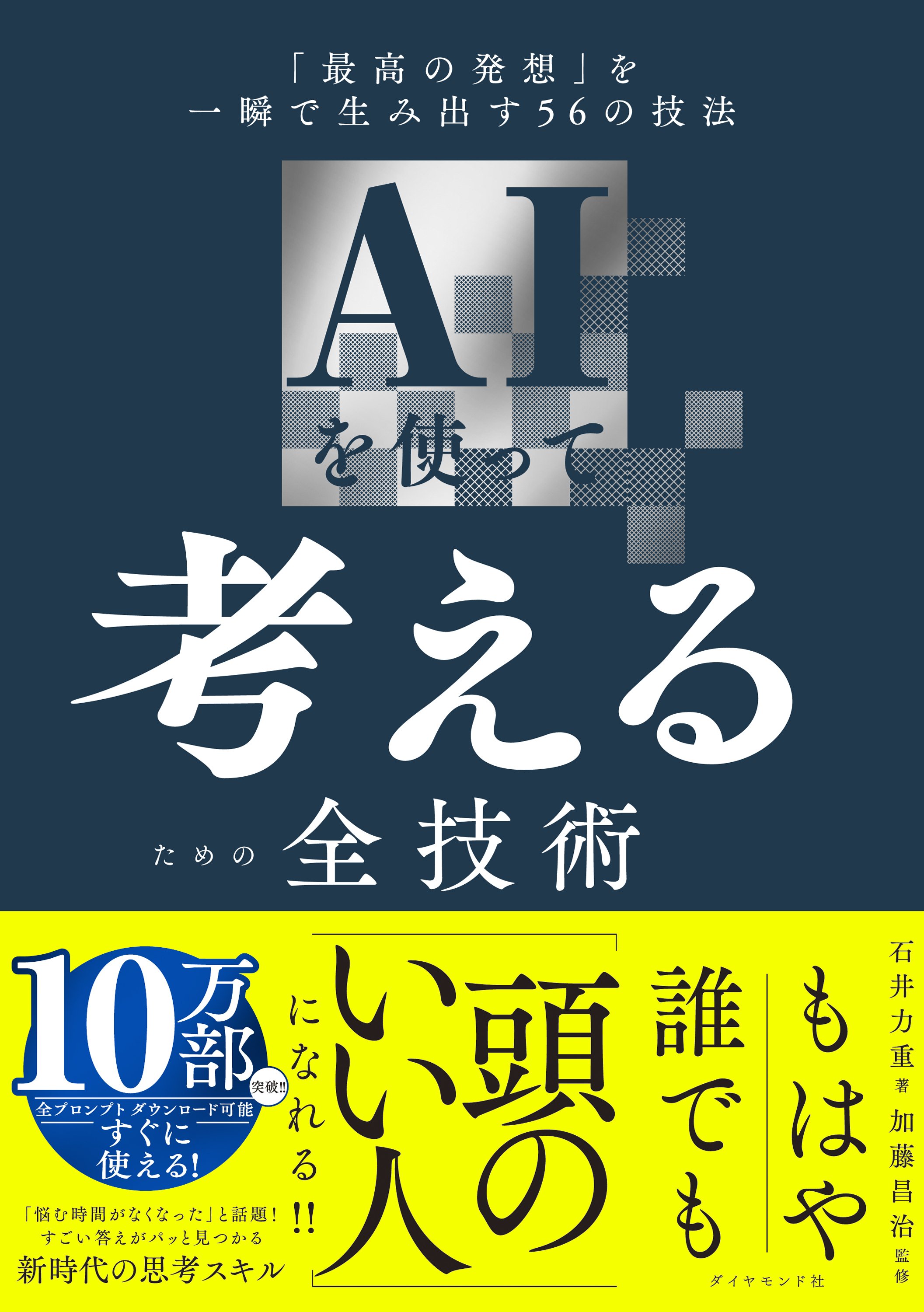AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
脳内散歩でアイデアを生み出す「エクスカーション法」
プロフェッショナルなアイデアパーソンたちがよく使う、「エクスカーション法」という発想法があります。
英語で綴ると「excursion」。遠足・小旅行という意味に加えて、「脱線」なんて訳語もある単語です。
実際、散歩や遠足の最中にアイデアが生まれることが多々あります。「エクスカーション法」は、実際に外出せずして発想を生み出す発想法。あなたの脳内でちょっとした“お出かけ”をして、そこで出合った「何か」をアイデアのヒントにする方法です。
慣れてしまえば、たいへん使い勝手の良い発想法。だからプロフェッショナルも重用しています。
「お出かけ先」で思いついたものを書き出す
「お出かけ先」はどこでもかまいませんが、おすすめは以下の3つ。
①動物・生物 ②場所 ③職業
たとえば「動物・生物」に“お出かけ”して、エクスカーション法を試してみます。
自分が抱えているお題はいったん脇において、猫、イルカ、ワニ、蜘蛛、カブトムシ、薔薇、微生物……など、なんでもいいので動物・生物を10個書き出します。
次に、リストアップした動物・生物から思い浮かぶ機能や特徴などを単語として書き出します。この時点ではお題との関連付けは不要です。
猫→「にゃーにゃー鳴く」「集会をする」
薔薇→「トゲ」「香水の素」「誕生日プレゼント」
正解はありません。思いついたままで。むしろ、ちょっと外れたぐらいの言葉がほしいところです。できれば10個ほど書き出してみてください。10の動物・生物×10個の言葉で、合計100個が目標です。
意外な組み合わせから、「意外なアイデア」が生まれる
この100個の言葉を、お題と掛け合わせます。仮にあなたが「ボールペンの新商品」を考えたいのであれば、「ボールペン×集会をする」「ボールペン×トゲ」など、お題といくつかの言葉を組み合わせて考えてみます。
すると「何本か集めることで別の機能を持つペン」「指のツボを刺激してくれる突起があるペン」など、お題と言葉との組み合わせからアイデアが出てくるから不思議です。
出かける先が「場所」「職業」であっても、方法は同じです。たとえば「場所」なら、「南の島」「仙台駅」など、まずは空想の旅先、またその旅の途中で出合うシーンを10個、考えてみます。「そこでは何が見えた?」と自分に問い、10個のキーワードとして言葉にしてください。
「職業」版も同じ。まずは10個の職業を思い浮かべ、その職業に必要な道具や、その職業の人がすることなど、思いつく言葉を合計100個書き出します。なりきって考えてみるのがポイントです。
こうして設定した動物、場所、職業を介して、つまりお題とは無関係な「猫」や「薔薇」をいったん経由して、脳内からアイデアにつながりそうなヒントを引っ張り出してくるのがエクスカーション法です。
エクスカーション法をAIで実践する技法「多様な特徴」
慣れてくると便利な「エクスカーション法」ですが、最初に仲介物を10個、最終的に100個の機能やシーンを1つずつ書き出していくのは……考えるまでもなく正直かなり面倒です。加えて、出てきた100のキーワードのどれをお題と組み合わせればいいかも悩ましいところ。
そこで、AIの力を借りてエクスカーション法を行うのが、技法その1「多様な特徴」です。
こちらが、そのプロンプトです。
まず、特徴が異なる動物や生物を10個あげてください。次にその動物から連想できる特徴や機能を各10個あげてください。最後に、連想した単語と組み合わせて有益な機能を持つ〈アイデアを得たい対象を記入〉を7つ考えてください。
AIを使えば、自分では思いつけなかった動物や、知らなかった特徴もざくざくと掘り出してくれます。発想法の構造はそのままに、手間を減らしてアイデアを得てしまいましょう。
なお、商品・サービス企画にもっとも向いているのは「動物・生物版」。ということでAIへのプロンプトには「動物」を採用しています。慣れてきたら、あるいは気分しだいで「場所」や「職業」にプロンプトを入れ替えて使ってみるのもOKです。
技法その1「多様な特徴」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める方法を多数紹介しています)