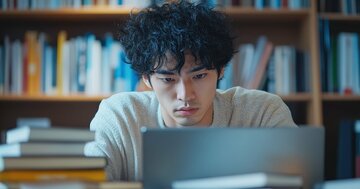AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AI回答の質が目に見えて変わった!」「値段の100倍の価値はある!」との声も多く話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
視覚情報をアイデアに結びつける発想法「インプット法」
「インプット法」という発想法があります。
発想につながる刺激を取りに行く際、お題に関係するものではなく、無関係な情報を浴びるように見に行く方法です。
でも人間は、ついついお題に関係があること(距離の近い情報)に目が行きがち。そこで、距離の遠いヒントを探すために行くのが、お題とは関係ない物事があふれている「屋外」です。
これが、アイデアパーソンの多くが旅行や街歩きを推奨している理由です。道中で出合った、お題と直接は関係ないものが、アイデアにつながりやすいからです。
AIでインプット法を実践する技法「写真の中のヒント」
とはいえ、忙しいビジネスパーソンには頻繁に旅行や散歩に出ていく余裕がありませんから、AIの協力を得ましょう。
AI(を使うためのパソコンなど)を屋外に持ち出す、なんてことではありません。過去に撮影した写真や、検索して見つけた画像を取り込んで、アイデアのヒントを見つけてもらうんです。
それが、技法その11「写真の中のヒント」です。
こちらが、そのプロンプトです。
この画像から思い浮かぶことを10個あげてください。次にそれを材料にして〈アイデアを得たい対象を記入〉として妥当なものを3つ、意外なものを3つ考案してください。
※画像を添付した上で使ってください
「エクスカーション法」や「辞書法」と効能は似ていますが、辞書から持ってくる「比較的整っている言葉群」に比べて、もっと生活に近い要素、たとえばゴミなどの「美しくないもの」もAIは探してきますから、発想の方向はだいぶ異なります。目的に応じて使い分けてください。
自分の中にある「言葉」や「概念」に縛られない発想が生まれる
プロンプトの中で「妥当なものを3つ、意外なものを3つ」と指示しているのには理由があります。本来は「意外なもの」だけを欲しているのですが、それだけを回答させるよりも、「妥当なもの」もセットで探してもらう方が、もっと「意外」な概念になるんです。そうしたAIの特性を考慮しています。
黙々と1人で行うアイデア出しはもちろん、複数人で一枚の写真を見ながらワイワイとアイデアを出し合うときにも有効です。
その上で、ぜひチャレンジしてみてほしいのは専門性の高いお題。多くの発想法は「言葉」「概念」を出発点にします。それでも充分に距離のあるヒントは見つかるのですが、画像を起点にする「写真の中のヒント」は、視覚的な情報を含めて、異質な情報を抽出する強制力があると思います。
技法その11「写真の中のヒント」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って“思考の質”を高める方法を多数紹介しています)