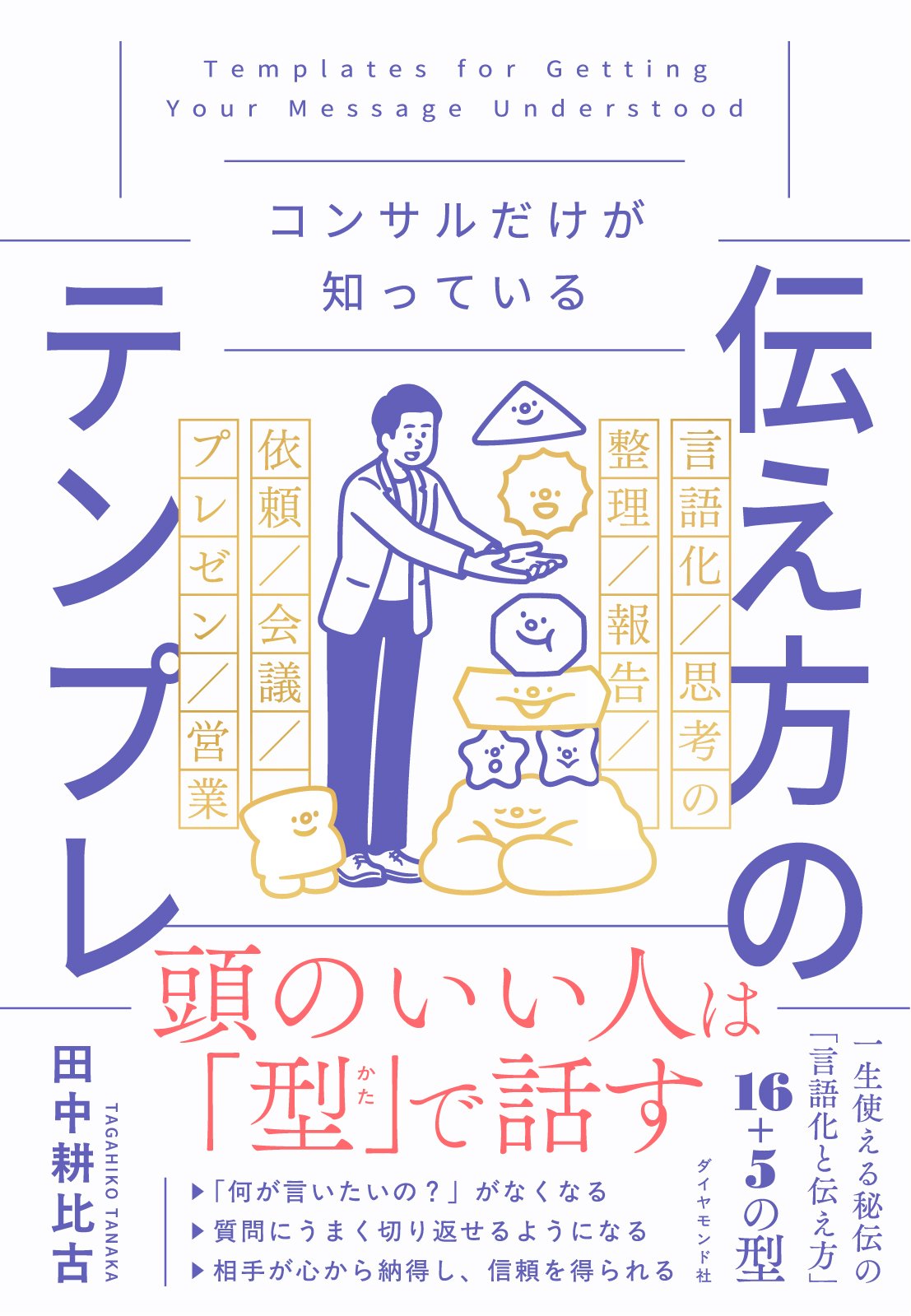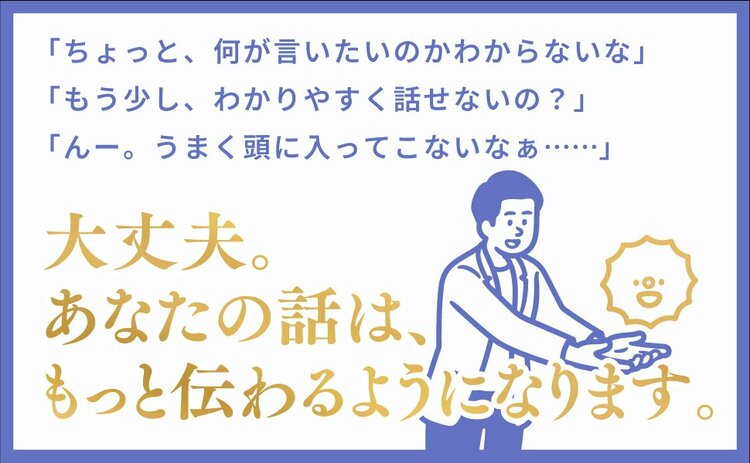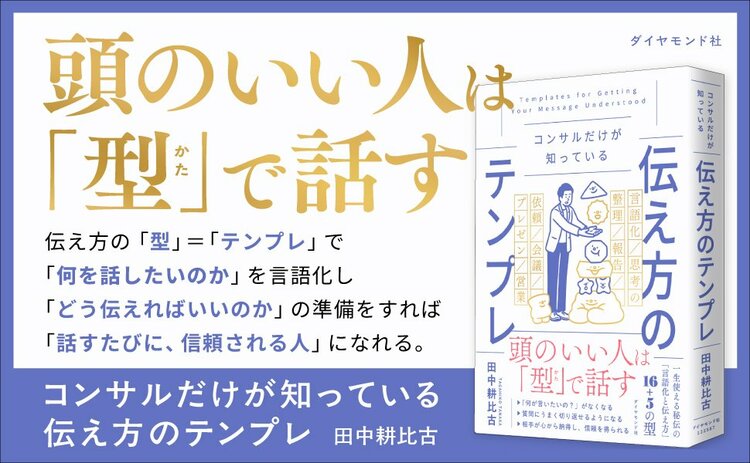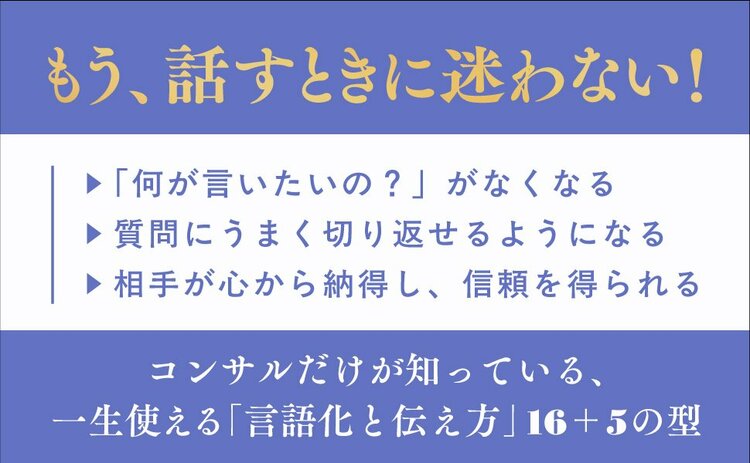「一生懸命に考えたのに、思ったように伝わらない」「焦りと不安から自分でも何を話しているかわからなくなってしまう」…。言っていることは同じなのに、伝え方ひとつで「なんでこんなに差がつくんだろう」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
コンサルタントとして活躍し、ベストセラー著者でもある田中耕比古氏の著書『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』から、優秀なコンサルが実践する「誰にでもできるコミュニケーション術」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「変化」に注目してストーリーを描く
「相手を納得させたい」、「自分の話に説得力を持たせたい」ときには、「これを実行したら、何がどう変わるのか」という「変化」の提示が、非常に強い武器となります。
そのとき使えるのが「Before→Afterテンプレ」です。“現状=変化前”と“理想形=変化後”を対比させることで、変化の意味と価値を明らかにしていきます。
「Before→Afterテンプレ」のステップは、次のとおりです。
ステップ①:Before(現状)を理解する
ステップ②:After(将来の理想形)を描写する
ステップ③:両者の差分を明らかにする
ステップ④:なぜ、それが起こるのかを明らかにする
ステップ①:Beforeの理解
まず、変化前の状態を整理します。
例えば「日々の作業が属人化していて、特定のメンバーに依存しており、休暇などでその人がいないと業務が滞ってしまう」など、目指す変化によって改善したい「問題」のある状態が想定できます。
プライベートであれば、「長期の旅行に行きたいが、他のことにお金を使ってしまいお金が貯まらない」や、「子供が勉強しなくて成績が悪い」なども変化前の状態として考えられます。
ステップ②:Afterの描写
続いて、将来の理想形として、どのような状態に変わるのかを考えます。
先ほどの仕事の例であれば、「業務標準化により、誰でも一定の品質で作業できるようになる」などが将来の理想形でしょう。
プライベートの例であれば「旅行資金が自然と貯まるようになる」、「子供が自発的に勉強するようになる」などでしょう。
ステップ③:差分の見極め
次は、BeforeとAfterのあいだにある変化を明確にします。
仕事の例ならば、「属人的作業」が「標準的な業務」になり、「人に依存した運用」が「仕組みでまわる運用」に変わっています。
旅行の場合は「浪費」が「目的のための貯蓄」に変化します。勉強の場合は「強制」が「自発性」になり、「勉強しない」が「勉強する」に変わります。
これが変化の価値です。BeforeをAfterに変えると「どんな良いことがあるのか?」を問うと差分が明らかになります。
ステップ④:変化が起きる理由を示す
最後に、「どうすれば、そういう変化が起こり理想的な状態にできるのか」「どういう理由で価値を生むことができるのか」を言語化します。
実現できない理想形を思い描いても仕方ありません。
「Before→After」の話は「このようにすれば、こういう結果が得られる」という実現性を伴った構造になっているからこそ、意味のあるストーリーとして成立します。
先ほどの仕事の例であれば、「標準的な業務」と「仕組みでまわる運用」が、なぜ実現できるのか、その理由を考える必要があります。
ここで、相手に提案する「解決策」が出てきます。
例えば「業務標準化のためのツールを導入し、現在の業務内容を定型的なフローに落とし込んで自動化する」とか、「マニュアルを整備し、いつでもアクセスできるように電子化して、タブレットやスマホなどから簡単に検索できるようにする」などの打ち手が考えられます。
つまり「この状態(Before)を、こう変える(After)ために、この解決策を採用しましょう」というのが、「Before→Afterテンプレ」による言語化の基本形です。
旅行の例であれば、旅行代理店や航空会社などが提供している「旅行積立」、子供の勉強は「ゲーミフィケーション型学習サービス」などの解決策によって、変化を実現する、というストーリーが考えられます。
何が変わるのか、なぜそんな変化が起こるのか、に注目して言語化をしていくアプローチが「Before→Afterテンプレ」です。
なお、Before→Afterを、現状(現在)→理想(未来)として紹介してきましたが、過去→現在として使うこともできます。
つまり、昔はうまくいっていたことが、現在はうまくいっていないような状況です。
例えば、少人数の組織ではコミュニケーションが円滑だったが、人が増えてきた現在はあちこちで情報連携に問題が起きている状態や、発売直後は注目が集まって売れ行きが好調だったが、最近は競合商品も出てきて伸び悩んでいる状態などが当てはまります。
そういう場合にも、このテンプレを使って両者の差分を見極め、その原因や理由について言語化を進めることができるのです(その場合、ステップ③で明確化される「差分」は、価値ではなく、課題や問題点などになります)。
(本記事は『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』の一部を抜粋・編集したものです)