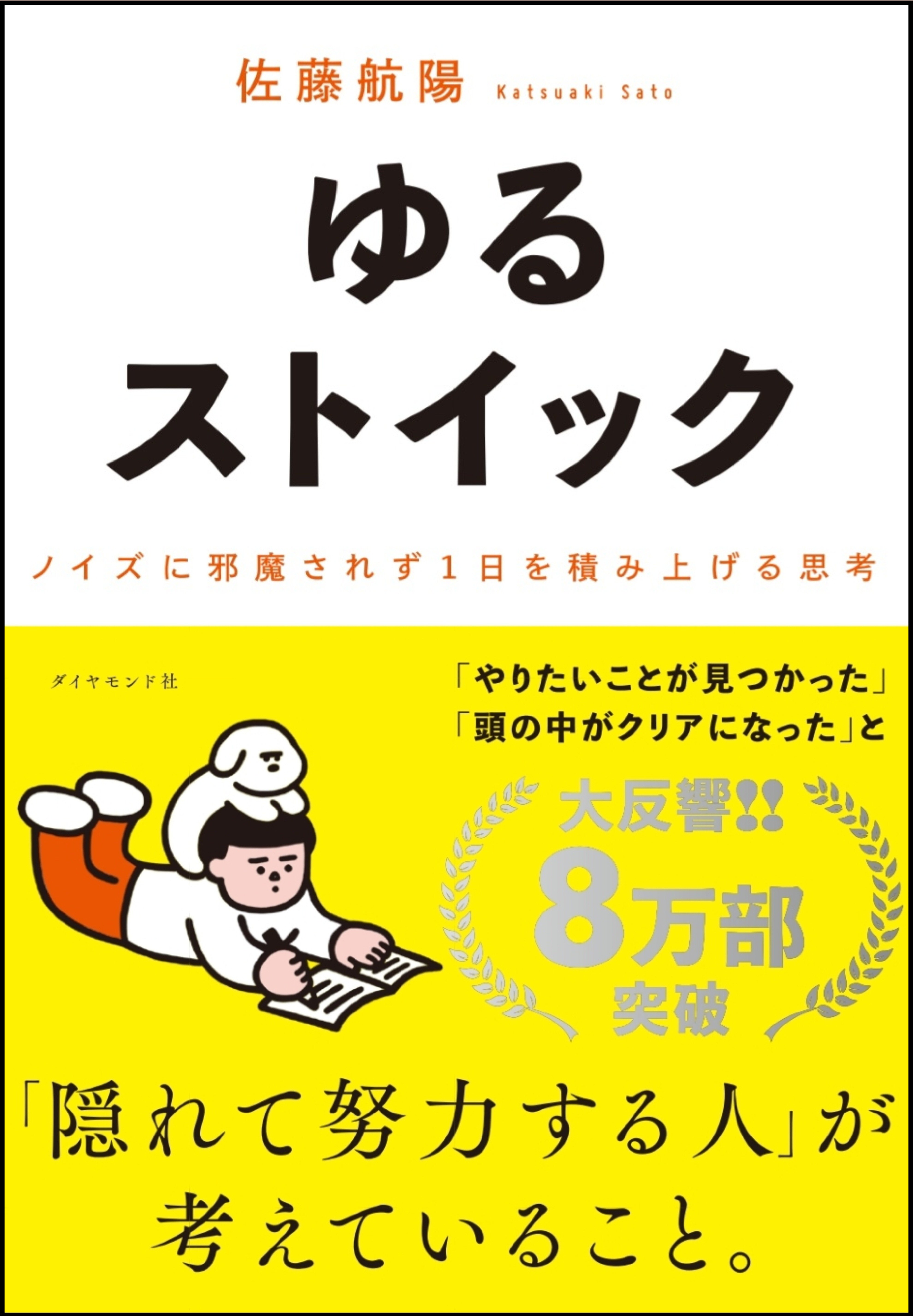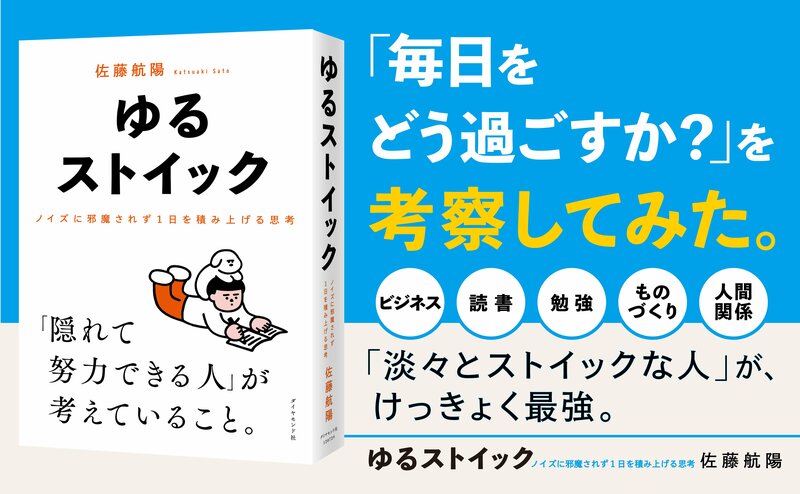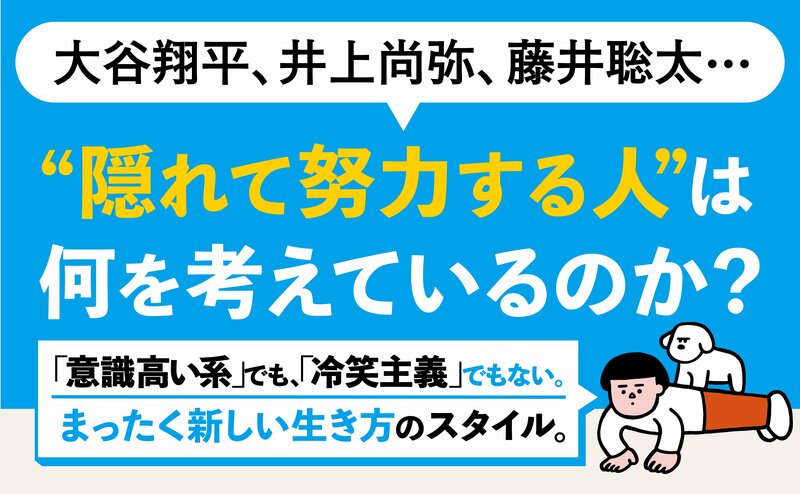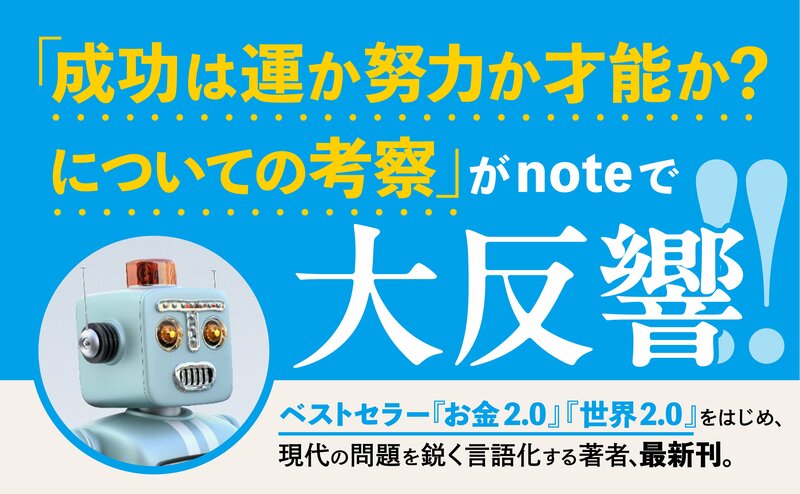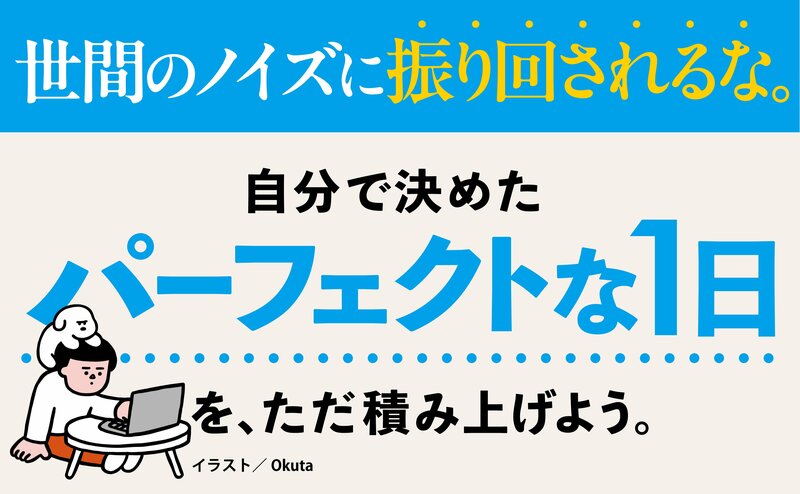頭の悪い人は「顔がいい」「声がいい」という一部を切り取る。じゃあ、どのように伝えればいいのか。
次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。数々の成功者に接し、自らの体験も体系化し、「これからどう生きるか?」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。
コロナ後の生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち(大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…)は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。
『ゆるストイック』では、新しい時代に突入しつつある今、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、「私自身が深掘りし、自分なりにスッキリ整理できたプロセスを、読者のみなさんに共有したいと思っています」と語っている。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
言語には限界がある
私自身、テレビやYouTubeの番組に出演し、多くの人々の前で話す機会があります。
そうした場では、さまざまなコメントやフィードバックをいただきますが、その多くは発言の内容に触れるものではなく、容姿や声といった視覚や聴覚に基づくものがほとんどです。
「見た目がいい・悪い」
「声がいい・悪い」
そんな感想ばかりが届きます。
中には、内容を誤解して受け取ったり、話していないことを勝手に連想して怒りを露わにするような反応もあったりして、非常に発見が多いです。
しかし、こうした反応は、言語そのものが持つ限界を考えれば、まったく不思議なことではありません。
言葉を過剰に信仰している
心理学のメラビアンの法則が示す通り、人間のコミュニケーションにおいて言語が相手に与える影響はわずか7%程度にすぎないからです。
そのため、視覚や聴覚を通じて得られた「印象」が言語の「内容」を上回り、人々の反応や記憶に強く影響を与えるのは自然なことです。
現代の知識社会は、言語による情報伝達を重視する一方で、言葉の影響力を過剰に信仰しすぎています。
しかし、人類の歴史を振り返れば、言語は生物学的に見ても比較的新しいコミュニケーション手段です。
何万年もの間、人間は視覚、聴覚、嗅覚、触覚といった感覚器官を頼りに生活し、コミュニケーションを取ってきました。
言葉が人間社会に浸透したのはその後のことであり、むしろ感覚を通じたコミュニケーションが本来の形だったのです。
「視覚と聴覚」を活かす情報発信をしよう
そのため、情報を発信する際には、言語だけに頼るのではなく、視覚や聴覚といった感覚的な要素を重視する必要があります。
たとえば、明確でわかりやすい話し方や、親しみやすい表情、身振り手振り、適切な身だしなみは、言語以上に人々に影響を与える重要な要素です。
こうした視覚・聴覚的要素を活用し、より多くの人々にメッセージを届ける工夫が求められます。
株式会社スペースデータ 代表取締役社長
1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人(Forbes 30 Under 30 Asia)に選出される。最新刊『ゆるストイック』(ダイヤモンド社)を上梓した。
また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。