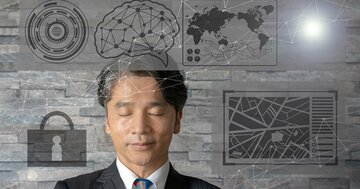写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
近い将来に親が、そしていつかは自分も……と考えるとひとごとではない「認知症」。高齢になると日本人の多くが罹患(りかん)するものの、特有の症状である「物忘れ」や「判断力の低下」はどのように発生し進行していくのか、ご存知だろうか。認知症の中でも多くの割合を占める「アルツハイマー型認知症」を取り上げ、その発症メカニズムを解説する。※本稿は、伊古田俊夫『認知症とはどのような病気か 脳の構造としくみから全体像を理解する』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。
複数の原因が重なり合って
認知症が発症していく
認知症を引き起こす病気には、さまざまな種類があります。そのなかでも、最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の約60%を占めます。次に血管性認知症が約20%を占め、残りの20%には前頭側頭葉変性症、レビー小体型認知症、アルコール性認知症などが含まれます。
病名は単独で表示されることが多いですが、実際には複数の原因が重なり合うことも少なくありません。
アルツハイマー型認知症の約30%は、脳血管障害や事故による脳挫傷、アルコールの多量摂取などが合併した混合型認知症と考えられています。脳の検査で脳梗塞(こうそく)や脳外傷の痕跡が見つかっても、その影響が重くない場合には、アルツハイマー型認知症単独の診断名になることが稀ではありません。
アルコールを長期間にわたって過剰に摂取してきた人の場合は、それが認知症を悪化させていることがありますが、脳の検査では確認できません。
また、うつ病の既往や、脳のはたらきに影響する薬の長期間服用も、認知症の病状に影響を与えます。
高齢期の脳には、長い人生におけるさまざまな影響が積み重なって、認知症が発生してきます。