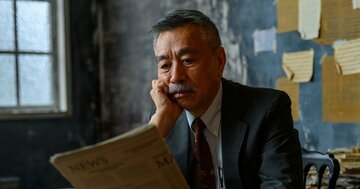写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本では、65歳以上の約4人に1人が、なんらかの認知機能障害を抱えているとされている。中でも近年注目されているのが、「人間関係」と「認知症リスク」の関係性。現役時代に“仕事だけのつながり”しか持たなかった人は、退職後に孤立しやすく、そのことが認知症の発症にも関わってくるという。米国内科専門医・老年医学専門医の山田悠史氏は、著書『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』の中で、最新の研究知見に基づいた予防のヒントを数多く紹介している。今回、山田氏に人間関係だけでなく、「飲酒・喫煙・勉強」などの身近な生活習慣と認知症リスクの相関について、話を聞いた。(取材・文/新里百合子)
退職と同時に“会話ゼロ”になる人がいる
――「友達が職場にしかいない人」は、定年後どのようなリスクがあるのでしょうか。
それ自体がリスクというわけではありませんが、会社の同僚との関係が必ずしも友人関係とまでは言えず、あくまで仕事上の付き合いの場合も多いですよね。職場以外の人間関係が希薄なまま定年を迎えると、それを機に会話や交流が一気にゼロになるケースが少なくありません。
本来であれば、近所付き合いなど自然な人間関係に移行していくのが理想なのですが、特に男性は、定年後に人との接点が急に減る方が多い傾向がある気がしています。
――人との関わりがなくなることと、認知症リスクにはどのような関係があるのでしょうか。
「社会的孤立」は、実は認知症の大きなリスク因子のひとつです。人と会話する機会が失われると、脳が受ける刺激が極端に減少し、結果として認知症の発症リスクが高まると考えられています。
定年を迎えてから「物忘れ」などの理由で受診される方に比較的共通して見られるのは、やはり「孤立」なんです。人との関わりが急になくなってしまって、それがじわじわと影響してくるケースが多いですね。
――ちなみに、生成AIとの会話は人間関係の代替にはならないのでしょうか? 個人的には、ChatGPTなど生成AIと話すことで孤独感が軽減されている実感があるのですが……。
生成AIとのやり取りが、リアルな人間関係の代わりになるのかどうかについては、現時点ではまだわかっていません。これからの研究課題になると思います。ただし、孤独感がなくても、一人暮らしなどで人間関係が全くない、あるいは希薄な「社会的孤立」状態にあること自体が、認知症リスクと密接に関係していることは繰り返し示されています。
――一人暮らしをしていても、孤独を感じることなく過ごしている方もいますよね。そうした場合でも、認知症リスクが高まる可能性があるというのは、少し意外に感じます。