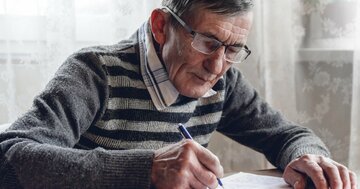写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
中高年になるとチラチラと頭をよぎる「認知症」。親の心配ももちろんだが、自分が認知症にならないかと不安に思ってしている人も多いはずだ。認知症とはどんな症状なのか。予防法はあるのか。専門医が詳しく解説する。(取材・文/日本文章表現協会代表理事 西田延弘)
物忘れのような症状から始まり
近い時期の記憶から徐々に失われる
認知症は脳の病気や障害によって認知機能が低下し、日常生活に支障が起こる状態のことだ。「一口に認知症といっても、その種類にはさまざまある」と説明するのは、高知大学保健管理センター医学部分室准教授の上村直人氏。代表的なものに次の4つがある。
アルツハイマー型認知症
認知症患者の中で最も割合が高く、全体の70%近くを占める。脳の神経細胞にアミロドβというタンパク質がたまり、それが神経細胞を破壊して脳が委縮することによって発症する。
「初期は物忘れのような症状に始まり、食事をしたことを覚えていないなど、近い時期の記憶から徐々に失われていきます。その後日常生活能力の低下がみられ、さらに進行すると徘徊、失禁、性格の変化等が現われるようになるのが特徴です」
血管性認知症
認知症患者全体の20%近くを占める。脳梗塞や脳出血などによって脳の神経細胞への血流が閉ざされ、脳の一部が壊死することで発症する。
「症状は障害を起こした脳の部位によって異なり、歩行障害や手足のしびれ、麻痺、排尿障害、言葉が出にくくなる、意欲の低下、不眠などが起こります」
レビー小体型認知症
認知症患者全体の5%近くを占める。レビー小体という異常タンパク質がたまって発症する。
「幻視、錯視(ないものが見える、別のものに見える)、実態意識性(人がいないのに隣の部屋や2階にいる気がするなど)、レム期睡眠行動障害(睡眠中に寝言や足を動かす)や身体のこわばり、歩行障害、幻視、うつ症状などの症状が現れます。認知機能が変動するのもこの型の認知症の特徴です」
前頭側頭型認知症
認知症患者全体に占める割合は約1%と少ないものの、50~60歳代に発症しやすい認知症で、多くは10年ほどかけてゆっくりと進行していく。脳にピック球という異常構造物がたまって発症するケースと、TDP-43というタンパク質がたまって発症するケースがある。
「性格が変わり、こだわりが強くなったり、本音のまましゃべったりするなどの脱抑制という症状が現れます。また、本能のままに行動してしまって万引きなどに繋がる行動が起こったり、柔軟な思考ができなくなる、身だしなみに無頓着になる、同じパターンの言動を繰り返すなどの症状が現れたりします」
言葉の意味が通じなくなったり、口数が少なくなったりするなどの言葉の問題が目立つ場合もある。
これらの認知症の原因物質であるアミロイドβやレビー小体、ピック球、TDP-43がなぜたまるのかは解明されていない。