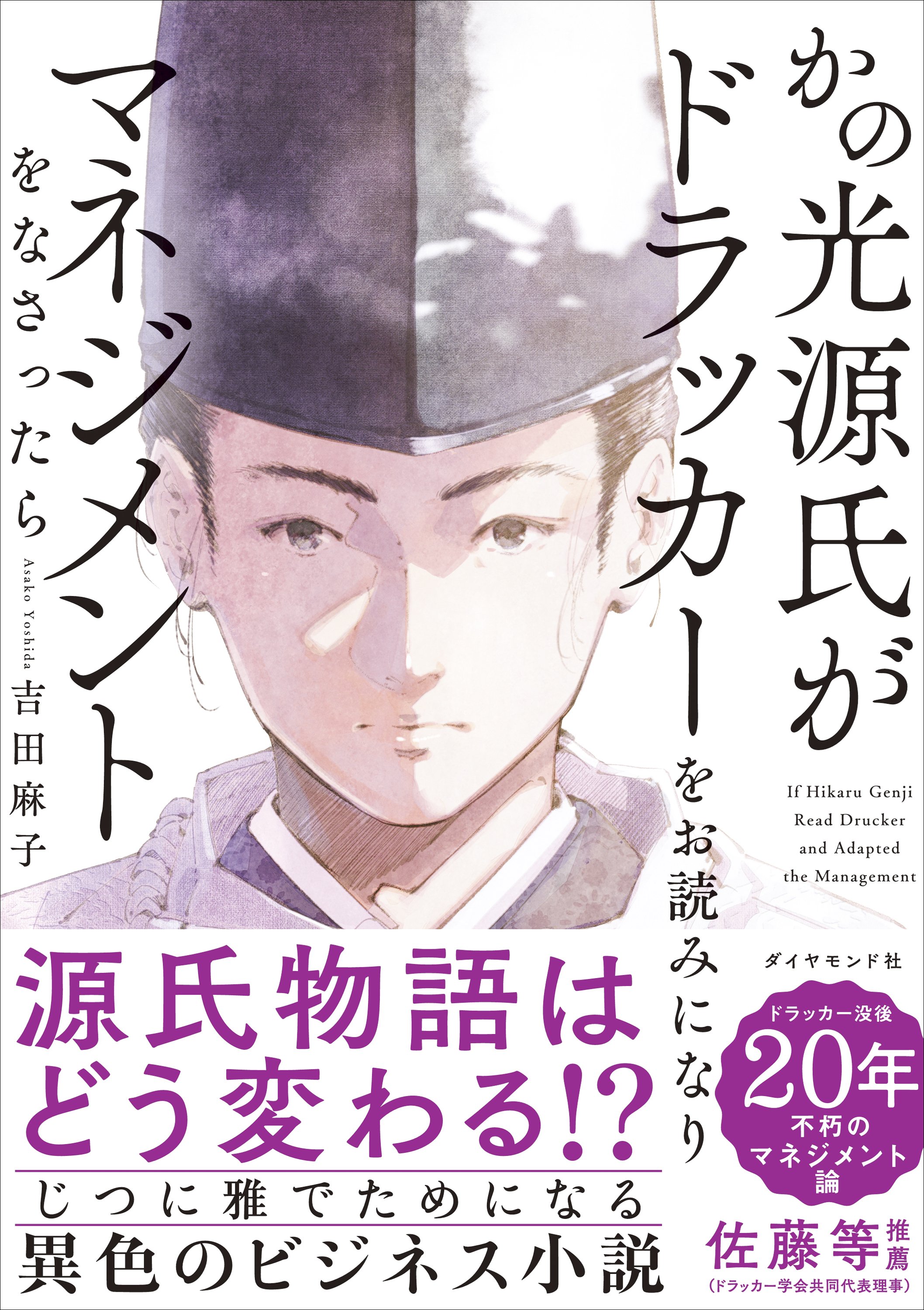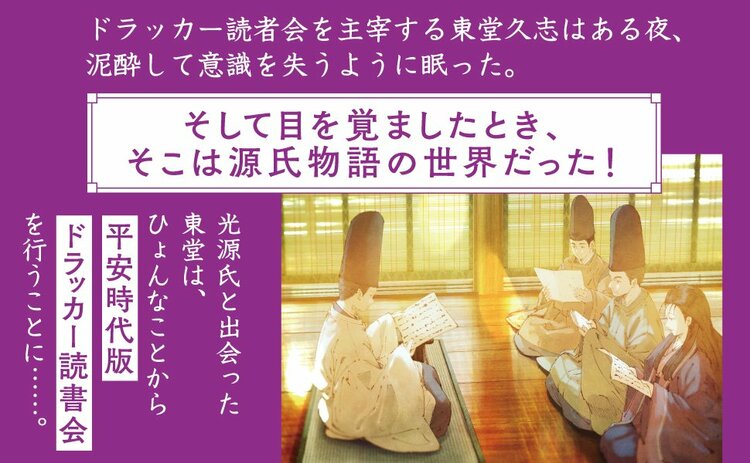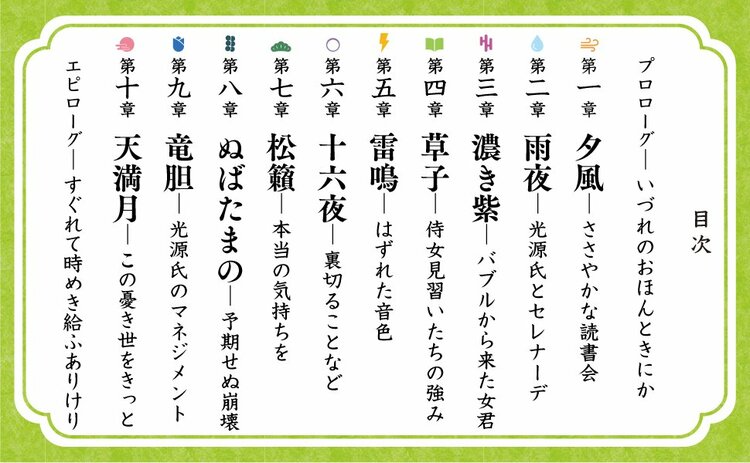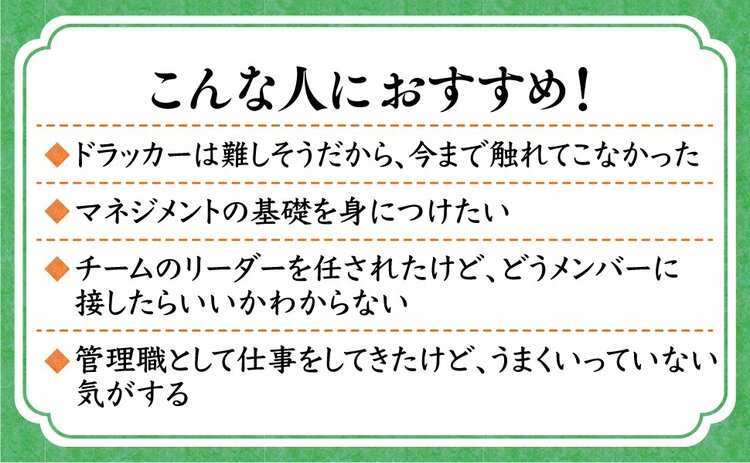「強みによる人事」の原則
――優秀な人を採用すると、その人用に仕事を変えてしまったり、その人用の仕事を作ってしまったりすることもあるかもしれませんが、ドラッカーはそういったことに警鐘を鳴らしているので触れておきましょう。
ドラッカーが強調した「強みによる人事」です。
『経営者の条件』にはこうあります。
「仕事を客観的かつ非属人的に構築しなければならない」
「人に合わせて仕事を構築するならば、組織や情実となれあいに向かう」
「組織は公平さと非属人的な公正さを必要とする」
ついつい「優秀な人に仕事を合わせよう」と考えてしまいがちですが、まずは仕事が適切に設計され、その適所に適材が配置されることが大切です。
Aさん「確かに、学歴で判断するのは“属人的な思い込み”かもしれませんね」
Bさん「スポーツやオーケストラも、まず仕事が先にあるもんなあ」
Cさん「採用基準をこの仕事はこの人の強みとどうつながるかに置き換えると、判断がシンプルになりそうです」
若者への問いかけ:自分を使って何をしたいか
――そして学生側から見た就職活動ということについても触れてみましょう。
学生側からの言葉を引き出すためにこの文章をお伝えします。
ドラッカーは『断絶の時代』でこう述べているんですよ。
「無数の選択肢を前にした若者が答えるべき問題は、何をしたらよいかではなく、自分を使って何をしたいかである」
「社会は、一人ひとりの人間に対し、自分は何か、何をしたらよいか、何を投じて何を得たいかを問うことを求める。この問いは、役所に入るか、企業に入るか、大学に残るかという俗な問題に見えながら、実は自らの実存に関わる問題である」
就職活動というのは、このような本質的なことを自らに問う重要な時期であるともいえます。「自分を使って何をしたいか」という問いを人事担当者が投げかけてみるのもよい対話を引き出せる方法となるかもしれませんね。
Aさん「自分を使って何をしたいか……いい言葉ですね」
Bさん「学生との面談で、この言葉を伝えてみたいです。すごく響きそう」
Cさん「採用側にとっても大事な視点ですね」
学歴だけでなく、その人が「自分をどう使いたいのか」という内的動機に耳を傾けること。それが成果に直結するのです。
ドラッカー的採用チェックポイント
もちろん、高学歴の人材を採用することは決して間違いではありません。
優秀な人材を惹きつけるために企業側が努力することもたくさんあります。
しかし、スペックだけの求め合いにならないためにも、本質的な対話が重要です。
そのためにもドラッカー的チェックポイントを3つに整理します。
・その仕事に強みを発揮できるか
・「自分をどう使いたいか」という問いにどう答えるか
この3つの視点で見直せば、学歴に振り回されない採用の基準がぐっと見えやすくなるかもしれません。