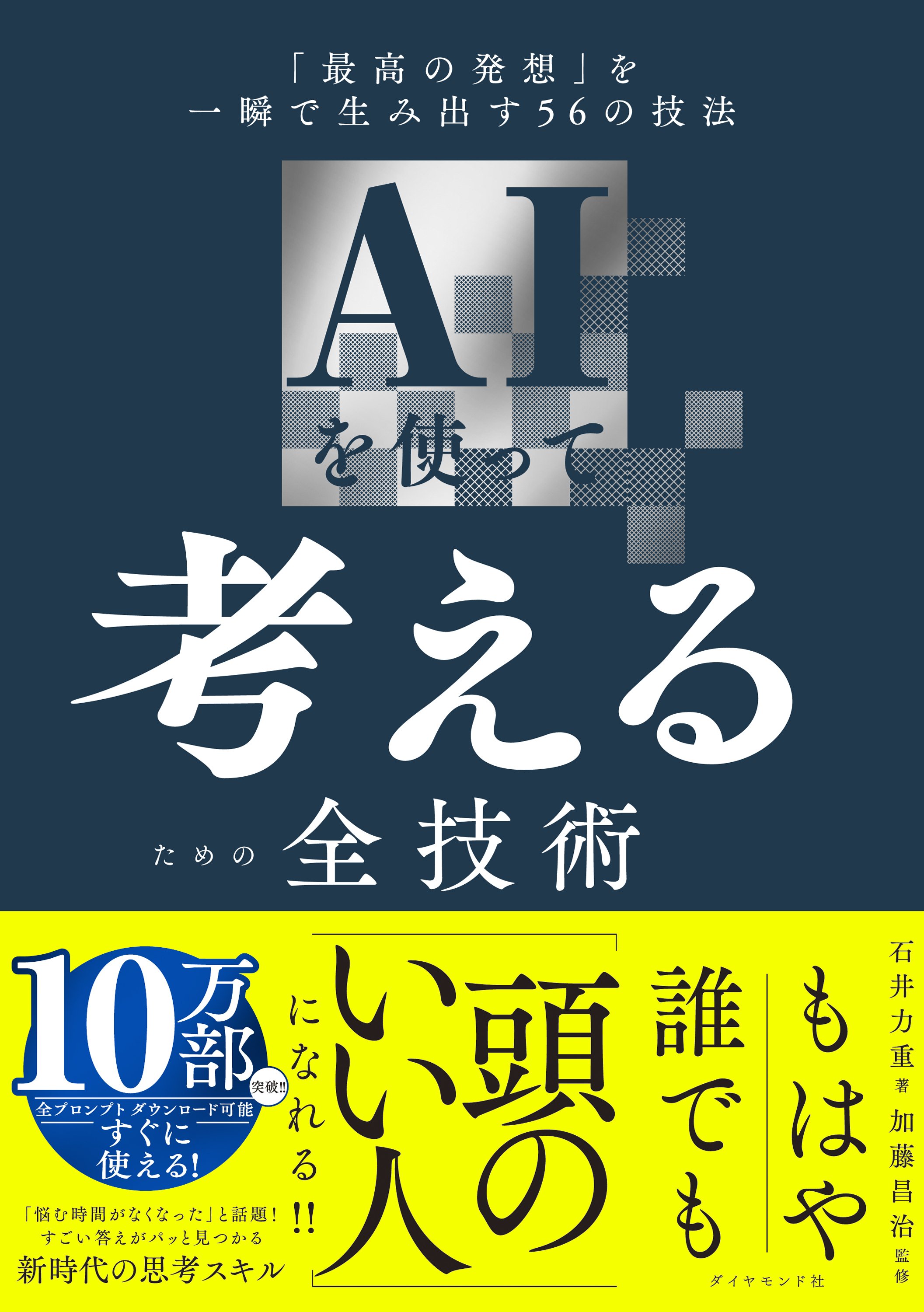AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
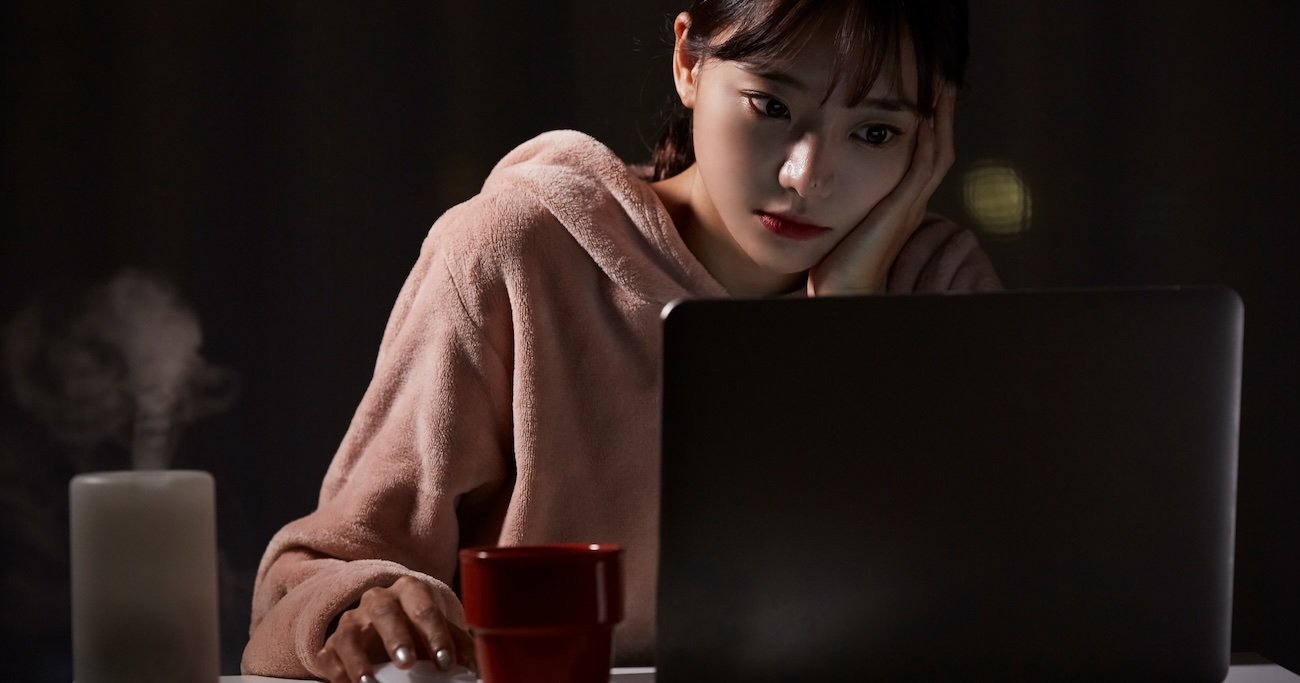 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
環境に配慮していないアイデアは受け入れられない時代
まさに今の時代に必要なアイデア発想について、紹介します。
本書の「はじめに」で、良いアイデアの定義とは「新しい+有用性」であるとお伝えしました。たしかにそれは人間や社会にとっては素晴らしいアイデアとなるでしょう。ですが、そのために人間以外の存在を蔑ろにしていいかというと、そうとは言えない時代です。
現代の、とくにビジネスアイデアにおいては、環境への配慮がとても重要な要素になりました。
B2C商品・サービスの領域では、価格が高かったとしても環境に優しい商品を選択する行動を指す「エシカル消費」という概念が生まれ、市民権を得ています。
環境に配慮した行動をとっている企業を評価する投資家も多くなってきました。「脱炭素」という言葉も、多くの企業が真剣に取り組み、すでに一般化していることは読者の皆さんもご存じのはず。
ユーザーの利便性を向上させるだけでは不充分なビジネス環境になりました。有用性と環境配慮、この両立を実現させるのが、今の時代におけるクリエイティブなアイデアであるとも言えるでしょう。
地球のことも考えたアイデアを出す技法「環境配慮の案」
その重要性には共感できる一方で、環境問題に関する情報は広く、深いものです。世界規模の話ですから、海外事情も知りたいところ。自分1人だけで考えたり、社内の身近なメンバーだけでブレインストーミングをしたりするだけではカバーできないこともあります。
人間だけでは足りないところは、AIで補強しましょう。情報や視点、切り口など、目を配っておくべき点の抜け漏れへの心配がかなり軽減できます。
そのための方法が、技法その6「環境配慮の案」です。そのプロンプトが、こちら。
〈課題などを記入〉について、持続可能なエネルギー源を活用したアイデアや、環境への影響を配慮したアイデアはありますか?
他の技法と同じようにAIに課題を投げて、環境に配慮したアイデアを出してもらうだけなんですが、シンプルに「環境に配慮した案を出して」と指示するのみでは抽象度が高く、理念的な回答に偏りがちです。
環境問題は多くのテーマ、課題、施策を含んでいるため、企業として取り組むウエイトの高い「再生エネルギー」をサンプル要素として示すことで、AIからの回答に要求する具体度のレベルを上げています。
セカンドオピニオン的なアイデアがほしいときにも有効
この技法は私がコンサルティングを提供している各企業の現場ニーズから生まれました。他の技法とは粒度も具体性も異なり、ことさらに環境問題に限定した発想法となっています。
基本的にはプロンプトどおりでOK。そのままで一般的な課題へも対応できます。とくに、環境に配慮する必要が当然視される課題なら、そのまま使ってください。環境問題に詳しくなくても、AIのサポートがあればある程度適切なアイデアを手に入れることができるでしょう。
より詳しく環境問題に対応する必要がある場合は、プロンプト上の「持続可能なエネルギー源を活用したアイデア」の部分をぜひ変更してください。「海洋プラスチックなどゴミ問題を考慮しながら」「雨水の再生利用技術など、どこでも使えるテクノロジーを参照して」など、直面している課題や出してもらいたいアイデアのイメージに即して、ケースバイケースで適切な要素を入れて回答を求めるといいでしょう。
「環境」とは関係のない課題に使うのもおすすめ
また、環境問題に限定せず、SDGsに含まれるような他の社会課題要素を入れて使うのもおすすめです。
さらには、環境への配慮をそこまで必要としないお題についても、この技法は役立つことが多いんです。
環境問題に配慮したアイデアとは、別の見方をすれば社会課題に対して敏感なアイデアとも言え、時代に対して先見性のあるものが多いからです。
実際、環境面から考えたことで、これまでとは方向性の異なるアイデアが見つかり、それがセカンドオピニオン(的なアイデア)として作用して、既存のアイデアに好影響を与えることもよくあります。他の技法とは結構違う切り口からのアイデアが多く出てくるため、その“カブり”のなさも良いところなのです。
技法その6「環境配慮の案」、ぜひ活用してみてください。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、AIを使って思考の質を高める方法を多数紹介しています)