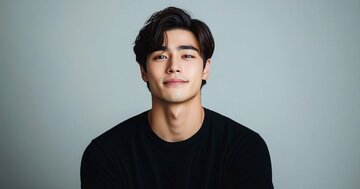AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って「思いつき」を仕事に活かす
メールの作成、資料の作成や要約、英語の翻訳……などなど。AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。
AIは、「頭を使う作業」に活用してこそ、その真価が発揮されると考えています。たとえば、思いつきを仕事に活かすことにもAIは活用できます。
その方法の1つが、技法その53「着想のターゲット」。
これを使えば、思いついたアイデアが実現した際にユーザーとなる可能性のある人を探ることができます。
こちらが、そのプロンプトです。
〈商品やサービスのアイデアを記入〉という製品コンセプトに対して、仮定されるユーザー層はどのような市場や人々と想像しますか?
「こんな商品があったらいいな」「サービスがあったらいいな」と、妄想のようにアイデアだけが浮かぶことがあります。ただ「面白そう」という場合も多いと思います。
そういったアイデアや技術が先行して誕生した商品にも、のちにヒット商品となったケースは現実に存在します。
そこで、「~~なアイデアがあるんだけど、これは誰にとって有用だろうか?」とAIに問うのが、この技法です。アイデアに対して興味を持ってくれる可能性がある人を見いだせれば、その人たちが喜ぶようにアイデアを磨くこともできるでしょう。
「語呂合わせサービス」で喜ぶ人を探ってみよう
では、実践してみましょう。私がとあるワークショップで出合った、ちょっと突飛なアイデアを例として使ってみます。
それは「どんな数字や言葉でも、すぐに覚えやすい語呂合わせを考える」というサービスです。電話番号など数字の羅列を覚えたり、歴史の年号を覚えたり、化学の元素記号を覚えたりと、様々なところで語呂合わせは私たちを助けてくれています。しかしスマートフォンでなんでも記録、登録、検索できる今の時代、電話番号を覚える必要はほぼなくなりました。暗記教育の弊害も昨今では叫ばれています。そんな時代に、はたして「語呂合わせをつくる」サービスにユーザーは存在するのでしょうか?
〈どんな数字や言葉でも、すぐに覚えやすい語呂合わせを考える〉という製品コンセプトに対して、仮定されるユーザー層はどのような市場や人々と想像しますか?
この技法を使うときは、こちらもユーザーがイメージできていないわけですから、回答を待つ間はちょっとドキドキしますね。