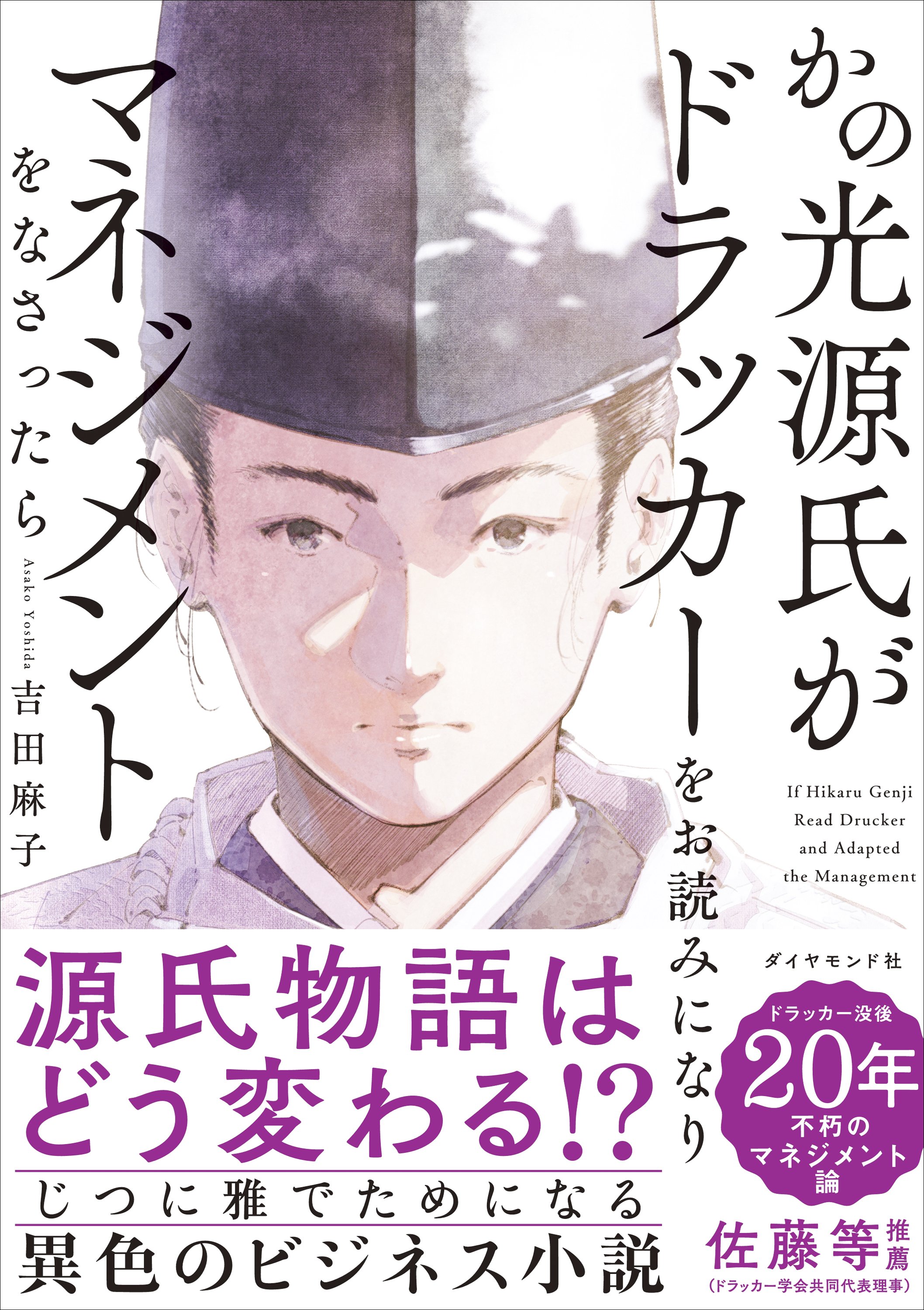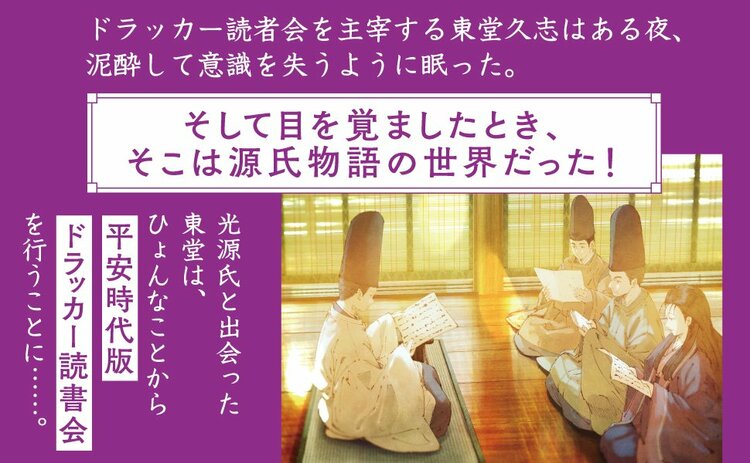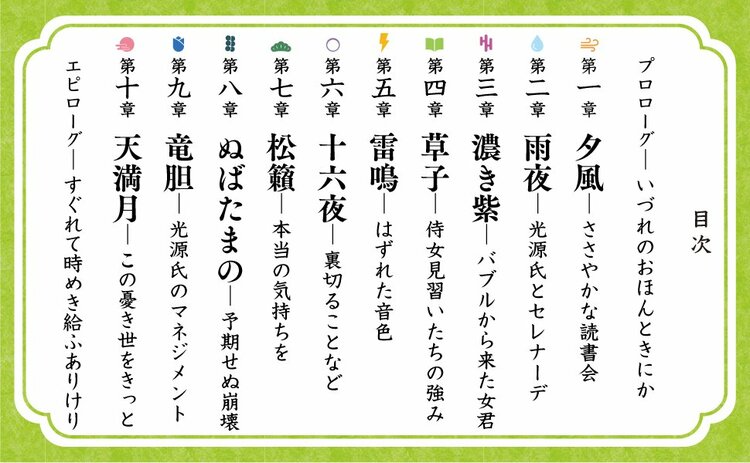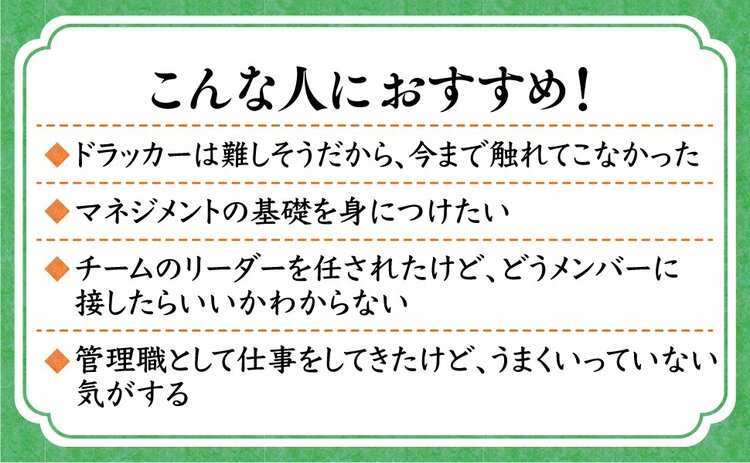マネジャーには二つの役割がある
――著書『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』でも、集団行動なのに音を外してしまう楽人が登場しますね。現代でも、仕事ができない部下にマネジャーはどうすべきでしょうか。
ドラッカーはマネジャーには二つの役割があると『マネジメント』で言っています。
・第一の役割:部分の和よりも大きな全体、すなわち投入した資源の総和よりも大きなものを生み出す生産体を創造すること
・第二の役割:そのあらゆる決定と行動において、ただちに必要とされているものと遠い将来に必要とされるものを調和させていくことである
第一の役割では、「したがってマネジャーは、自らの資源、特に人的資源のあらゆる強みを発揮させるとともに、あらゆる弱みを消さなければならない。これこそ真の全体を創造する唯一の方法である」としています。
つまり、仕事ができない部下に対しても「弱みを直す」だけではなく、「強みを生かして全体の成果につなげる」方向づけが必要になるのです。
また、第二の役割では「石臼に鼻を突きつけつつ丘の上を見るという曲芸をしなければならない」とドラッカーは言います。
目の前の短期的課題を処理しつつ、長期的な成長や組織の方向性も同時に見据えること。これはマネジャーならではのバランス感覚です。
『現代の経営』には次のようにあります。
「今日必要とされているものは、一人ひとりの人の強みと責任を最大限に発揮させ、彼らのビジョンと行動に共通の方向性を与え、チームワークを発揮させるためのマネジメントの原理、すなわち一人ひとりの目標と全体の利益を調和させるためのマネジメントの原理である」
つまり、効率が悪い、気が利かないと見える部下も、「強み」と「方向性」を見出せば、チーム全体の成果に貢献し得るのです。
具体的には、こうした視点をもつことが役立ちます。
・その人が何に時間をかけると成果につながるのか
・どの場面で存在感を発揮できるのか
・チーム全体の成果と個人の目標をどう結びつけるのか
この視点を持ち続けることで、「音を外す楽人」も、オーケストラ全体にとって欠かせない一員へと変わっていく可能性があります。
マネジャーの役割は「弱点の矯正」ではなく、「強みの発見と方向付け」です。
足並みを揃えさせるのではなく、一人ひとりの強みを組織の成果につなげる。そのとき初めて、全体は部分の和を超えた大きなものを生み出します。