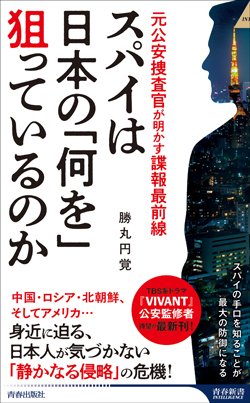神社や観光地にスパイの機密文書が…?
実際に過去、東京の世田谷八幡宮で、ベンチの下に瓶を埋めて情報をやり取りしていたスパイがいました。神社のようにめったに工事をされない場所は、諜報活動にとって理想的な拠点です。その他には、岐阜県の白川郷のような観光地でも、警備が手薄な場所では同様の方法が取りやすくなります。
さらに、「フラッシュコンタクト」といって、すれ違いざまにUSBメモリなどのデバイスを渡すという手法もあります。一瞬の出来事なので、誰が誰に渡したのかを特定するのは非常に困難ですし、監視カメラがあっても検出が難しい場合もあります。
映画、ドラマ、小説の世界だけでなく、こうした方法は今も現実の情報戦の現場で使われているのです。私の外事警察の先輩には、かつては手紙の封を水蒸気で開封し、内容を小型カメラで撮影してから再度、封をし直すという技術があったと聞きました。
現在ではそうした技術を持つ公安捜査官はほとんどいませんが、暗号化されたメッセージを、換字表や乱数表を使って解読する公安捜査官は存在します。
要するに、スパイというのは「見られるリスク」を前提に動いている。だからこそ、アナログな方法が今でも使われているわけです。私たちが気づかないところで、情報の受け渡しは日常の中に溶け込むように行われています。そうした目に見えない脅威を認識し、社会全体で警戒していく必要があると、私は感じています。