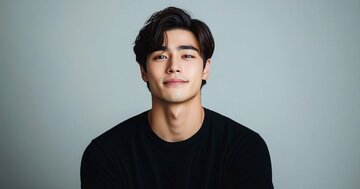AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って「ビジネスの将来」を予測する
メールの作成、資料の作成や要約、英語の翻訳……などなど。AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。
AIは、「頭を使う作業」に活用してこそ、その真価が発揮されると考えています。たとえば、ビジネスの将来像を描くことにもAIは活用できます。
その方法の1つが、技法その15「未来の変化因子」。
これを使えば、対象の変化に影響を与える因子を踏まえて、ビジネスの未来を構想できます。
こちらが、そのプロンプトです。
まず、〈アイデアを得たい対象を記入〉の今後10年間の変化に大きな影響を与えそうな因子をあげてください。次にその因子が充分に発展した場合の10年後の対象の姿をデザインしてください。最後にそれらを「N年後、●●する」という表記で3ステップの実現性を加味した構想を描いてください。
「バックキャスティング」という考え方があります。まず10年後や20年後と、はるか未来を予想し、そこから「10年後が~~なら、その6~7年前だとまだ~~の段階だろうから、今から3年後は~~な感じかな?」と、着地点から逆算して考える発想法です。
そのバックキャスティングをAIで行う方法が、技法「未来の変化因子」です。AIの力で、軽々と遠い未来像を手に入れることができます。既存の流れから妥当に考えてもあまり新しい発想が出てこないときや、未来の洞察を踏まえて構想したいときに威力を発揮する技法です。
10年後も通用する「金属加工」のアイデアを考えてみよう
では、実践してみましょう。
変化のスピードが速い現代、これまで100年以上続いてきた生活習慣や、30年、40年と利益を上げてきたビジネスモデルも、数年先のことはわかりません。そういった非連続な未来を想像しにくい成熟したビジネスのお題こそ、「未来の変化因子」との相性が良いと思います。
たとえば成熟産業である「金属加工」という業界がさらに発展するアイデアはあるのでしょうか?
まず、〈金属加工〉の今後10年間の変化に大きな影響を与えそうな因子をあげてください。次にその因子が充分に発展した場合の10年後の対象の姿をデザインしてください。最後にそれらを「N年後、●●する」という表記で3ステップの実現性を加味した構想を描いてください。
先に未来像を予想してもらい、その未来にいたる道のりとしてアイデアをあげてもらいます。