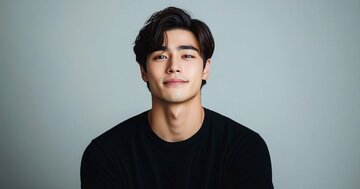AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIから“質の良い回答”を得られる「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、AIから「意外性のある極端なアイデア」を引き出したいときにおすすめなのが、技法その2「10倍の目標」です。
こちらが、そのプロンプトです。
本来の発想のお題〈課題や目標を記入〉に含まれる目標を10倍高い目標にしたお題を生成してください。次にその目標が実現している状態を7つ連想してください。最後に各々の状態を切り口にして、「本来の発想のお題」について「魅力的で、実行しやすいアイデア」を提案してください。
「エクストリーム・ゴール」と呼ばれる発想法があります。アイデアを出してはみたが、どうも平凡で新味がないとき、わざと10倍高い目標を仮定して考えてみると、奇策を練ったり、激しく特化した案を考案する必要に“追い込まれ”ます。そうして得られたヒントを本来のゴールに適用して、新しさのあるアイデアを手にする発想法です。
この発想法を、AIの力を借りて行うのが技法「10倍の目標」です。
1000回洗っても大丈夫な「タオル」を考えてみよう
では、実践してみましょう。この技法は、地道なアプローチだけではなく、意外性のあるアプローチによって斬新なアイデアを見つけたいときに適しています。
そこで、なかなか斬新さを生み出すのが難しい、タオルの商品改良にこの技法を使ってみましょう。耐久性など、品質を示す数値を設定して実践してみます。
本来の発想のお題〈新品のタオルが洗濯を100回した程度でダメになっていく〉に含まれる目標を10倍高い目標にしたお題を生成してください。次にその目標が実現している状態を7つ連想してください。最後に各々の状態を切り口にして、「本来の発想のお題」について「魅力的で、実行しやすいアイデア」を提案してください。
まずお題の生成、そして10倍にしたゴールの設定。続けてそのゴールを達成するためのアイデアを出して、という流れでプロンプトが設定されています。