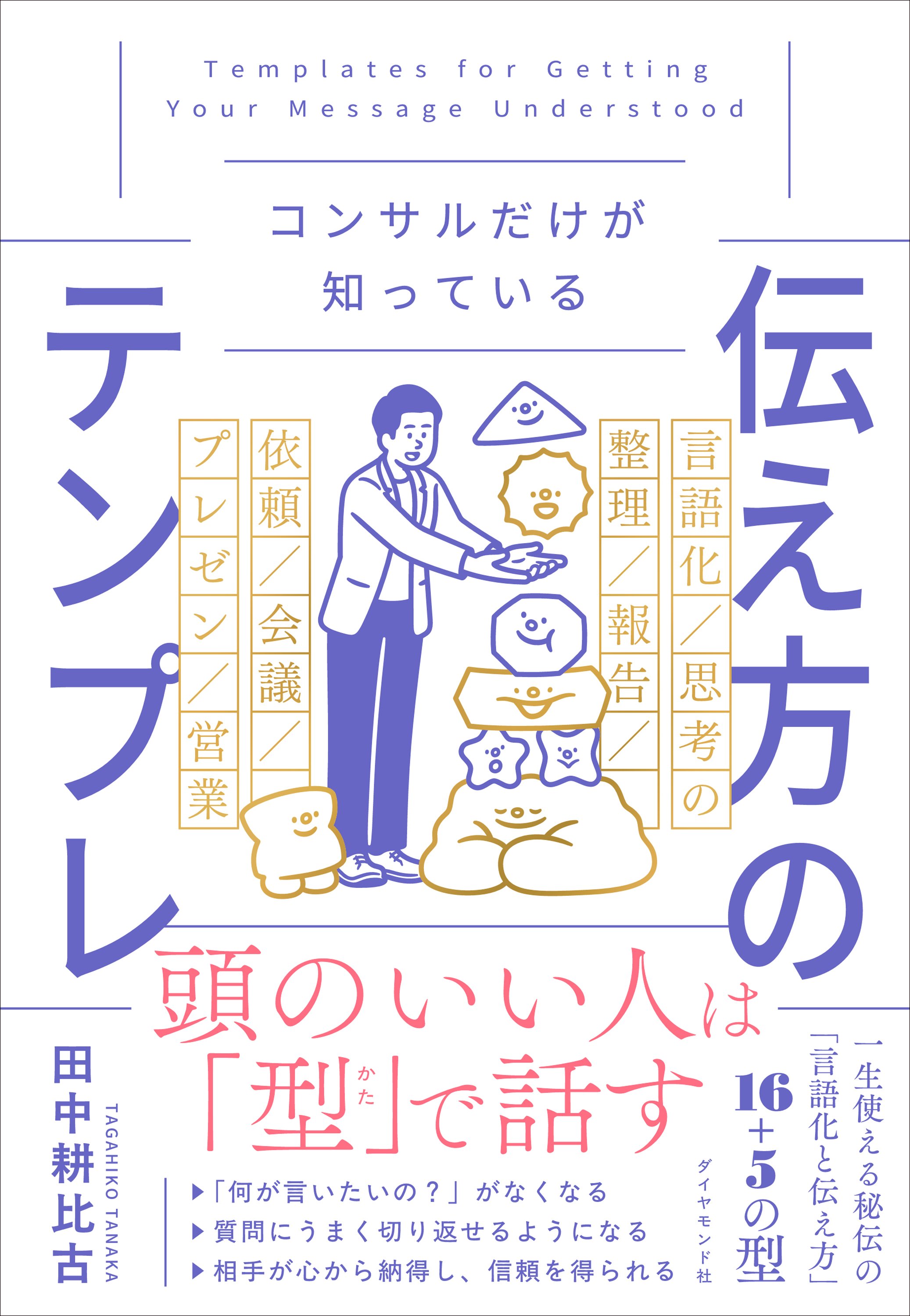そもそも、話の中身が時系列のステップ論になってしまっていて、どこが要点なのか、聞いている方はよくわからなくなってしまうでしょう。
ここで大切なのは、「何がこの話の“幹”なのか」を見極めることです。
“枝葉”を捨てて、“幹”だけに絞り込む。これが、非常に重要なポイントです。
ここでの話の“幹”、すなわちメインストーリーは、
・ 既知の事実:来月の広島出張で■■社に行く
・ その後の動き:追加訪問をしたい
・ 新しい情報:2社追加になった
です。
グッとシンプルになりますね。
話の“枝葉”の
効果的な使い方
その他の情報は全て“枝葉”です。
具体的には、次のように考えて、“枝払い”を行います。
・ 10日から1泊2日→広島出張が、来月のうちに複数回あるのなら必要な情報かもしれないが、普通に考えれば不要
・ ■■社の工場見学とその後の会食→訪問の具体的内容は、ここでは重要ではない
・ 広島支社と連携→広島支社のことを立てたい、などの特別な意図が無ければ不要
・ 特定の条件でスクリーニングして4社をリストアップ→中間プロセスのため不要
・ X社とY社の詳細情報→入れるとしても社名まで。社名だけでは、何の会社かわからないというなら、ここでは「2社」という情報のみで十分
・ アポの時間+もう1社設定できないか調整中→言うとしても、「空き時間にもう1社入れられないか調整中」で十分
普段のミーティングでも“枝葉”は捨てるべきシーンが多いのですが、特に時間が限られている場面では、思い切って「バッサリ捨てる」勇気を持ちましょう。
なお、こうして払った枝葉については、
1. まだ話せそうなら、いくつかピックアップして話す(枝の中でも、太いものを選んで伝える)
2. 後で補足する機会を作る
という使い方をするとよいでしょう。
特に2つめの「後で補足する」については、「詳細はメールを送りますので、あとで読んでおいてください」とか「明日の定例ミーティングの際に、日程や訪問先情報を詳しくお伝えします」などの言葉を最後に添えることで、情報が分断されず、話につながりをつくることができます(詳しくは『頭のいい人が〈会議の最初と最後〉に必ずやっている大切なこと』)。
このように情報を整理することができると、短い場面でパッと伝えることができるようになるだけでなく、資料作りにおいても、言いたいことをクリアにする技術が磨かれます。
言いたいことを言いたいように伝えるのではなく、相手が知りたいであろうことを想像して伝え方を工夫する。
自分にとっても相手にとっても、良い効果を生むと思います。是非、実践してみてください。