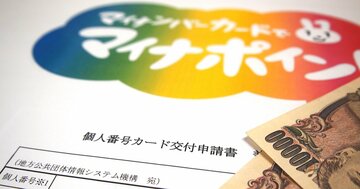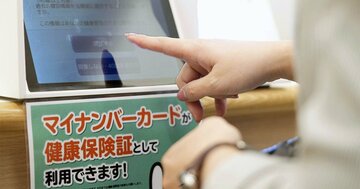写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
病気やケガで仕事を休むことになって、いきなり無収入に……ということがないように、公的医療保険で補償が定められている「傷病手当金」。しかし、誰もが対象というわけではない。『医療費の裏ワザと落とし穴』299回は、その仕組みと、給付を受けられるようにするための働き方を解説する。(フリーライター 早川幸子)
被用者保険の加入者なら
万一の時に所得補償がもらえる
公的医療保険の給付のひとつである「傷病手当金」。病気やケガで仕事を休んでいる間の所得を補償してくれるものだが、「療養の給付」や「高額療養費」とは異なり、すべての人がもらえるわけではない。実質的に傷病手当金を給付しているのは、企業や団体などに雇用されている人が加入する被用者保険だけとなっている。
一応、国民健康保険法(第58条の2)でも、保険者が任意で「傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」と定められており、業種単位で組織されている国民健康保険組合の一部は傷病手当金の給付を行っている。
だが、医師国保や建設国保など財源に余裕のある組合だけで、地域単位の都道府県国保で傷病手当金を給付しているところは皆無だ。つまり、傷病手当金は賃金労働者の特権ともいえるのだ。
傷病手当金をもらえれば、病気やケガをして仕事を休んでも、いきなり無収入になるという心配はない。そこで、今回は傷病手当金の仕組みとともに、給付を受けられるようにするための働き方について見ていきたい。
労働者のための健康保険が創設されたのは、第一次世界大戦後の世界恐慌で社会が大きく混乱していた頃だ。今も昔も産業の発展は労働者の働きにかかっているが、当時はストライキやサボタージュが頻発し、労働効率が低下するようになっていた。産業の停滞を招く労働争議を減らすためには、労働者の待遇改善と生活の安定が必要だった。