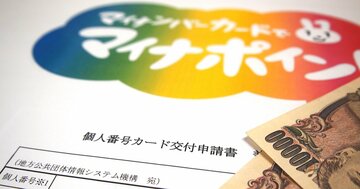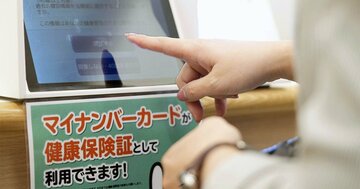働き始めてから支給開始日までの期間が12カ月に満たない場合は、就職から休職する前月までの標準報酬月額の平均額と、全加入者の標準報酬月額の平均を比較して、少ない方の金額をもとに計算する。
休業中も勤務先から満額の給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されない。だが、給与が減額されていて、傷病手当金の支給額に届かない場合は、その差額が給付される。
被用者保険の適用拡大が進み
企業規模や賃金要件が撤廃される
このように、被用者保険に加入していれば、病気やケガで仕事を休んでも、月収の3分の2程度の傷病手当金が最大で1年6カ月分給付される。給与の全額には届かないが、収入がゼロになるわけではないので、傷病手当金のない国民健康保険に比べると被用者保険が有利なことは間違いない。
正規雇用だろうと、非正規雇用だろうと、企業や団体に雇用されている労働者にとって、勤務先からの賃金が生活の糧であることは変わらない。病気やケガをして給与がもらえなくなったら、経済的リスクが発生する。だが、現状では、企業や団体に雇用されている賃金労働者のすべてが被用者保険に加入しているわけではない。
正規雇用の場合は就職とともに健康保険に強制加入する。だが、同じ被用者でもパートやアルバイトなどの短時間労働者は、一定の要件を満たした人のみが加入することになっている。
現在、被用者保険への加入が義務づけられている短時間労働者は、「年収106万円以上(月収8万8000円以上)」「週の労働時間が20時間以上」「従業員数51人以上の企業労働者」「学生ではない」といった条件を満たした人だ。
この要件から外れると、A家族が加入している健康保険の被扶養者になるか、もしくは、B自分で保険料を負担して国民健康保険に加入することになる。
例えば、Aは被用者保険に加入している夫がいて、年収要件などを満たすことで、パートで働く妻は被扶養者として夫の健康保険に加入するというケースが考えられる。保険料の負担なしで公的医療保険に加入できるが、被扶養者は傷病手当金の給付対象外だ。
また、Bは、同じようにパートやアルバイトでも、夫が自営業だったり、労働者本人がシングルマザーだったりするケースだ。国民健康保険には被扶養者という制度はなく、収入や家族の人数に応じた保険料負担が発生するが、傷病手当金の給付はない。
病気やケガで仕事を休んだ場合の経済的リスクは同じなのに、社会保険の適用を受けていない短時間労働者は所得補償がないという不利な状態に置かれているのだ。