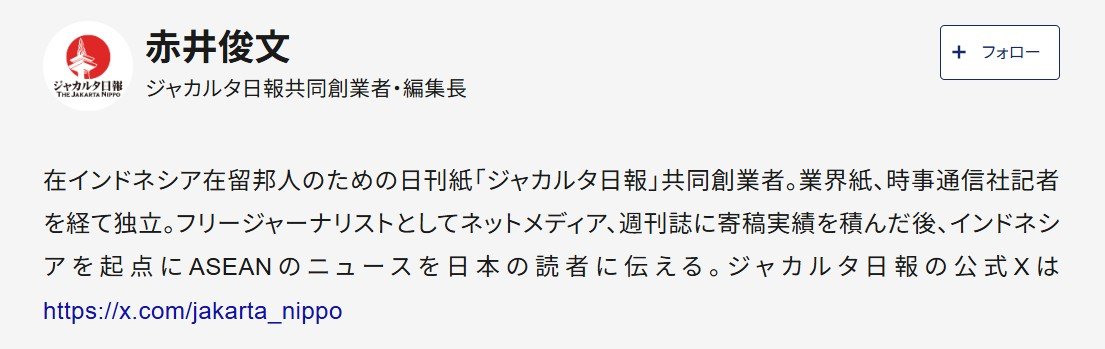そもそもこの規制は、5月に中国自動車大手・長城汽車の魏建軍会長が、激化するEVの価格競争について「自動車メーカーや部品サプライヤーの収益を圧迫している」と懸念をあらわにしたことに端を発する。魏氏は、巨額債務危機の末に清算された不動産ディベロッパー恒大集団を引き合いに出し、「自動車業界にも同様の存在がある」などと語った。
魏氏はBYDを名指しこそしなかったものの、自社を批判されたとみなしたBYD側が「恒大のような危機は存在しない」と反論する騒動にまで発展。うがった見方をすれば要するに、中国自動車業界の内輪揉め、新旧メーカーの足の引っ張り合いがきっかけだったのだ。
ただし実際、EVの価格競争の長期化で完成車メーカーの資金繰りが厳しく、下請けサプライヤーに支払い延期や手形・電子約束の受入れを求める商習慣が定着していた背景はある。当然ながらサプライヤーの運転資金も圧迫され、問題視されていた。これが、習近平政権の「共同富裕」の理念に反するとして、6月に新規制が始まったというわけだ。
さて、6月頭の新規制から3カ月が経過した。中国EVメーカーが狙う東南アジア市場では、早くも異変が起きている。特にBYDはタイに続きカンボジア、インドネシア、マレーシア、ベトナムなどで工場建設ラッシュだが、中国人ファーストのやり方が地元の反社会的勢力との対立を招いているという。
そして自動車業界が避けて通れない「トランプ関税」の影響はどうなっているのか。BYDが得意とする「安売り攻勢」は今後も通用するのか。生産拠点としてもモータリゼーション著しいマーケットとしても有望で、日本車の牙城だった東南アジアで何が起きているのか。『中国BYDの「EV安売り」攻勢に暗雲…シェア拡大戦略に立ちはだかる“巨大な壁”とは』では、現地情報を詳報する。