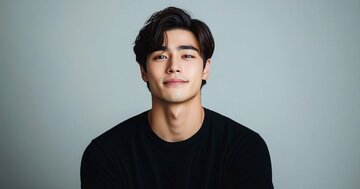AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って自分の“創造力”を解き放つ「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、アイデアや課題解決策を創造的に考えたいときにおすすめなのが、技法その7「関連する要素」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈課題や目的を記入〉
この問題から連想できる単語を30個あげ、次に関連が薄くてもいいので連想できる単語を100個あげてください。
じつは、「創造力」は高めることができます。
創造力を発揮するにいたる源泉に、連想力があるからです。連想力を自在に扱えるようになれば、想像力が豊かになり、最終的には創造力の発揮につながるのです。
そして「連想」には、有名な以下の4つの型があります。
・接近:対象の“近くにある”ものはなんだろう?
・類似:対象と“似ている”ものはなんだろう?
・対照:対象と“何かしらが反対である”ものはなんだろう?
・原因結果:対象が“生み出す”もの、対象を“生み出す”ものはなんだろう?
この4つの連想技を使えるようになることが、私たちの連想力、そして創造力を高めてくれます。
ただ、そうはいっても、コツをつかむまでには時間がかかるもの。そこで、この型を使って連想する作業をAIにアシストしてもらうための技法が、この「関連する要素」です。AIにお題を投げて、そこから連想する言葉を瞬時に生み出してもらいます。
「自分らしい家づくり」の方法を考えてみよう
では、実践に行きましょう。一般的に、これまで取り組んだことのないお題に対しては創造力を発揮しにくいもの。
「自宅を建てる」なんて、まさにそんなお題。「さて、どこから手を付けようか?」と迷ったときには、この技法が有効です。急がば回れ。いきなりアイデア出しから入るのではなく、まずは「関連する要素」のチカラを借りて、アイデアへのヒントを探ってみましょう。
〈自分らしい暮らしができる家づくりをしたい〉
この問題から連想できる単語を30個あげ、次に関連が薄くてもいいので連想できる単語を100個あげてください。
「“自分”って言われて、AIはわかるの?」と思ったでしょうか。はい、AIは「自分」が誰か知らないでしょうね。回答の精度を上げるなら、「自分たちは~~で、~~で、~~なことを大事にしています」などの自己紹介的なやりとりを先に行っておくとベター。
ただ、「アイデアを出す」ためにAIを使うのなら、そこまでの個人情報は入れなくても大丈夫です。なぜならAIと一緒に考える自分たち側にその情報があるからです。ということで本稿では前置きなしバージョンで進めます。