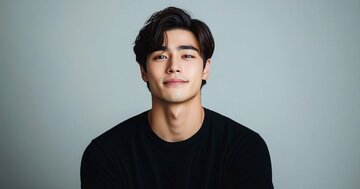AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“行き詰まり”を突破できる「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、課題解決のアイデア出しに行き詰まったときにおすすめなのが、技法その4「アートの示唆」です。
こちらが、そのプロンプトです。
〈課題を記入〉
このお題に関して、有名な小説や絵画から得られる創造的なアイデアは何ですか?
じつはアイデア発想にもアートって使えます。古今東西のアート作品や、アーティストが考えたことを、アイデアのヒントにするんです。距離のある要素だからこそ、結びつけることでアイデアの幅が拡がります。
「人事制度」の改革アイデアを考えてみよう
では、実践してみましょう。
あえてアートとはかなり距離のあるお題、たとえば「人事制度」なんて堅いお題で試してみましょう。
〈硬直的な人事制度が問題になってきている。しかし良い改革の方法が浮かばない〉
このお題に関して、有名な小説や絵画から得られる創造的なアイデアは何ですか?
普通なら、芸術的な作品から人事制度に関するアイデアのエッセンスを得ようとしたりしないでしょうけれど……さて、回答はいかに。