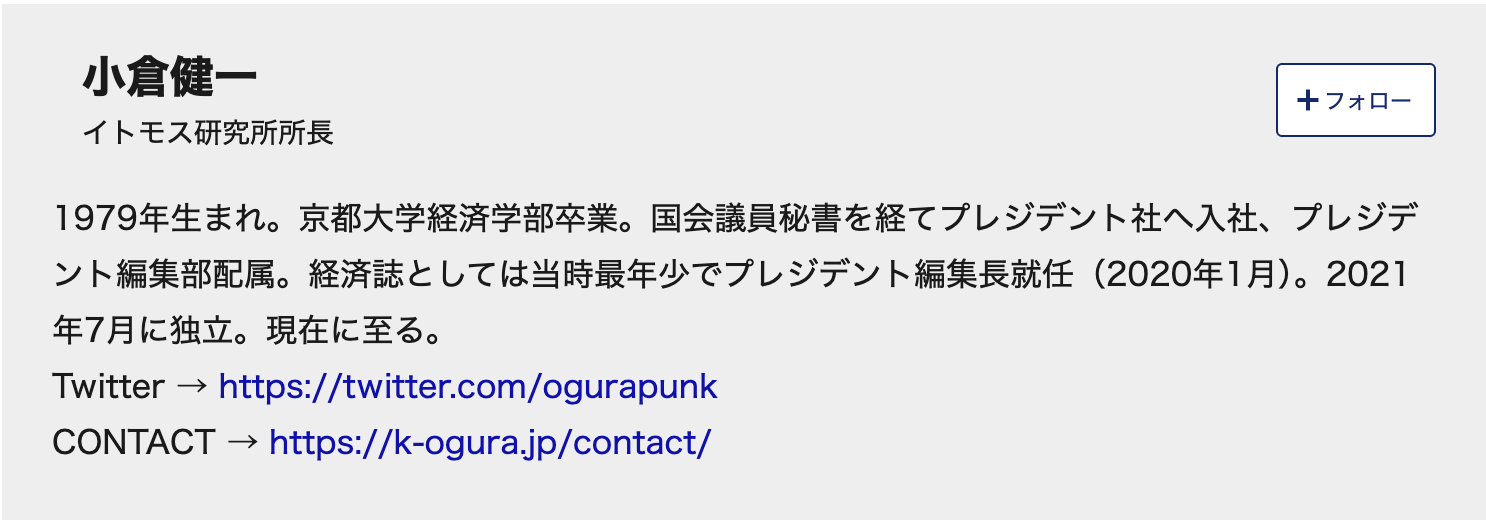残る従業員に対するメッセージの方が重要
論文では、上司が部下に与える影響を2つの戦術に分類した。一つは部下に過度な要求や脅しを用いる「プレッシャー」、もう一つは部下の価値観や理想に働きかける「インスピレーショナル・アピール」である。研究の結論は明確であった。
管理者が部下に使う『プレッシャー(圧力)』は、従業員の感情的なエンゲージメント(仕事への熱意や愛着)を低下させ、離職率を高める。逆に、管理者が『インスピレーショナル・アピール(鼓舞するような働きかけ)』を行うと、エンゲージメントが高まり、離職率は低下するという。
一見すると、稲盛氏の厳しい叱責は「プレッシャー」に分類されるように思えるかもしれない。しかし、稲盛氏の行動を深く考察すると、その本質が全く異なる場所にあることがわかる。
彼の怒りは、抗議してきた若手社員たち、そして会社に残る全ての従業員に対する、極めて強烈な「インスピレーショナル・アピール」であった。
去っていく者に安易な同情を寄せず、「残って頑張っている君達こそが立派だ」と断言する行為は、残された従業員の自尊心と組織への帰属意識を劇的に高める効果を持つ。
短期的な個人の感情に迎合するのではない。組織全体のエンゲージメントを長期的に向上させるための、計算され尽くした高度なマネジメント手法であった。
稲盛和夫の厳しさは、組織という共同体を守り、発展させるという大局的な視点に基づいた、深い愛情の表現だったのである。
稲盛が示した「去る者は追わず」の姿勢は、自己の都合や無関心から生まれたものではない。その根底には、会社と共に歩むと決めてくれた従業員への限りない感謝と敬意、そして自らが信じる経営哲学への揺るぎない確信が存在した。
彼の厳しさは、感情的な反応ではなく、組織全体の士気を高め、一体感を醸成するための意図的なリーダーシップの発露であった。現代の経営者が直面する人材流出の問題に対して、稲盛の哲学は重要な示唆を与えてくれる。
つまり、去りゆく個人の感傷に寄り添うこと以上に、組織としての一貫した理念を掲げ、残る仲間に対して明確で力強いメッセージを発信し続けることの重要性である。