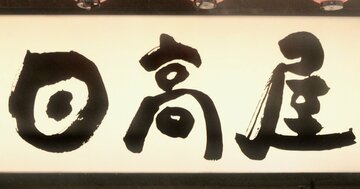Photo:JIJI
Photo:JIJI
近年、企業にとって従業員の離職は避けて通れない問題だ。引き止めるのか、それとも快く送り出すのか――反応はさまざまだろうが、経営の神様・稲盛和夫の反応は強烈だった。(イトモス研究所所長 小倉健一)
会社を辞める部下が続々…稲盛和夫の衝撃の対応とは
現代経営にとって従業員の離職は、事業の根幹を揺るがしかねない深刻な問題である。
手塩にかけて育てようとした部下が、実は本人が全く異なる未来を描いて組織を去る現実に直面することは少なくない。上司としては、期待をかけていただけに、経営者自身が否定されたような喪失感に襲われることもあるだろう。
離職を決意した側も、私自身の経験を振り返ればさまざまな記憶がよみがえる。
激しく引き止められることもあれば、驚くほどあっさりとした大人の対応をされることもあった。引き止めがあまりないときには、拍子抜けというか、どこか寂しさを感じたこともあった。
深刻な人材不足が叫ばれる現代において、去りゆく従業員にどのような態度で臨むのが最適解なのか。明確な答えを見出すのは極めて困難である。
経営の神様と称された稲盛和夫氏は、従業員の離職という問題に対して、常人とは一線を画す哲学を持っていた。
古代中国の思想家、孟子の言葉に由来する「来るものは拒まず、去るものは追わず」という故事成語がある。近づく者を受け入れ、去る者を無理に引き止めないという、相手の自由意志を尊重する寛容な姿勢を示す言葉として広く知られている。
稲盛氏もまた「去る者は追わない」という点では同じであった。ただ、稲盛の哲学の根底にある思想は、一般的な解釈とは全く異質のものであった。