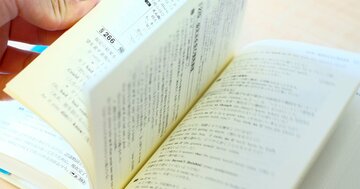写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
英語学習で「ネイティブに近づくべき」という思い込みを今すぐ捨てよう。ただし、英語のルールから外れ過ぎても通じない。では、発音や文法の「必要最低限ライン」や「許容範囲」は何だろうか?受験勉強やTOEIC、オンライン英会話やChatGPTはどのように活用すればいいか、合わせて解説しよう。(パタプライングリッシュ教材開発者 松尾光治)
日本人と韓国人は
「英語ネイティブ」信仰が強いけど…
YouTubeやSNSには、「その英語、ネイティブにはこう聞こえます」「ネイティブはそう言いません」といったタイトルのコンテンツが多い。英語学習に関して、日本では「ネイティブ信仰」が強いからだろう。ちなみに日本人の英語力に関して比較対象になりがちな韓国人も、同じくネイティブ信仰が強い。
しかし実は今、ネイティブのような英語を目指す必要はなくなってきている。非ネイティブ同士で英語を使う場面の方が多いからだ。そこで活躍するのは、発音も文法もネイティブ並みの英語ではなく、「相手と噛み合う伝達力のある、分かりやすい英語」だ。
実際、英語教育界ではかなり前から変わり始めている。1990年代以降のグローバル化で、「World Englishes」(直訳すると「世界の英語たち」)という考え方が生まれた。World Englishesにおける英語は、「Lingua Franca」(リンガ・フランカ、共通語)などと呼ばれる。
日本人の話す英語の特徴は、国際的にも結構知られている。「礼儀正しい」「相手への配慮を示す言葉が多い」「謙虚な姿勢が感じられる」「文法ルールに忠実であろうとする」といった理由から、おおむね好意的に受け取られている。
日本人が気にしがちな発音や文法のミスについては、少なくとも通じるレベルであれば、外国人は大して気にもとめていない。むしろ、日本人の多くが自分の発音や文法ミスを恥じて謝る、その態度のほうが気になるようだ。
謙虚なのか、単に自信がないのか、正確さにこだわる几帳面さの現れか、どう捉えられるかは相手次第。つまり、日本人の英会話の最大の課題は、過度に自分の誤りを恐れて萎縮してしまうことだ。発話量が減ることは、コミュニケーションの機会損失につながる。
ここで、「理屈は分かったから、どうすればいいの?」「じゃあ、どういう英語(聞く、読む、話す、書く)が求められているの?」「TOEICや英検などのテストは意味ないの?」といった疑問が当然、浮かぶだろう。ネイティブ英語は必要ないが、「なんでもありの英語」で良いというわけではない。英語のルールから外れ過ぎても通じない。では、「必要最低限ライン」や「許容範囲」は何か。