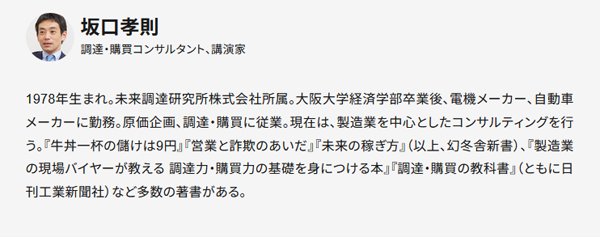なぜネーミングは「卓越」になった?
昭和~平成~令和で日本企業が激変
この一連のネーミング戦略は、終身雇用という日本独自の社会契約を、“突然死”させないための、極めて緩衝材的なツールとして位置づけられるのではないか。
昭和の時代、会社はまるで家族みたいなものだった。家族ならば、途中で何があっても一生を添い遂げる。日本企業は、社員のキャリア全体に責任を負う、家父長的な存在だった。欧米型のレイオフは、暗黙の「みんな家族でしょ」的な契約に対する裏切り行為と見なされていた。
しかし、いつしか企業は、退職を社員による「自己実現のための主体的な選択」として再定義する「発見」をしたのだと思う。筆者は、一方的に企業を責めるつもりはない。常識的な早期退職募集なら何も問題ない。中小企業の対比として責められがちな大企業だが、中小企業のひどい例も多く知っているので、大企業だけを責める気にはなれない。
企業は人員構成の最適化を達成しつつ、社会的な摩擦を最小限に抑えたい意図がある。早期退職の妙なネーミングの役割とは、一つの社会規範からシフトする端境期に、言葉を使って企業と人材に架けられた橋といえる(※またも大げさに言っています)。
現代社会は、企業の持続的成長と、働く人の多様な生き方を尊重する。妙なネーミングは、この二つの大義を両立させるための、苦渋の産物なのだろう。情に厚い日本的経営の「おもてなし」の心とも言えるかも(!?)
ただし私が勧めたいのは、ぜひ社員も会社と、時に闘争しながらも強く生きる姿勢だ。「NEXT STAGE」という名の舞台に送り出されたと思ったら、実際は「EXIT STAGE」でした、なんて顛末だとメシが食えなくなる。「ニューライフ」が天国で始まることに、なってはいけない。
人生100年時代、働く日本人にエールを送りたい。筆者も頑張ります。