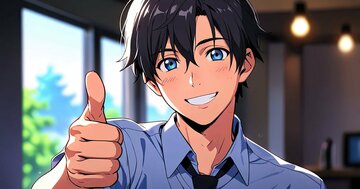「オルカンは最高のスタート」だが、それだけで満足してはいけないワケ
破竹の勢いであっという間に17万部突破のベストセラーとなっている『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』の著者・kenmoさんと、新刊『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』の著者・宇根尚秀さんによる特別対談をお送りする。新NISA(少額投資非課税制度)で、大人気の「オルカン(eMAXIS Slim全世界株式<オール・カントリー>)」や「S&P500(米国株式)」に連動する投資信託を始めた多くの個人投資家に、次の一手となる個別株投資を指南。個人投資家とファンドマネージャーによる「ここでしか語れない」さまざまな話を繰り広げる。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
オルカン・S&P500は「最高のスタート」
kenmo 2024年1月に始まった新NISAを機に、多くの人がオルカンやS&P500といったインデックス積立投資を始めましたが、この現状を宇根さんはどう捉えていますか? 投資のキッカケとしては、とても良いことだと思いますが、将来的に見えてくる「限界」や「物足りなさ」があったりするでしょうか?
宇根尚秀(以下、宇根) オルカンやS&P500への積立投資は、いろいろと考え抜いたうえでの一つの「秘訣」だと考えています。長い人生には投資以外にも様々な要素がありますが、その中で何を成し遂げたいかによって、投資に求めることも変わってきます。
もし「投資に割く時間を一定以下に抑え、他の人生をしっかりと楽しみたい」ということであれば、手間が少なく、世界経済の成長という果実を享受できるオルカンやS&P500への積立投資は、非常に良い選択肢だと思います。
 kenmo(湘南投資勉強会)
kenmo(湘南投資勉強会)1982年愛知県生まれ。大阪大学大学院情報科学研究科修了後、東証一部(現・東証プライム)上場のメーカーに研究員として就職。2011年に4年間で貯めた元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに、会社員を続けながらわずか5年で資産1億円を達成。現在は、約3億円を運用している。2018年個人投資家同士の情報交換を目的とした「湘南投資勉強会」を設立。2023年に中小企業診断士の資格を取得。15年間勤めた会社を辞め、IR支援や企業コンサルティングを行うための法人を設立。現在は株式投資のかたわら、講演活動や、数多くの企業のIR説明会を主催している。『ダイヤモンドZAi』『日経マネー』『日経ヴェリタス』『日本経済新聞』などでの記事掲載多数。初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社)が17万部突破のベストセラーとなり話題に。X:kenmo@湘南投資勉強会3.1万フォロワー YouTube:湘南投資勉強会オンライン チャンネル登録者数1.85万人
一方で、老後も見据えた長期的な資産形成という目的から見れば、オルカンやS&P500への投資は「最高のスタート」と言えるでしょう。実際に積立投資を始めて成功体験を積むと、「楽しい」と感じる方が一定数いらっしゃいます。そうした方々から「次は何をすればいいですか?」と聞かれることも非常に多い。投資が好きな方は、その先を見据えて色々と研究なさるのも良いのではないでしょうか。
プロの短期思考から個人の長期視点へ
宇根 ゴールドマン・サックスにいた当初から、今のような考えを持っていたわけではありません。後から様々な経験を経て、この考えに至りました。ゴールドマン時代は「収益を上げること」が目的として設定されており、それも20年、30年かけてではなく「毎年」収益を出すというルールの下で、パフォーマンスを最大化することが課題でした。ですから、当時は「本当はS&P500への投資がいいのに」といった意識は正直なところありませんでした。
私がプロとして与えられた課題は「毎年収益を上げること」でしたが、一般の個人投資家の皆さんはプロのトレーダーではありません。個人としての投資目的を考えたとき、皆さんの強みは「毎年勝ち続けなければいけない」わけではなく、「20年かけて結果的に儲かっていればいい」という点にあります。この強みを最大限に活かすことを考えたとき、インデックスの積立投資が確度の高いスタイルだと、後から気づいたのです。
ゴールドマンには15年いましたが、キャリアの途中から、投資の目的やその人のリスク許容度によって最適な投資は異なってくることを意識するようになりました。そして、会社を辞めてから、それを自分でも実践するようになった、ということですね。