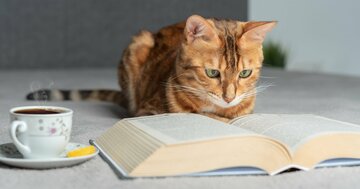ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
「絶滅」と進化の関係
ダーウィンの理論によれば、絶滅は進化の副産物である。広さに限りのある地球上で、新しい種がゆっくりと生まれていく以上は、それに対応して、いくつかの種がゆっくりと絶滅していかなくてはならない。
化石記録は、この予想通りのパターンを示していると、ダーウィンは述べている。
すでにダーウィンの時代の多くの人々は、絶滅を認めていた。そして、生物が絶滅することの説明の一つとして、種にも個体と同じように寿命がある、と考える人がいた。
これは現在でも一定の人気がある考え方で、何の根拠もなく主張されることが多いものの、まれに、それなりの根拠を持って主張されることもある。
人類から男性がいなくなる?
たとえば、哺乳類の性染色体の組み合わせは、オスがXYでメスがXXであるが、Y染色体からは遺伝子が失われやすい。オスはY染色体を一本しか持っていないので、もしY染色体上の遺伝子が損傷したときに、もう一本のY染色体を参照して修正することができないからだ。
哺乳類のY染色体はおよそ三億年前には約一五〇〇個の遺伝子があったと見積もられているが、現在残っているのは約五〇個にすぎない。このペースでいくと、約一千万年後にはY染色体の遺伝子がすべて失われてしまう。
人類も哺乳類の一種であるから一千万年後には男性がいなくなって絶滅すると、この研究は解釈されることもあった。
しかし、アマミトゲネズミのように、哺乳類のオスでY染色体のないものもいるので、おそらくY染色体がなくなっても人類は絶滅しないだろう。
ダーウィンは、種の寿命を仮定しなくても絶滅は説明できると考えており、化石記録から種の寿命を支持する証拠は見つからないとも考えていた。これは現在の進化学の見解と一致している考え方である。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。